電子カルテの導入を検討する際、「クラウド型」という言葉を目にする機会があるはずです。
「クラウド型」と言われても何を表しているのかわからず、スルーしてしまうかもしれません。
そこで、今回はクラウド型電子カルテとは何か、クラウド型電子カルテを導入するメリット・デメリットについて解説します。
記事の後半では、おすすめのクラウド型電子カルテについても解説するので、ぜひ最後までチェックしてみてください。
この記事の内容
クラウド型電子カルテとは?

クラウド型電子カルテとは、クラウド上に電子カルテを置く電子カルテのことです。
従来主流だったオンプレミス型よりも便利に利用できることから、2022年現在ではクラウド型のほうが主流になっています。
オンプレミス型電子カルテでは、院内に全てをサーバーを設置し、管理を自身で行う必要がありますが、クラウド型ではその必要がありません。
他の事業者により管理されているサーバーにアクセスするだけで電子カルテが運用できるため、安価に簡単に利用できます。
クラウド型電子カルテが普及した理由
では、電子カルテの主流がオンプレミス型からクラウド型に移った理由は何があるのでしょか?
それは2010年に厚生労働省が出した『「診療録等の保存を行う場所について」の一部改正』が影響しています。
『「診療録等の保存を行う場所について」の一部改正』が出されるまでは、医療機関における電子化データは院内のサーバーで管理する必要がありました。
しかし、『「診療録等の保存を行う場所について」の一部改正』により、医療機関においてクラウドが解禁されたため、クラウド型電子カルテが普及し始めました。
クラウド型電子カルテを導入するメリット
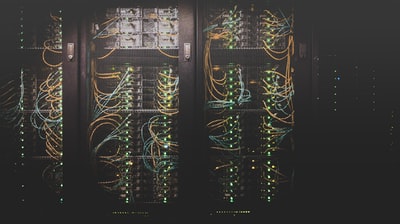
クラウド型電子カルテを導入するメリットは以下の4つです。
- コストがかからない
- 端末・場所の制限がない
- バックアップできる
- 他システムと連携しやすい
1つずつ確認していきましょう。
コストがかからない
1つ目はコストがかからないことです。
オンプレミス型は院内にサーバーを設置する必要があり、多額の初期費用がかかってしまいます。
一方、クラウド型では事業者が用意したサーバーを利用するだけなので、オンプレミス型よりも安価に導入できます。
また、月額料金も必要ですが、1万円〜5万円ほどで利用できることが多いため、大きな負担とならない場合が多いでしょう。
端末・場所の制限がない
2つ目は端末・場所の制限がないことです。
クラウド型では、サーバーに接続できればどんな端末でもどんな場所でも利用できます。
そのため、外出している場合でも利用でき、在宅医療や学会でもカルテを確認できる利点があります。
バックアップできる
3つ目はバックアップできることです。
万が一、院内で火災が発生したり地震で建物が倒壊したりしてしまうと、オンプレミス型の場合、データが全て消失してしまう可能性があります。
しかし、クラウド型では院内ではなく、外部のサーバーにデータが保存されているため、火災の発生や建物の倒壊によりデータが消失する可能性が少なくなります。
そのため、災害対策としてクラウド型電子カルテを導入することも検討すると良いでしょう。
他システムと連携しやすい
4つ目は他システムと連携しやすいことです。
予約システム、問診システム、オンライン診療など、さまざまなWebサービスがあります。
これらのWebサービスとは、オンプレミス型よりもクラウド型のほうが親和性が高いため、連携がしやすいです。
クラウド型電子カルテを導入するデメリット
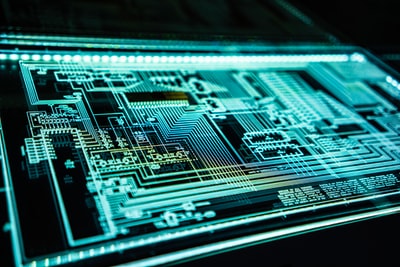
クラウド型電子カルテを導入するデメリットは、以下の3つです。
- インターネット接続が不可欠
- 月額費用がかかる
- カスタマイズが不自由な場合がある
1つずつ確認していきましょう。
インターネット接続が不可欠
1つ目はインターネット接続が不可欠なことです。
クラウド型電子カルテの使用にはインターネットが欠かせず、インターネット接続ができないとデータが確認できません。
医院を円滑に運営するためには、インターネットに接続しているだけでなく、安定した接続ができなければなりません。
そのために新たに回線を契約する必要もあるので、注意してください。
月額費用がかかる
2つ目は月額費用がかかることです。
クラウド型の導入費用はオンプレミス型よりもかなり安価に済みます。
一方、クラウド型は月額費用がかかり、トータルでクラウド型のほうが多くの費用がかかってしまう可能性があります。
そのため、長期的な目線でどちらのほうが高い費用がかかるのかを検討してみましょう。
カスタマイズが不自由な場合がある
3つ目はカスタマイズが不自由な場合があることです。
オンプレミス型電子カルテでは自由にカスタマイズできますが、クラウド型電子カルテの自由度は高くありません。
そのため、製品の仕様に合わせてカルテの使い方を変えなければいけない場合も出てきます。
カルテの使い方にこだわりがある場合は、クラウド型電子カルテよりもオンプレミス型電子カルテのほうが適している可能性があるので、あわせて検討してみましょう。
おすすめのクラウド型電子カルテ6選

ここでは、おすすめの電子カルテランキングを紹介します。
- SymView
- CLIUS
- エムスリーデジカル
- HOPE Cloud Chart II
- Open-Karte Cloud
それぞれの電子カルテについて、特徴や導入費用などを解説します。
SymView

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 特徴 | 電⼦カルテや予約システム等と正式連携し事務作業の効率化を図る |
| 主な機能 | 電子カルテ直接連携(URL連携) QR連携 オンライン診療クロンと正式連携 ⾼度な予備問診による医師問診の省⼒化 |
| 初期費用 | 要問い合わせ |
| 月額費用 | 要問い合わせ |
| 運営会社 | 株式会社レイヤード |
1つ目に紹介するのは、SymViewです。
SymViewは電子カルテではなくWeb予約システムですが、電子カルテとの連携が非常にスムーズなので、ここで紹介しています。
連携方法も2つ用意されており、そのうちのQR連携を使えば、どんな電子カルテでも連携できるのです。
CLIUS(クリアス)

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 特徴 | Mac・Windows・iPadで自由に操作できるクラウド型電子カルテ |
| 主な機能 | WEB問診 予約機能 オンライン診療/在宅診療 バックアップ 薬用量機能 |
| 初期費用 | 200,000円 |
| 月額費用 | 12,000円 |
| 運営会社 | 株式会社DONUTS |
2つ目に紹介するのは、CLIUSです。
WEB問診や予約機能など、電子カルテのみならず様々な機能が搭載されています。
クラウド型電子カルテであり、どのパソコン・タブレットでもログインさえできれば使用できるため、オンライン診療や在宅診療にとても役立つでしょう。
エムスリーデジカル

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 特徴 | 5年連続クラウド電子カルテシェアNo.1(m3.com調査 2022年1月) |
| 主な機能 | M3 DigiKar モバイル 検査結果ビューアー 適応症の自動学習(AI) iPad手書きカルテアプリ 処置行為自動学習(AI) 処方監査オプション |
| 初期費用 | 無料 |
| 月額費用 | 税抜9,800円〜 |
| 運営会社 | エムスリーデジカル株式会社 |
3つ目に紹介するのは、エムスリーデジカルです。
クラウド型電子カルテの中では、かなり広いシェアをとっています。
M3 DigiKar モバイルでは、iPhoneでいつでもどこでもカルテ情報が
HOPE Cloud Chart II

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 特徴 | 導入しやすく柔軟な対応が可能 |
| 主な機能 | 安心安全なシステム構成 フェイルオーバー機能の搭載 24時間365日監視・対応 回線トラブル時も業務継続可能 充実した教育コンテンツ 参考マスタの提供 |
| 初期費用 | 要問い合わせ |
| 月額費用 | 要問い合わせ |
| 運営会社 | 富士通株式会社 |
4つ目に紹介するのは、HOPE Cloud Chart IIです。
富士通が開発した電子カルテで、導入が簡単かつ柔軟な対応が可能な点が特徴です。
安全なシステム構成になっているため、セキュリティ面は余程のことがない限り問題ないでしょう。
Open-Karte Cloud

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 特徴 | スムーズな導入、安全な管理、低コスト |
| 主な機能 | 診療カレンダー機能 アシストビュー機能 部門業務機能 選べる医事会計システム |
| 初期費用 | 要問い合わせ |
| 月額費用 | 要問い合わせ |
| 運営会社 | 富士フイルム株式会社 |
5つ目に紹介するのは、Open-Karte Cloudです。
低コストで、かつ安全な管理ができるため、費用対効果の高い電子カルテだといえるでしょう。
また、会計システムとの連動もできますが、1つの会計システムにしか連携できないわけではなく、複数の会計システムから自身が好みのものを選択できます。
Medicom-CK

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 特徴 | 一般・療養型中小規模病院向け電子カルテ |
| 主な機能 | 患者情報の一括入力機能 受診前相談記録の受診後の患者カルテへ統合可能 |
| 初期費用 | 要問い合わせ |
| 月額費用 | 要問い合わせ |
| 運営会社 | PHC株式会社 |
今回の内容を参考に、クラウド型電子カルテの導入を検討してみてください。



