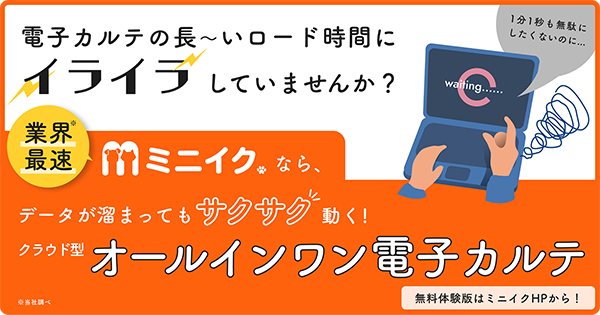「電子カルテの入力に時間がかかり、他の業務を圧迫してしまう」
こんな経験から「電子カルテの入力練習がしたい」とお考えになる方が少なくありません。
電子カルテの入力をスムーズに行うためには、継続した練習が必要になります。
そこで、この記事では、電子カルテの入力をスムーズに行う方法や電子カルテの入力練習におすすめのツールを紹介します。
また、少しのコツを身につけるだけでタイピングが楽になるテクニックも随所で紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
おすすめのサービス
-
Vetty

獣医の経験を持つ開発者が、動物病院ならではの困った「あるある」を解決!
初期費用 0円~(データ移行: 150,000円~) 月額費用 税別35,000円~(お問合せ:利用機能/接続シート数) サポート オンライン講習会・院内での実地講習会・サポートデスク
この記事の内容 [非表示]
電子カルテの入力をスムーズにする方法

電子カルテの入力をスムーズにするにはどんな方法が考えられるでしょうか?
たくさんの方法が考えられますが、ここではその中でも特に有効な5つの方法を解説します。
- タイピングの精度を高める
- ユーザー辞書を使う
- テンプレートを利用する
- 専門用語を覚える
- 音声入力を使う
それぞれの方法にはどのような効果があるのか、1つずつ確認していきましょう。
タイピングの精度を高める
1つ目は、タイピングの精度を高めることです。
タイピングの精度を高める上で重要なのは、スピードよりも正確性を意識することです。
スピードが速くてもミスが多ければその分修正に時間を取られてしまいます。
まずは、タイピングのホームポジションを覚え、キーボードを見ずにミスなくタイピングができることを目指してください。
それができれば、自ずとタイピングスピードも速くなり、結果としてスピードと正確性の両方を手に入れられるでしょう。
ユーザー辞書を使う
2つ目は、ユーザー辞書を使うことです。
ユーザー辞書と言われても、あまりピンとこない方もいらっしゃると思うので、実例を用いながら紹介します。
例えば「よろしくお願いいたします。」と打つとき、「もう少し短く入力できればスムーズにできるのに……」と、入力するのが面倒に感じることがあるかもしれません。
そこで、ユーザー辞書に「よろしくお願いいたします。」の略称を「よろ」と登録しておけば、「よろ」と入力しただけで、「よろしくお願いいたします。」と入力されるようになるのです。
この機能を電子カルテ入力にも使い、よく使用する単語をユーザー辞書に登録しておけば、タイピング時間の短縮につながり、入力がスムーズにできるようになるでしょう。
テンプレートを利用する
3つ目は、テンプレートを利用することです。
電子カルテにはテンプレートが用意されていることがほとんどです。
毎回、同じ内容を入力しなければならない項目があり「面倒臭いな」と感じてしまうことがあるでしょう。
そんな時に、テンプレートをあらかじめ登録しておくことで、ボタン1つをクリックするだけで内容を入力してくれるので、非常に楽に入力できるようになります。
かなりの時間短縮にもつながるので、ぜひ利用してみてください。
専門用語を覚える
4つ目は、専門用語を覚えることです。
電子カルテは医師の先生だけでなく、医療事務に慣れていないスタッフが行うケースも多いため、医療用語に慣れていない可能性があります。
電子カルテの入力中に、聞き慣れない医療用語が出てくると、戸惑ってしまい入力スピードが遅くなってしまうかもしれません。
そのため、医療関係の専門用語は一通り聞いたことのある状態にしておくのが望ましいでしょう。
とくに医薬品について学ぶことをおすすめします。
医薬品の名称自体が難しいこともありますが、医薬品について学べば他の専門用語にも触れることになるため、一石二鳥になるからです。
少し負担が重くなってしまいますが、今後の仕事をスムーズに進めるためにもぜひ挑戦してみてください。
音声入力を使う
5つ目は、音声入力を使うことです。
「どうしてもタイピングが苦手」という方も中にはいらっしゃるはずです。
「いくら練習しても速くならない」「どれだけ練習しても間違いが減らない」という悩みを抱えているのであれば、音声入力を使うのも1つの手です。
音声入力は精度がバラバラだったのですが、近年開発されたツールに搭載されている音声入力機能は高性能なものが多く、かなり誤字が減っています。
もちろん完璧に文字にしてくれるわけではないので多少の修正は必要ですが、一から全て入力するわけではないので、かなり負担が減るでしょう。
電子カルテの入力練習に最適なツール

電子カルテの入力練習はツールを使って行うことも可能です。
ここでは、電子カルテの入力練習に最適なツールを3つ紹介します。
- e-typing
- 電子カルテ代行入力問題集
- 寿司打
それぞれのツールがどのような練習に適しているのかを確認していきましょう。
e-typing

1つ目は、e-typingです。
e-typingはタイピングの精度を高めるために使うサイトで、表示された単語を正確に素早く入力する練習ができます。
表示される単語はジャンル別に指定でき、医療分野や介護分野に特化した練習が可能です。
具体的には医療機器の名称や医療用語、介護用語、歯科用語などのジャンルが用意されています。
医療分野で使う特徴的な単語のタイピング練習ができる機会はあまりないので、ぜひ挑戦してみてください。
電子カルテ代行入力問題集

2つ目は、電子カルテ代行入力問題集です。
この問題集は「宮城県の医師・看護師不足を補うための医師事務作業補助者育成」という事業の中で使用されたものです。
事例として、問診票や実際のやりとりが20個載っているため、かなり実践的な練習ができます。
電子カルテを入力する流れをおさらいしたり入力方法を確認したりするのに大いに役立つでしょう。
寿司打

3つ目は、寿司打です。
寿司打はタイピング練習サイトの中ではかなり有名であり、もしかしたら使ったことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ジャンルは指定できませんが、e-typingと同じように表示された単語をタイピングしていくことで、点数が加算されていき、まさにゲーム感覚でタイピングを楽しめます。
同じローマ字が続く単語など入力しづらい単語が多く表示されるので、かなりタイピングの力が鍛えられるでしょう。
速さを追求する練習、正確さを追求する練習、速さも正確さも追求する練習など、複数のパターンが用意されているので、目的に合わせて使うことも可能です。
まだ使ったことのない方は、一度使ってみることをおすすめします。
おすすめの電子カルテ
電子カルテの入力をスムーズに行うためには、使いやすいシステムを選ぶことも重要です。そこで、記事の最後におすすめの電子カルテサービスをご紹介させていただきます。
- ミニイク
- PETORELU+
- Vetty
ミニイク
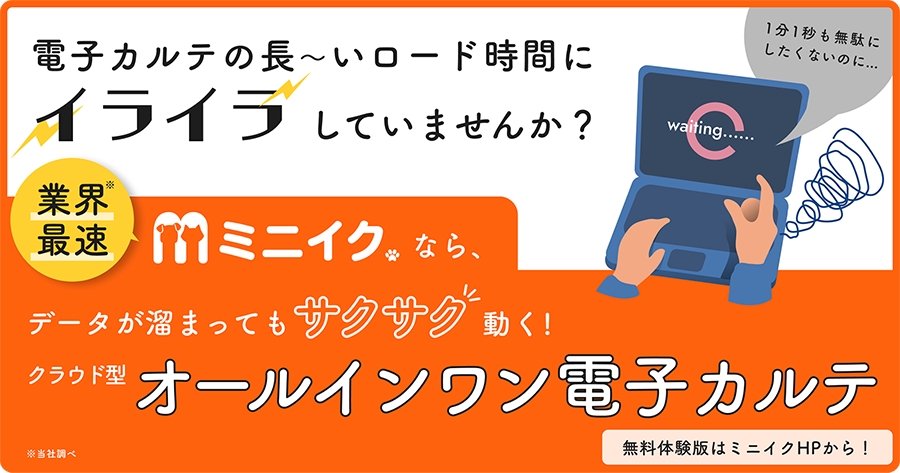
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 特徴 | 「予約から会計まで」動物病院の業務をまるっと一元管理できる電子カルテ |
| 主な機能 | オンライン予約(問診あり) 顧客管理 電子カルテ(手書き対応可) レセプト 入院・ホテル管理 リスト抽出(DM) 調剤 売上・統計 会計(保険魔導口精算対応) クレジット決済、現金決済、QRコード決済 各種帳票出力 各種機器連携(決済、医療機器等) シフト管理 自動バックアップ |
| オンプレミス型/クラウド型 | クラウド型 |
| 初期費用 | 0円 |
| 月額費用 | お問い合わせ |
| 運営会社 | ミニイク株式会社 |
| ホームページ | https://miniique.com/ |
ミニイクは、現場経験がある獣医師とエンジニア、デザイナー目線で使いやすい見た目にこだわったクラウド型オールインワン電子カルテシステムです。
オンライン予約とCRM、電子カルテ、レセプトが連動しているため、予約~診察~会計までがスムーズになります。面倒だったカルテの転記作業をする必要がなくなり、薬剤の自動計算や保険適用なども行えます。
また、サクサクと動かせるのもミニイクの特長。画面の移動やデータの読み込みが早いだけでなく、手書きのスケッチやメモを取ることもできます。誰でもわかりやすく直感的に使用できるので、電子製品が苦手な方でも安心してご利用いただけます。
動物病院の運営に必要なサービスをまるっと一括したミニイクなら、雑務を極限まで減らし、動物病院で働く皆さまの心をラクにしてくれるでしょう。
PETORELU+

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 特徴 | 予約管理から会計決済、電子カルテ登録まで、診療プロセス全体をシームレスに管理 |
| 主な機能 |
電子カルテ 予約管理 顧客管理 ネット予約 勤務表・シフト表 集計機能 リマインダー |
| オンプレミス型/クラウド型 | クラウド型 |
| 初期費用 | 0円 |
| 月額費用 |
月額費用 予約プラン 6,600円 電子カルテAプラン 19,800円 電子カルテBプラン 26,400円 |
| 運営会社 | ピクオス株式会社 |
| ホームページ | https://www.plus-petorelu.jp/ |
PETORELU+(ペトレルプラス)は、予約・会計・電子カルテのすべてが連携した、動物病院向けのクラウド型電子カルテシステムです。クラウドベースなのでインターネット環境さえあれば、院内外問わずどこからでも利用可能です。
視覚的に分かりやすいカレンダー形式の画面で、予約や診療スケジュールも直感的に把握できます。予約、診察、会計にまたがる情報はすべて自動で連携されているため、手入力の手間やミスを大幅に削減します。診療明細の作成もスムーズで、ペット保険にも対応しているため、受付業務の負担も軽減されます。導入したその日からすぐに使えるシンプルな設計で、PC操作に不慣れなスタッフでも安心して使いこなせます。また、飼い主様は24時間WEB予約が可能なため、時間制限のある電話予約が不要になることで、予約を入れやすくなり、より気軽に診療の機会を提供できることになるでしょう。
料金プランは複数用意されており、初期費用を抑えて導入したい方から、機能をフル活用したい方まで、動物病院の規模や業務内容に合わせて最適なプラン設計が可能です。「まずは使い勝手を試してみたい」という方には無料体験も用意されています。
PETORELU+は、動物病院の診療から経営までをトータルに支える、飼い主様にとってもスタッフにとっても使いやすい現場目線の電子カルテシステムと言えるでしょう。
Vetty

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 特徴 | 特許AIカルテ生成「声でカルテ®」搭載でカルテ作成時間が50%改善・1秒で処方箋の登録ができる電子カルテ |
| 主な機能 |
オーナー・ペット管理 SOAP型診療カルテ 処方箋の自動計算・過去の複製機能 注射点滴量の自動計算・過去の複製機能 医薬品の早見表登録 レセプト会計 日計/日報出力 DMハガキ印刷・デジタルDM 既往歴・プロブレムリスト管理 院内メッセージ 院内タスク管理 入院管理・ごはん給餌管理 スケジュール管理 オーナー向け「myVetty(マイベッティ)」アプリ(Line連携) AIカルテ生成 |
| オンプレミス型/クラウド型 | クラウド型 |
| 初期費用 | 0円~(データ移行: 150,000円~) |
| 月額費用 | 税別35,000円~(お問合せ:利用機能/接続シート数) |
| 運営会社 | 株式会社MOTOCLE |
| 公式サイト | https://vetty.clinic/ |
Vetty(ベッティ)は、獣医療現場で必要な情報をすべて一か所に集約した、次世代の電子カルテシステムです。
オーナーの整理券発行、自動受付、電子カルテ、保険会計、院内タスクがすべて連携しており、過去の治療記録も簡単に確認・複製できるため、再診の対応がスムーズです。
さらに、AIが診療中の音声を自動で文書化・要約するため、手入力の手間が大きく省け、診療に専念できるのも大きなメリットです。
※AI自動カルテ生成機能のみを使いたい場合は「声でカルテ®」の導入がおすすめです。
検査機器との連携や、手入力で検査や評価内容を柔軟に管理することが可能です。また、早見表や力価・錠剤分割機能を活用すれば、処方箋や注射点滴の登録を1秒で行うことができます。
さらに、オーナー向けアプリ「myVetty」を利用すると、検査結果やお知らせなどをオーナーに自由に送付でき、myVetty決済を使えば代金の前払い・後払いにも対応可能です。
1名の病院様から、1拠点で従業員60名の診療規模の動物病院様まで、幅広く業務をサポートしている実績がある電子カルテです。パソコンやタブレットからアクセスできるため、院内どこからでも利用できるのも魅力のひとつです。
また、電子カルテを切り替える際には、画像や過去の検査結果など柔軟なデータ移行にも対応可能です。導入時のサポートもあるため、スムーズに使い始めることができます。
公式HPはこちら
まとめ

今回は、電子カルテの入力練習について解説しました。
後半で紹介したようなツールを使って、地道にコツコツ練習することが大切です。
大変ではありますが、毎日10分でも良いので練習してみてください。
また、前半で紹介したユーザー辞書やテンプレートなどのテクニックは、今日からでも使えるので、ぜひ試してみてください。