「デジタルサイネージが気になっているけど、具体的にどのような種類があるのだろう……」
「デジタルサイネージの効果的な利用方法を知りたい……」
デジタルサイネージは、目に留まりやすい魅力的な情報を配信・表示できるツールで、さまざまな企業や医療機関が導入しています。
一方で、デジタルサイネージはさまざまな種類があり、目的に合った種類を選択することが必要です。
そこで本記事では、デジタルサイネージの種類や費用相場について解説します。デジタルサイネージを導入する際のコツについても解説しているので、参考にしてみてください。
この記事の内容
デジタルサイネージとは?

デジタルサイネージとは、液晶ディスプレイやプロジェクターなどを活用し、映像や情報を表示できる電子的な看板・掲示板です。
近年では、商業施設や駅構内、医療機関など多種多様なシーンで利用されています。
画像だけでなく、動画も表示させられるため、多くの方の目に留まりやすく、視覚的に魅力のある情報を配信可能です。
たとえば、商品・イベントのPRや、休診情報や健康コラムなどの情報を表示したいというときに活躍してくれます。
デジタルサイネージの種類

デジタルサイネージの種類は、4種類あります。
- スタンドアローン型
- ローカルネットワーク型
- クラウド型
- インタラクティブ型
各種類ごとの魅力を解説していきます。
スタンドアローン型
スタンドアローン型は、単独設置型とも呼び、ネットワークが不要で、USBやSDカードから直接コンテンツを再生するタイプです。
設置と運用が簡単で、小規模な施設や一時的な情報掲示を行いたいときに向いています。
たとえば、個人クリニックや歯科医院の待合室などにおすすめで、USBに保存したインフルエンザの予防接種の案内や、診療時間の変更のお知らせなどを簡単に表示可能です。
小規模でも効果的な情報発信ができるため、多くの医療機関・小規模施設におすすめです。
ローカルネットワーク型
ローカルネットワーク型は、LANを活用して複数台の管理を行える種類です。
パソコンで情報を一括管理できるため、配置場所や目的に合わせて効果的な配信が行えます。
たとえば、中規模病院の複数階に設置した案内サイネージを、中央管理室のPCから一斉更新できます。また、各診療科の診療スケジュールや担当医の情報などを、院内全体で統一させることも可能です。
外部との通信がないため、セキュリティ面も安心できる点が魅力です。
クラウド型
クラウド型は、インターネットを通じて、遠隔地から管理・更新が可能なタイプです。
多拠点に展開している場合に強く、最新情報を即時に反映できます。たとえば、医療法人グループが運営する複数の診療所・クリニックに向いているでしょう。
本部が各施設のサイネージを一括管理し、コロナワクチン情報や季節性の健康情報をタイムリーに配信するなどが行えます。
デバイスの状態監視や、スケジュール配信も可能です。
インタラクティブ型
インタラクティブ型は、双方向型とも呼び、タッチパネルやセンサーを使い、ユーザーと双方向にやり取りができます。
総合案内のタッチパネルなどが、インタラクティブ型に該当します。案内検索やアンケート、受付補助などが可能で、ユーザーが求める情報を案内しやすい点が魅力です。
また、外国語対応や音声ガイドも搭載しており、外国人患者にも配慮できます。
受付混雑を緩和し、スタッフの負担軽減にもつながる点がメリットといえるでしょう。
デジタルサイネージの仕組み

デジタルサイネージは、映像や動画などのコンテンツをパソコンで作成し、サイネージ端末に送って再生・表示する仕組みです。
たとえば、デジタルサイネージを活用したい場合は、まず診療時間・休診時間のお知らせ、健康情報などをパソコンで作成し、USBメモリやSDカードなどに保存します。
コンテンツの作成が終わった後は、配信方法に合わせてサイネージ端末に情報を送ります。
スタンドアローン型であればUSBメモリやSDカードを使用し、ローカル型は院内のLANで配信、クラウド型はインターネット経由で遠隔から情報を送りましょう。
デジタルサイネージに情報が届いた後は、ディスプレイやタブレットに内蔵された再生機器で、届いたコンテンツを再生・表示します。
デジタルサイネージの費用相場

デジタルサイネージの費用相場は、ディスプレイ形式によって費用が異なります。スタンド型や壁掛け型の費用、ランニングコストなどについて解説します。
スタンド型の費用相場
スタンド型の費用相場は、ディスプレイのサイズや、屋内・屋外で使用するかによって変わります。
| ディスプレイ | 屋内用 | 屋外用 |
|---|---|---|
| 32~42インチ | 10万〜30万円 | 40万〜80万円 |
| 43~55インチ | 11万〜40万円 | 40万〜140万円 |
たとえば、屋内で使用する場合は、32~42インチであれば10~30万円、43~55インチであれば11~40万円が相場です。
一方、屋外で使用する場合は、同じ32~42インチでも40~80万円、43~55インチで40~140万円が費用相場になります。
屋外で使用する場合は、屋内と比べて、外気や雨にさらされるため、耐久性の高いディスプレイの設置が必要です。
壁掛け型の費用相場
壁掛け型の費用相場は、以下のとおりです。
| ディスプレイ | 屋内用 | 屋外用 |
|---|---|---|
| 通常ディスプレイ | 42インチ:15万円~ | 98インチ:~300万円 |
| マルチ専用ディスプレイ | 42インチ:20万円~ | 屋外では使用されない |
壁掛けタイプは、インチ数によって費用相場が大きく変わります。
また、複数画面対応のマルチ専用ディスプレイは、通常ディスプレイと比べてやや費用相場が高いです。
目的や配信したいコンテンツに合わせて、ディスプレイタイプや設置場所を選ぶようにしましょう。
ランニングコストの費用相場
デジタルサイネージのランニングコストの費用相場は、以下のとおりです。
- CMS利用料:2,000円~10,000円/月額
- 電気代:1,000円~2,000円/月額
- 保守・運用費用:機器価格の5~10%/年間
- コンテンツ制作費用:静止画1万~3万円・動画(約2分)で10万円程度
- 通信費:5,000~8,000円
たとえば、コンテンツ制作費用は、静止画にするか、動画にするかによって大きく変わります。
また、自社制作であれば、静止画は1万~3万円・動画であれば10万円程度で製作可能です。
一方、プロに依頼する場合は、数十万円から数百万円までの幅があり、静止画でも30万~50万円規模になってしまうケースもあります。
また、電気代も1日8時間稼働させるのか、24時間稼働させるのかによっても変わるため、使用状況に合わせてランニングコストを考えるのが良いでしょう。
レンタルの費用相場
デジタルサイネージは、レンタルサービスもあります。
レンタルサービスの場合は、ディスプレイの対応やインチ数・設置環境によって費用相場が変わります。
たとえば、通常ディスプレイの場合は、月額費用が8,400円以上で、初期費用が18,000円を超えるケースが少なくありません。
一方、マルチ専用ディスプレイだと、月額費用は10,400円以上で、初期費用が18,000円を超えます。
屋外に設置する際には、保護ケース料金が発生するため、さらに費用がかさむ点を考慮しておきましょう。
また、レンタルの場合は、ディスプレイを使っている期間によって毎月支払う金額が変わる場合もあるため、さまざまな費用を考慮したうえで予算内に収まるか検討してください。
デジタルサイネージを導入する6つのメリット

デジタルサイネージを導入するメリットは、6つあります。
- 動画と音声で視覚・聴覚どちらの訴求も可能
- 特定のターゲットにアプローチしやすい
- 複数台・複数拠点の配信管理ができる
- インタラクティブな体験を提供できる
- 配信日程や時間スケジュールの管理がしやすい
- AI分析や音声認識システムもある
それぞれのメリットについて解説します。
動画と音声で視覚・聴覚どちらの訴求も可能
デジタルサイネージのメリットは、動画と音声で視覚・聴覚のどちらの訴求もできます。
たとえば、音声を入れることによって、デジタルサイネージを見ていない不特定多数の人に対しても情報を発信できます。
また、音声を入れることで聴覚に訴えかけ、記憶に残る体験を生み出すことが可能です。
動画で視覚・音声で聴覚に訴求できるため、デジタルサイネージを利用する際にはこだわってみてください。
特定のターゲットにアプローチしやすい
特定のターゲットにアプローチしやすい点は、デジタルサイネージのメリットです。
デジタルサイネージは、時間帯や曜日にあわせて表示する内容を変えられるため、年齢層や性別などに応じて魅力的な情報を発信できるでしょう。
たとえば、午前中は小児科の患者が多い場合は、予防接種のスケジュールや虫歯予防のアニメを流し、午後からは、糖尿病予防や運動療法などの案内を流すなどができます。
有益な情報発信は、利用者の満足度向上を図れるため、デジタルサイネージの活用はおすすめです。
複数台・複数拠点の配信管理ができる
デジタルサイネージは、複数台・複数拠点の配信管理ができます。
一括でコンテンツを配信・更新できるため、本部から複数のクリニックや病院に一貫した情報発信が可能です。
たとえば、医療法人グループ全体で、熱中症対策の動画を一斉配信できます。
各拠点で同じ内容をタイムリーに伝えられるため、情報のばらつきや更新漏れを防げます。
インタラクティブな体験を提供できる
デジタルサイネージは、インタラクティブな体験を提供できる点がメリットです。
タッチパネルやセンサーを使って、患者が自分で情報を選んで操作できる仕組みも導入できます。
たとえば、院内にあるサイネージで、診療科の案内や、医師のプロフィールをタッチ操作で閲覧することも可能です。
初診患者が迷わず、目的の診療科にたどり着けるようになるでしょう。
配信日程や時間スケジュールの管理がしやすい
配信日程や時間スケジュールの管理がしやすい点は、デジタルサイネージのメリットです。
特定の時間帯や曜日に合わせて、自動でコンテンツを切り替えられます。たとえば、月曜日の朝は混雑注意のお知らせ、毎週金曜日には土曜診療の案内などに設定することが可能です。
手作業で切り替える手間がなく、スタッフの負担を軽減できるでしょう。
AI分析や音声認識システムもある
デジタルサイネージは、AI分析や音声認識システムもあります。
カメラやマイクを連携させることで、視聴者の属性や音声での対話・案内が可能です。
たとえば、顔認識で年齢や性別を判別し、子どもが近づいたときだけ小児科のQ&A動画を再生させることもできます。
また、音声で診療受付の場所を質問された際に、音声ガイドで誘導することも可能です。
感染対策と利便性を両立させられるため、患者の満足度を高めやすいでしょう。
デジタルサイネージの効果を高めるコツ
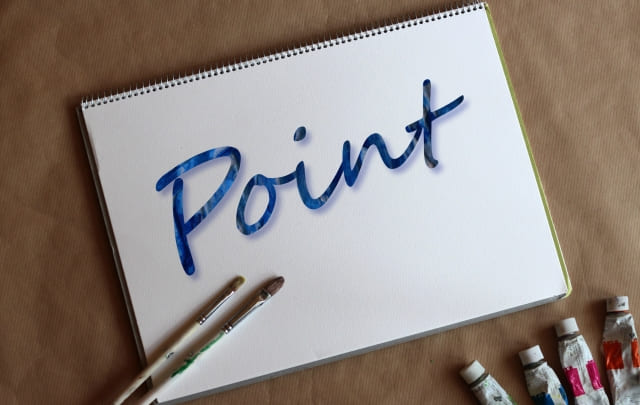
デジタルサイネージの効果を高めるコツは、5つあります。
- ターゲットを明確に設定する
- ディスプレイのサイズを意識する
- 設置する場所を考慮する
- 刺激を与えるような画像・映像にする
- 外国語にも対応させる
それぞれのコツについて解説していきます。
ターゲットを明確に設定する
デジタルサイネージを効果的に運用するコツとして、ターゲットを明確に設定しましょう。
誰に向けて情報を発信するのか、年齢や性別、症状、関心などを明確にすると、内容の精度が高まり、関心を引きやすくなります。
たとえば、小児科の前では、予防接種スケジュールや、発熱時の対応などを配信すると、有益な情報として注目してもらいやすいです。
ほかにも、内科では高血圧の予防や、生活習慣病対策を中高年向けに配信すると、良いでしょう。
誰に見せたいか決めることで、訴求力が高まりやすいです。
ディスプレイのサイズを意識する
デジタルサイネージを利用する際には、ディスプレイのサイズを意識すると良いでしょう。
設置場所や見る距離を考え、見やすいディスプレイを選ぶことが大切です。文字や映像が小さすぎると、効果が激減してしまう可能性があります。
そのため、設置場所に合わせてディスプレイのサイズにこだわってみてください。
設置する場所を考慮する
デジタルサイネージを上手に活用するコツは、設置する場所を考慮することです。
人が立ち止まりやすい場所や、目に入りやすい位置に設置することで、自然に注目を集められます。たとえば、受付横や待合室の中央など、視線が集まりやすい場所に設置すると良いでしょう。
無意識のうちに目に入る場所が効果的です。
刺激を与えるような画像・映像にする
デジタルサイネージは、刺激を与えるような画像・映像にすることが大切です。
動きのある映像や、明るく目を引くデザインを使うことで、「つい見てしまう」という状態を作れます。
たとえば、食事指導の映像を流したい場合、イラストやアニメを使って動きのあるコンテンツにすると、見た人の記憶に残りやすいです。
ほかにも、色鮮やかでメリットが伝わりやすいビジュアルにすると良いでしょう。
外国語にも対応させる
デジタルサイネージを効果的に運用するコツとして、外国語にも対応させるのがおすすめです。
外国語に対応させることで、外国人患者に伝わりやすいです。インバウンド対応や、地域の外国人居住者にも安心感を提供できるでしょう。
診療案内や受付方法を表示させるときに、日本語・英語・中国語など交互に表示させるとわかりやすいです。
デジタルサイネージを利用する際に必要なもの

デジタルサイネージを利用する際に必要なものは、以下の機器です。
- 映像を配信するためのディスプレイ
- セットトップボックス(STB)またはパソコン
- 配信用のコンテンツ
- その他の周辺機器やケーブル
まずは、デジタルサイネージを映すためのディスプレイを用意しましょう。
設置場所によって、ディスプレイのサイズや種類が変わります。
ほかには、映したい画像・動画などのコンテンツや、ディスプレイにコンテンツ内容を送るためのSTBまたはパソコンが必要です。
配信環境の整備として、その他周辺機器やケーブルも用意しましょう。
配信環境の整備には、手間とコストがかかるため、必要なものを洗い出して計画的に準備を進めてください。
デジタルサイネージ導入の流れ

デジタルサイネージを導入するときは、5つの流れで進みます。
- 導入計画を策定
- 機器の選定やシステム設計・構築
- 設置工事・画像調整
- コンテンツの制作・配信
- 運用・保守
それぞれの流れについて解説します。
STEP1.導入計画を策定
デジタルサイネージを利用したいときは、まず「デジタルサイネージをなぜ導入するのか」「どこで使うのか」「誰に何を伝えたいのか」などの目的と方針を明確にしましょう。
目的や方針が定まっていないと、誰にもささりにくい内容になってしまい、興味を持ってもらいにくいです。
たとえば、「患者向けに健康情報提供したい」「受付業務の負担を減らしたい」などの課題や目的に合わせて、導入方針を整理しましょう。
STEP2.機器の選定やシステム設計・構築
デジタルサイネージを利用する目的や方針が明確になったあとは、機器の選定やシステム設計・構築を行いましょう。
具体的には、目的に合ったディスプレイのサイズ・台数、設置場所、配信システムなどを選定することが必要です。
たとえば、本部から複数拠点へ一括配信したい場合、クラウド型システムの導入などがあげられます。
医療現場の環境に合わせたシステムを構築しましょう。
STEP3.設置工事・画像調整
機器の選定やシステム設計・構築が終わったあとは、設置工事・画像調整を行いましょう。
選んだ場所に実際にモニターを設置してみて、電源やネットワークの工事、画面の明るさ・角度の調整を行います。
たとえば、通行の邪魔にならず、見やすい高さや角度で設置することが重要です。
ほかにも、日光が入る場所では、光が反射しないように光対策モニターを使用しましょう。患者導線と安全性にも考慮することも大切です。
STEP4.コンテンツの制作・配信
設置工事や画像調整を行ったあとは、コンテンツの制作・配信をしましょう。
実際に表示する画像や動画、文章などのコンテンツを作成し、配信スケジュールを設定します。
たとえば、混雑時には待ち時間の目安を自動表示、季節に応じた内容を配信するなどを設定しましょう。
医療現場に合わせて、情報の質とタイミングにこだわるのがおすすめです。
STEP5.運用・保守
デジタルサイネージの導入後は、定期的なコンテンツ更新や機器の点検、トラブル時のサポート体制の構築などが必要です。
担当スタッフが簡単に更新できるような運用体制にすると良いでしょう。
ほかにも、故障時にはすぐ対応できる業者と保守契約を結ぶのがおすすめです。
長期的に安定した運用をするためには、保守体制の整備が欠かせないため、入念に確認しましょう。
まとめ:デジタルサイネージを理解して的確な種類を選択しよう

デジタルサイネージは、さまざまな種類があり、目的や方針を明確にしたうえで選ぶと良いでしょう。
とくにデジタルサイネージを運用する際には、コンテンツの明確化や設置場所・サイズにこだわるのがおすすめです。
動画や画像で魅力的な情報を配信できるため、デジタルサイネージを利用したい方は本記事でご紹介した内容を参考にしてみてください。


