糖尿病(2型糖尿病)(トウニョウビョウ)の原因
体内に摂取した糖分をエネルギーに変える糖代謝システムが正常に働かなくなり、糖分を使わないため血液中の当分がたまってきて高血糖になる状態。糖尿病は大きく2つに分類される。ひとつは、食事から摂取したブドウ糖を細胞に取り込み、エネルギー源に変える作用を促進するインスリンが、膵臓のβ細胞が破壊されることによって分泌されなくなる1型糖尿病。もうひとつが、よくない生活習慣が引き金となり、インスリンの働きが低下して高血糖状態が続く2型糖尿病である。糖尿病(2型糖尿病)(トウニョウビョウ)の症状
のどの渇きや倦怠感、多尿、体重減少などの症状がみられるが、初期はほとんど症状がない。進行すると、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害などの合併症をともなう。糖尿病(2型糖尿病)(トウニョウビョウ)の治療
通常の社会生活を送ることができるよう、カロリーを抑える食事療法と運動療法が治療の基本となる。まず食事療法があり、次に運動療法、そして薬物療法となり、種類や症状によって、この3つを組み合わせて治療を進めていく。- 受診科目
- 内科
- 糖尿病内科
- 代謝内科
- 内分泌内科
この病気について21人の医師の見解があります。
医師から聞いた
糖尿病(2型糖尿病)の対処(治療)方法
21件中1~20件を表示


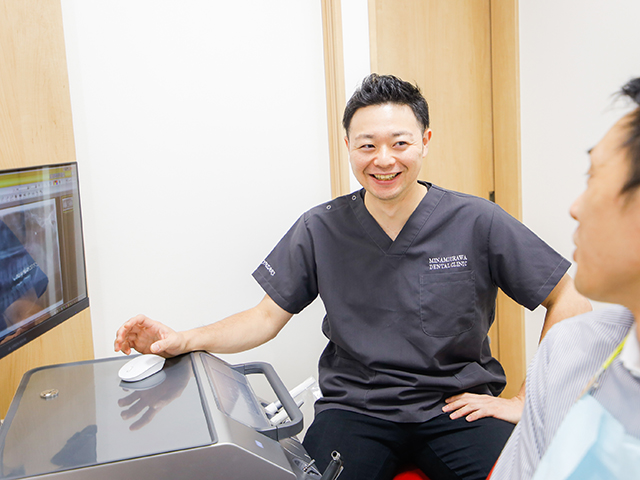







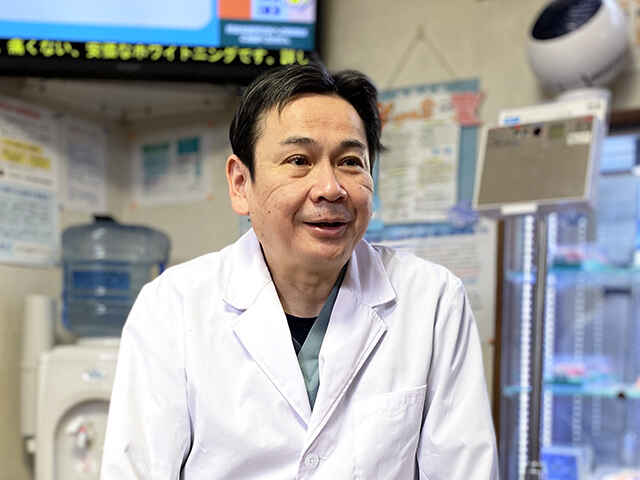











糖分が口中に停滞している「時間」が長いほど、虫歯は発生しやすくなる
虫歯の菌が歯を壊しているような画像をご覧になったことがあるかと思いますが、あれはイメージにすぎません。実際に、虫歯菌が直接歯を壊しているわけではなく、虫歯には、発生に至るメカニズムがあります。「時間」と「食事」、そして「菌」。これらが合わさることで虫歯が発生します。具体的には、食べ物に含まれる糖分を菌が分解し、酸を生み出します。その酸が歯を溶かしてしまうのです。逆に言えば、菌があっても、糖分がなければ虫歯は発生しないことになります。糖分が口中に停滞している時間が長ければ長いほど、虫歯は発生しやすくなります。それを防ぐべく、「だらだら食べ」や、「だらだら飲み」を避け、正しい歯みがきを続けていくことが大切です。