「病院の順番が長いと言われてしまった」
「クレームは入っていないが、順番待ちの時間を短縮したい」
病院は順番待ち時間が長いというイメージを持っている人は少なくありません。待ち時間が長いと、患者にストレスを与える恐れがあります。
そこで本記事では、病院の順番待ち時間を短縮するための方法や順番待ちシステムのおすすめを6つご紹介します。
おすすめのサービス
この記事の内容 [非表示]
病院の待ち時間が長い理由

「病院は待ち時間が長い」と感じられている患者も多いです。
では、なぜ待ち時間が長いのか、その主な理由は以下の3点です。
- 患者数が多い
- 急患で順番が前後することがある
- 地域によって医療機関の数に差がある
患者数が多い
病院の待ち時間が多い理由でまず考えられるのは、患者数が多いことです。
厚生労働省によると、外来患者の診察までの待ち時間は、最も多い割合が「15分未満」の27.9%ですが、「15分~30分未満」が 25.8%、「30分~1時間未満」が20.9%と、15分以上も待っている人は約半数います。
1時間以上待つという人は21.9%もいて、それだけ多くの患者が病院を訪れているということが考えられます。
令和2年に厚生労働省により実施された調査によると、ある1日の集計客体数(患者数)は、入院・外来あわせて病院が6,185施設に対し180.6万人、一般診療所が5,587施設に対し27.5万人、歯科診療所が1,217施設に対し2.6万人です。
毎日多くの患者が訪れると、その分順番待ちも待ち時間も長くなります。
参照1:令和2(2020)年受療行動調査(概数)の概況|厚生労働省
参照2:令和2年(2020)患者調査の概況|厚生労働省
急患で順番が前後することがある
急患(急病の患者)が訪れると、優先的に診察・治療を行わなければなりません。そこで受付済みの患者や予約済みの患者の順番が前後することがあります。
急患が入るのは、救急車で搬送されてくるような大きな病院に限らず、中小規模の内科や小児科などでも可能性はあります。
例えば、著しい高熱や、耐え難い腹痛や歯痛が収まらない場合などは、予約なしでも優先的に診察する必要があるでしょう。
緊急で処置を行う場合は長く時間がかかり、予約時間通りに進まないこともあります。結果的に、待ち時間が長くなってしまいます。
地域によって医療機関の数に差がある
地域によって医療機関の数に差があることも、待ち時間が長くなる原因の一つです。
厚生労働省の調査によると、令和4年の一般診療所の数は105,182軒です。
病院、歯科診療所も含めると181,093軒に上ります。
都道府県別にみると、同じ関東圏でも令和4年の東京都の一般診療所は14,689軒に対し、群馬県は1,582軒と10,000軒以上の差があります。
人口10万対施設数で見ると、東京都は104.6と人口に対して十分な数がありますが、群馬県は82.7とやや少ないことが分かります。
参照1:令和4(2022)年医療施設(動態)調査・病院報告の概況-医療施設調査 |厚生労働省
参照2:令和4(2022)年医療施設(動態)調査・病院報告の概況-統計表3 都道府県別にみた施設数及び人口10 万対施設数|厚生労働省
人口に対して医療施設数が少ない地域だと、混雑しやすい医療機関も多くなるでしょう。
混雑しやすい医療機関では、医師は一人当たりの患者の診察に割ける時間が少なくなってしまいます。
患者は「あれだけ待ったのに、診察はすぐに終わった」と不満に思ってしまうケースも少なくありません。
病院の受付方法は2種類

病院の受付方法は、以下の2種類があります。それぞれの特徴を把握して自院にはどちらがあっているかを判断しましょう。
- 順番待ち制
- 予約制
順番待ち制
順番待ち制とは、来院順に患者の受付した順番を管理するシステムです。
直接病院で受付をして院内で呼ばれるのを待つこととなります。
「院外へ外出してもいい」という病院もありますが、Web上でリアルタイムの順番が確認できないデメリットがあります。
呼ばれるまでに戻らなければ順番を飛ばされることから、結局院内で待つという患者も多くなり、院内が混雑しやすくなって座れず立って待つ患者も出てきてしまいます。
Webシステムと連携して運用する場合は、インターネット上で診察が終わった順番をリアルタイムで閲覧できます。
受付だけして受付順の番号の紙が発行されれば、そのあとは院外で順番が近くなるまで時間を潰して待つという方法が取れるメリットがあります。
最近では順番待ち制ではあるものの、Webでの順番予約だけを取る方法を導入している医療機関も増えてきています。
予約制
予約制とは、日付ごと・時間ごとに予約を取る方法です。
日ごとに順番だけを事前予約する方法と、時間帯ごとに予約を取る方法の2通りがあります。
順番予約の場合は、順番待ちのためのWebシステムを導入すれば、スマートフォンから事前に順番予約が取れます。
診察開始後も順番をWeb上で確認できるため、順番が近くなってから来院できるメリットがあります。
時間帯ごとに予約を取る場合は、「〇〇日の10時10分からはこの患者」「10時20分からはこの患者」と時間帯ごとに診察・処置を行う患者を分けることで、予定通りに処置を進めていけます。
歯科医院や眼科などのように、1人あたりの診察や治療の時間が長くなりやすいクリニックに適している予約受付方法です。
時間予約を取り入れるうえで気を付けたいのは、予約した時間から大きく遅れてしまった場合に「何のための予約なのか」と不満を感じられる場合があることです。
自院のキャパをしっかり管理して、適切な人数の予約を受け入れましょう。
順番待ちと予約制はどっちがいい?判断方法を解説

では実際、順番待ちと予約制はどっちがいいのでしょうか。
多くの病院では、順番待ち制度を採用しています。しかし、自院の患者の年齢層や、経営面で見てどちらが効率がいいかなどを鑑みて判断しましょう。
主な判断基準は、以下の3点です。
- 混雑しやすい診療科目か
- 待合室・駐車場のキャパシティに余裕はあるか
- 効率か利便性どちらを優先するか
1.混雑しやすい診療科目か
まず、自院の診療科目によって順番待ちが適しているか、予約制が適しているかが変わります。
診療科目によって、混雑度合いは異なります。お年寄りの患者が多い診療科目では、朝の時間帯から、働き世代が多い診療科目では夕方以降の時間に混雑しやすいです。
順番待ち制で待ち時間の目安が表示されるシステムなら、朝一で来院した時点で100分待ちと表示を目にすれば、諦めて他の病院に行ってしまう恐れがあります。
一方で、時間帯予約制であれば9:00の予約は埋まっているけど、10時の予約は空いているという状況なら予約を取ってくれる可能性があります。
混雑しやすい診療科目なら予約制を取り入れたほうが患者側も来院時間を決めて予定を立てやすいですし、円滑に診療を進められると考えられます。
朝の時間帯に混雑しやすい診療科目は、緊急性が高い患者が多い傾向にある小児科や婦人科などが挙げられます。
患者数は多いものの、緊急性の低い患者が多いと考えられる耳鼻科や皮膚科は、比較的時間帯ごとに患者の数が分散されやすいです。そのため、順番待ちはもちろん、時間帯ごとに何人までと受付数を決める時間帯予約制、順番予約制もマッチしているでしょう。
2.待合室・駐車場のキャパシティに余裕はあるか
待合室や駐車場の受け入れられる数に余裕があるかによっても判断できます。
小さなクリニックの場合、待合室もあまり大きくないと考えられるため、一度に多くの患者が来院すると待たせてしまう恐れがあります。
順番待ち制の場合、早めに受付した人以外は待合の椅子に座れず、立って待つか、院外で待つこととなります。
予約制を取り入れれば、こうしたデメリットも解消できるでしょう。
しかし、「待合室・駐車場のキャパシティに余裕がなければ予約制が合っている」とは言い切れません。
予約制をとっても、その時間帯から実際の診察時間が大きく遅れてしまうと、不満に感じる患者も増えてしまうためです。
時間帯予約制を導入しても診察に遅れが生じてしまう場合は、順番待ち制の予約受付を導入するとよいでしょう。
3.効率か利便性どちらを優先するか
効率か利便性どちらを優先するかも判断材料の一つです。
これは院長の考え方によるもので、当然どちらも大事ですが優先順位を決める必要があります。
業務上の効率を優先する場合は、順番待ち制を採用することとなります。
予約制の場合は、受付スタッフの電話応対が増えるというデメリットがあります。しかし、順番待ちなら、受付するだけでいいため業務負担が軽減されるでしょう。
ネット予約を導入しても、年配の患者などスマホ操作に慣れていない方は電話で予約されることが予想できます。完全にゼロにはできないでしょう。
しかし、患者目線で考えると予約制にしてほしいと考える人もいるため、患者にとっての利便性は下がってしまいます。
予約制の方が患者は予定が立てやすく、来院時間をコントロールしやすくなります。
どちらにもメリット・デメリットがあるため、自院にとってどちらが最適かを見極めて判断しましょう。
病院でスムーズな来院を促すなら順番待ちシステムがおすすめ
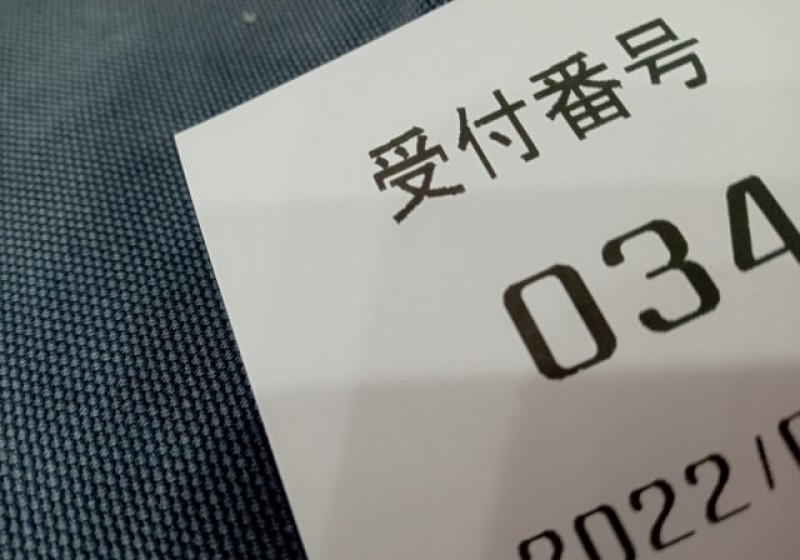
病院でスムーズな来院を促すなら、順番待ちシステムを導入するのがおすすめです。
順番待ちシステムを導入することで、以下のメリットが得られます。
- 受付業務を効率化できる
- 待合スペースの混雑を回避できる
- 顧客データを蓄積できる
- 再来院を促せる
受付業務を効率化できる
順番待ちシステムを導入することで、受付業務を効率化できます。
受付業務では、患者が来院したら診察券と保険証を受け取り、確認を行います。
順番が来たら呼び出しをして診察室へ案内しますが、順番待ちの管理をシステムで行えば受付から診察案内までがとてもスムーズになります。
受付の順番をシステムですべて管理でき、呼び出しも自動で行うため、受付スタッフは他の業務に費やせる時間が増えます。
手間を減らせるのはもちろん、人為的ミスも減少するため、病院と患者間の信頼も損なわれにくくなるでしょう。
業務効率化ができれば、スタッフの業務や心にも余裕が生まれます。患者とのコミュニケーションも取りやすくなり、質の高いサービスを提供できるでしょう。
待合スペースの混雑を回避できる
順番待ちシステムを導入すれば、待合スペースの混雑回避にもつながります。
自分の順番と、現在どこまで順番が進んでいるかがWeb上で把握できれば、患者は来院時間をコントロールできます。
順番が近くなったら来るということができるため、待合スペースが混雑しにくくなります。さらに、患者は長い待ち時間を院内で過ごすという無駄な時間の浪費をせずに済みます。
顧客データを蓄積できる
順番待ちシステムの中には、顧客データや受付データを集計する機能が搭載されたものもあります。
顧客データが蓄積できれば、混雑しやすい時間帯や曜日などが把握しやすくなります。
データを有効活用して混雑具合によってシフトを調整できれば、人件費の削減にもつなげられるでしょう。
再来院を促せる
順番待ちシステムには、登録者向けに情報発信を行える機能が備わったシステムもあります。
予約サイトで都度クリニックからのお知らせを掲載して、親切な設計を心掛ければ再来院につなげられるでしょう。
順番待ちシステムがあることで、「スムーズに予約ができた」「スムーズに受付から診察まで進んだ」と感じてもらいやすいのもメリットで、好印象を持たれやすくなります。
病院の順番待ちシステムおすすめ6選
ここからは、病院の順番待ちシステムのおすすめ6選をご紹介します。
- Uttaro
- Airウェイト
- メディカル革命byGMO
- ドクターキューブ
- EPARK
- i-CALL
なお、以下に記載の導入実績の件数に関しては、2024年3月時点でホームページに記載の情報を参考に掲載しています。
| システム名 | 主な機能(一部抜粋) | 料金 |
|---|---|---|
| EPARK | レセコン・電子カルテ連携 スマホ通知(順番が近づいた際) |
初期費用:150,000円 月額料金:15,000円~ |
| Airウェイト | オンライン順番受付 番号券の発券 |
ベーシック:11,000円 スタンダード:22,000円 |
| メディカル革命byGMO | ダッシュボード機能(予約数・運営状況の確認) WEB問診(オプション機能) |
要問い合わせ(個別見積もり) |
| ドクターキューブ | 院内ディスプレイカスタマイズ機能 電子カルテ・レセコンなどデータ共有可能 |
要問い合わせ(個別見積もり) |
| i-CALL | 院内タッチパネル予約受付 電子カルテ・レセコンとの連携機能 |
要問い合わせ(個別見積もり) |
Uttaro

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 初期費用 | 100,000円 |
| 月額費用 | 20,000円~ |
| 主な機能 | ワクチン設定 予約管理・患者管理 母子手帳写真から接種履歴データ化 ワクチン在庫管理 健診、診療など時間帯予約機能 |
| 運営会社 | ビープラスシステムズ株式会社 |
| 公式HP | https://www.uttaro.jp/ |
Uttaroは、予防接種や健診の予約を自動的に管理してくれるシステムで、小児科やファミリークリニックなど予防接種業務に力を入れておられる診療所からの評価が高いです。予約の83%がネット経由になり、スタッフの電話対応の回数が大幅に減少したという声も多く、その結果、受付業務が効率化され、スタッフの負担軽減にも繋がっています。健診予約機能は、乳児健診の予約での利用を前提の機能ですが、お好きな項目を追加して予約に使うことができるので、簡易な時間帯予約でよければ診察予約や発熱外来の事前予約制の診療予約にも活用できます。
複雑なワクチン接種のルールも、年齢や接種の間隔など医療機関それぞれの方針に合わせて細かく設定でき、ルールに合わない予約が入った場合は警告が表示されるため、誤ったタイミングの接種など、ミスを未然に防止してくれます。また、母子手帳や接種証明書の写真をアップロードするだけで過去の接種履歴が自動で整理され、医療機関側の確認作業もスムーズになります。
予約内容は見やすく一覧表示されるため、スタッフが状況を把握しやすいのも魅力です。患者さんにとっても直感的で分かりやすい画面設計が施されており、初めての方でも迷わず予約することができます。操作に困った場合も、Uttaroのヘルプセンターが受け付けます。患者向けコールセンターはAIと人間による連携対応で効率的にサポートしてくれるので安心です。Uttaroは、受付業務を効率化し、自動的に予約ミスを防ぐことができる、医療機関と患者さん双方にとって快適で安心なシステムと言えるでしょう。
Airウェイト

| 料金 | ベーシック:11,000円 スタンダード:22,000円 |
|---|---|
| 主な機能 | オンライン順番受付 番号券の発券 受付管理 電話での呼び出し(自動音声) など |
| 導入実績 | 医療施設の導入事例多数あり |
Airウェイトは、自院の課題に合わせてカスタマイズして、課題を解消できる順番待ちシステムです。
呼出番号ディスプレイで表示できるため、患者は「自分の順番まであとどれくらいか」を把握でき、呼び出しも自動で行い業務負担が軽減され、双方にメリットがあります。
オンライン順番受付機能を活用すれば、Web上で簡単に順番受付ができます。
受付・発券機能、メール呼び出し機能が体験できる0円プランもありますので、一度使って試してみたいという場合にもおすすめです。
メディカル革命byGMO

| 料金 | 要問い合わせ(個別見積もり) |
|---|---|
| 主な機能 | WEB予約機能 患者管理機能 ダッシュボード機能(予約数・運営状況の確認) WEB問診(オプション機能) など |
| 導入実績 | 1,000件以上 |
メディカル革命byGMOは、診療科目ごとに運用方法を提案してくれるシステムです。
例えば、整形外科クリニックなら、理学療法士の稼働率分析ができてクリニック運営改善に役立てられます。
医療機関のお困りごとを解決するべく。収益率を考慮した予約設定を行い、収益向上や業務改善・効率化を目指します。
WEB、電話だけでなく、LINEと連携してLINEからの予約も受付られるため、患者さんにとっても使用しやすいシステムといえるでしょう。
ドクターキューブ

| 料金 | 要問い合わせ(個別見積もり) |
|---|---|
| 主な機能 | 順番予約・時間予約・時間枠予約 自動音声予約 院内ディスプレイカスタマイズ機能 電子カルテ・レセコンなどデータ共有可能 など |
| 導入実績 | 4,000件以上(2021年10月時点) |
ドクターキューブは医療機関のための予約システムで、あらゆる診療科目に対応し、これまでに4000件以上の導入実績を持ちます。
順番予約・時間予約・時間枠予約に対応しており、状況やニーズに合わせて途中で変更することが可能です。
院内ディスプレイはデザインや画面構成の変更が可能で、待ち人数・待ち時間以外など、様々な組み合わせができます。
自動音声予約にも対応しておりますので、ご高齢の患者さんが多いクリニックに最適です。
EPARK

| 料金 | ベースプランの場合 初期費用:150,000円 月額料金:15,000円~ |
|---|---|
| 主な機能 | 受付予約システム 順番待ちシステム レセコン・電子カルテ連携 スマホ通知(順番が近づいた際) など |
| 導入実績 | 約38,000件(2021年10月現在) |
EPARKの「EPARKクリニック・病院コネクト」は、医療機関向けのネット受付予約・順番待ちシステムです。
約38,000件の導入実績を持ち、集患にも強いのが特徴です。
複数のメディアに医院情報が掲載され、病院を探している段階のユーザーにアピールできるメリットがあります。
日本最大級の病院検索サイト「EPARKクリニック・病院」に掲載でき、その他外部の連携メディアにも掲載されるため、多くの人の目にとまるようになるでしょう。
i-CALL

| 料金 | 要問い合わせ(個別見積もり) |
|---|---|
| 主な機能 | インターネット予約受付 電話音声自動予約受付 院内タッチパネル予約受付 電子カルテ・レセコンとの連携機能 など |
| 導入実績 | 1,206件 |
i-CALLは、全世代が予約しやすい方法を取り入れた医療機関向け診療予約システムです。
予約方法は、インターネットからの受付、電話での音声自動受付、院内タッチパネル受付の3通りが選べ、個々の患者さんそれぞれが操作しやすい方法で予約できます。
電子カルテ・レセコンとの連携機能も備わっており、カルテ操作の手間が軽減されます。
初期導入時・導入後の費用負担も最小限に抑える取り組みが行われておりますので、気になる方はぜひ一度お見積りを相談してみるといいでしょう。
まとめ:病院の順番待ち時間を短縮して業務効率化と患者の利便性向上を図ろう
病院を経営するうえで、順番待ち時間に関する問題は避けて通れません。病院の順番待ち時間を短縮すれば、業務効率化と患者の利便性向上につなげられます。
順番待ち時間を短縮するためには、順番待ちシステムを導入するのがおすすめです。
自院の診療科目やどういった年齢層の患者が多いかなど、総合的に検討して判断してください。


