災害や緊急事態に迅速かつ効果的に対応するため、医療機関には事前の準備が欠かせません。特にBCP(事業継続計画)を策定することは、患者からの信頼性を保つだけでなく、災害時に医療サービスを継続するために必要なステップです。
本記事では、医療機関におけるBCP策定の概要から、実際に策定する際の手順、ひな型の参考サイトまでを詳しく解説します。
この記事の内容
医療機関のBCPとは一体何?事業継続計画について解説

医療機関の「BCP」「事業継続計画」と聞いても、概要などを詳しく説明できる人はそう多くはないでしょう。
ここではBCPの基礎的な知識と医療機関における重要性、策定時の注意点を紹介します。
BCPの基礎知識
BCP(事業継続計画)は、災害や緊急事態が発生した際に、企業や病院などの組織が迅速かつ効率的に対応するために策定される計画です。
医療機関では、BCPは災害時や感染症流行時などの医療サービスの継続を考えるために策定されます。災害時に必要な資金、人力、医療材料などの確保、非常時の医療サービスの提供方法などを明確にした計画です。
医療機関でのBCPの重要性
医療機関でBCPを予め策定しておくことは、災害発生時など緊急事態において、医療サービスを継続するかどうか見極めるために重要となります。
緊急時にいかにして行動を起こすのかというのは、医療機関の規模を問わず、患者への信頼性を保つために避けては通れない課題です。
BCP策定の注意点とは?
BCP策定には、注意点が多くあります。
BCPで策定される項目には、必要な資金や人力の確保、災害時の医療サービスの提供方法の確立、災害時の医療サービスの提供の確認・継続のために必要な計画の作成などがあります。
その時、机上の空論ではなく、危機に直面した時に充分遂行可能な内容になっているのかや、策定した内容をスタッフ全員がしっかりと把握できるかなどに注意して決めていくことが大切です。
【医療機関向け】BCP策定のための手順
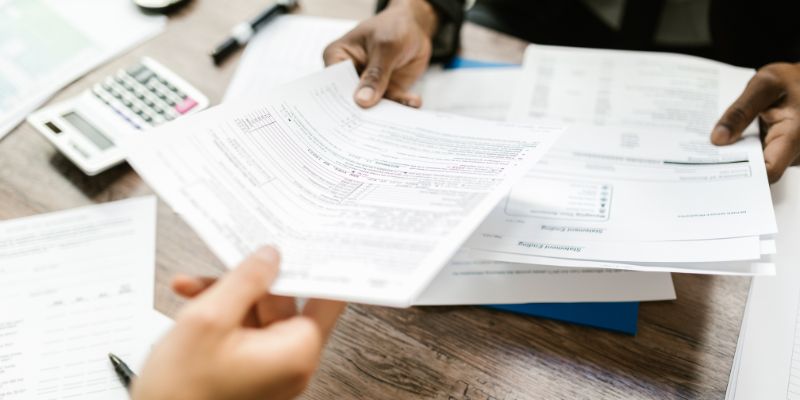
BCP策定には様々な注意点に気をつけながら、より具体的かつ実現可能な対応方法を準備することが大切です。そのためには、どのような手順で策定を行えばいいのでしょうか。
ここでは、BCP策定の手順を3つのステップに分けて解説します。
手順1:リスク評価の実施
BCPを策定するには、まずリスク評価を行うことが重要です。医療機関では、災害や緊急事態が発生する可能性を評価し、その影響を予測します。この評価結果は、後のBCP策定に大きく影響を与えるため、災害時なら「地震」「水害」「火災」など、それぞれの内容に合わせたリスク評価を行いましょう。
手順2:事業影響分析(BIA)の実施
BIAは、災害や緊急事態が発生した際に、医療機関の事業がどのように影響を受けるかを分析します。より具体的に分析することが大切になってくるため、さまざまな部門から意見を集めることがおすすめです。
この分析結果によって、BCP策定の際の対応方法が変わってくるので、とても重要な情報となります。
手順3:復旧戦略の策定
復旧戦略の策定は、災害や緊急事態が発生した際に、医療機関がどのように復旧するかを明確にします。
最初に復旧させるべきなのはどこなのか、復旧のためにはどのくらいの人員が必要なのかなど、部門ごとに意見をまとめます。その後、全体での会議などを通して復旧戦略を策定していきましょう。
医療機関がBCPを策定した後の周知方法

医療機関がBCPを策定した後は、その内容を周知することが重要です。医療機関のスタッフだけでなく、患者や医療機関以外の関係者にもBCPの内容を広く周知しましょう。
全員が内容を把握している状態なら、災害や緊急事態が発生した際にも医療サービスを継続するために速やかに行動できます。
院内での周知方法
医療機関内でのBCPの周知方法には、スタッフ間での訓練や書面を使った患者への情報提供などが挙げられます。中でもスタッフ間での訓練は、BCPの内容をしっかりと理解するために重要です。
訓練を通して出た問題点を解決していくことで、より現場に合った内容にアップデートできます。
院外への周知方法
院外への周知方法には、医療機関のWebサイトや会報誌への掲載などがあります。ウェブサイトなどで公開することにより、医療機関を滅多に受診しない患者でも情報を入手できます。
情報を広く公開することは、患者側が医療機関を選ぶときの参考になるだけでなく、緊急時における近隣の医療機関同士でのスムーズな協力体制の構築に役立ちます。
BCP策定にはテンプレート(雛形)の活用がおすすめ
の活用がおすすめ.jpg)
BCP策定には、テンプレート(雛形)の活用がおすすめです。ここでは、BCP策定に使用できるテンプレートを公開しているサイトを詳しく紹介します。
テンプレート①中小企業庁
中小企業庁は、「入門」〜「上級」まで4つのコースに分かれたテンプレートを掲載しています。それぞれの段階に合わせてステップアップできるように設計されているので、初めてBCPを策定する場合におすすめです。
また、用語解説やセルフチェック表など、テンプレート以外の部分でも参考になる資料を多数掲載しています。
テンプレート②事業継続推進機構
事業継続推進機構は、防災に特化したテンプレートとなっています。初めてBCPを作成する場合、まずは災害に関するBCPをしっかり作り込むことで、感染症などの他のBCP策定にも活かせます。
テンプレート③東京商工会議所
東京商工会議所は、カラーの図やフローチャートを豊富に使用したテンプレートを公開しています。また、東京都の非常災害時に起こり得る被害想定情報を掲載しているので、リスク評価を行う際の参考になるでしょう。
また、策定のガイドには事前チェックシートが掲載されているので、BCP策定前に概要などを再確認できるのも嬉しいポイントです。
BCPは医療支援システムと連携できる?

策定したBCPを電子カルテ等と連携できるかどうかは、採用している医療支援システムにより異なります。そのため、システムを導入する前に、BCPとの連携が可能かどうか確認することが大切です。
電子カルテなどの医療支援システムとBCPを連携させることで、非常時でも即座に患者情報を紹介できたり、避難順を把握できたりと、さまざまなメリットがあります。
医療機関のBCPに関するよくある質問

BCP策定において、よくある質問をまとめました。どれも策定に大きな影響を与える可能性があるため、策定に取り掛かる前に把握しておくと安心です。
BCPの策定は義務?作成しないとどうなるの?
災害拠点病院に指定されている医療機関は、2017年にBCPの策定が義務化されています。
災害拠点病院に指定されていない医療機関も、今後義務化される可能性は十分にあるため、いつからでも対応できるように事前準備をしておきましょう。
また、介護施設に関しては2024年4月からBCPを策定することが義務化されました。介護施設を併設している病院なども義務化される可能性があるので、注意が必要です。
自然災害BCPと感染症BCPは同じものを使用してもいいの?
自然災害BCPと感染症BCPでは、対応すべき課題が異なるため、別々のBCPを策定することが望ましいです。
| 自然災害BCP | 感染症BCP |
|---|---|
| 施設の被害や物資の確保 | 感染予防対策や人員確保 |
自然災害BCPでは、施設の被害や物資の確保などが主な課題となりますが、感染症BCPでは、感染予防対策や人員確保などが重要になります。
それぞれで求められる対応策が異なるため、別々のBCPを策定することをおすすめします。
人員が少ない場合は兼任も可能?
BCPの策定や運用において、医療機関の人員が少ない場合は兼任も可能です。特に非常災害時などは、咄嗟の判断を求められる場面が多くなるため、柔軟な対応が求められます。
ただし、BCPの実効性を確保するためには、人員が少ない場合でも定期的な見直しや訓練を実施する必要があります。スタッフ全員がBCPの重要性を理解し、実現可能な範囲で取り組むことが重要です。
医療機関もBCPを策定して非常時に備えよう

医療機関にとってBCPは、災害や緊急事態が発生した際にも医療サービスを継続させるために必要な要素となります。テンプレートやひな形を活用して、職場環境に合わせたBCP策定を進めていきましょう。
また、BCP策定の手順としてはリスク評価、事業影響分析(BIA)、復旧戦略の策定が挙げられます。適切に策定を進め、非常時にしっかりと備えていきましょう。


