「在宅医療が気になっているけど、メリットとデメリットが知りたい……」
「在宅医療を考えているけど、どのような点に注意したら良いのかな……」
このような疑問を抱いていませんか?
在宅医療は、患者が自宅で安心して生活できるように、医師や看護師、薬剤師などの医療・介護チームが自宅に訪問して医療を行うことを指します。在宅医療にはメリットがある一方で、デメリットもあります。
そこで本記事では、在宅医療のメリットやデメリットについて解説します。医療機関側と患者側のメリット・デメリットをそれぞれ紹介しているので、参考にしてみてください。
この記事の内容
【医療機関側】在宅医療のメリット
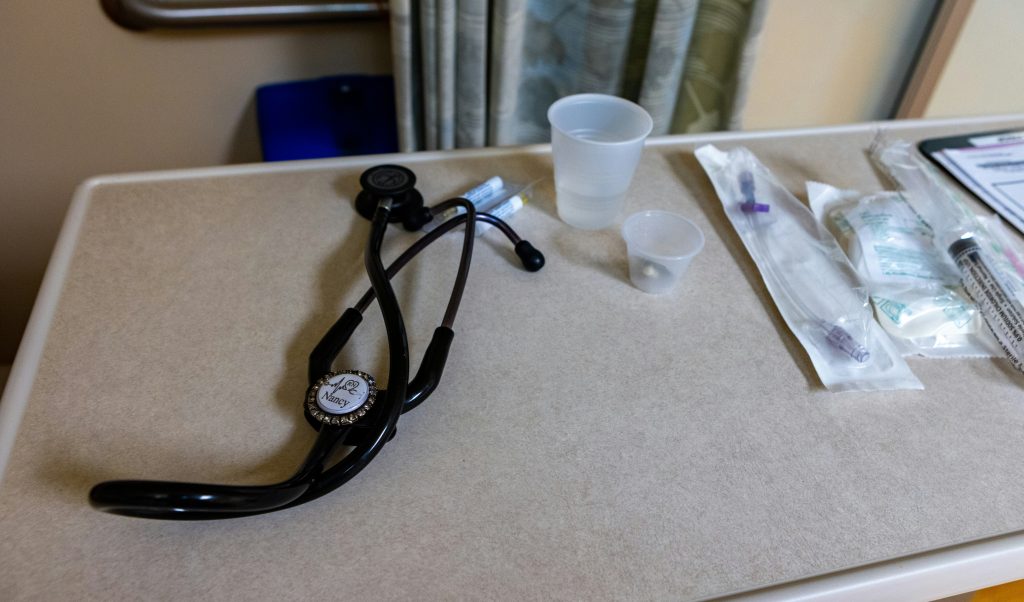
医療機関側の在宅医療のメリットは、主に4つあります。
- 新たな患者層の獲得を行える
- 地域医療への貢献・ブランド力の向上を図れる
- 患者との信頼関係を構築しやすい
- 情報共有や連絡を効率化できる
それぞれのメリットを解説します。
新たな患者層の獲得を行える
在宅医療を始めると、新たな患者層を獲得できる点がメリットとして挙げられます。地方に住んでいる高齢者や慢性疾患を持つ患者は、通院が困難に感じている方も多いです。
そこで、在宅医療を提供することで、通院が難しい患者やその家族に、自院の医療を届けられます。
なかなか通院できずに困っている新しい患者層を獲得できるため、経営の安定化も図りやすいでしょう。
地域医療への貢献・ブランド力の向上を図れる
地域医療への貢献やブランド力の向上を図れる点は、在宅医療のメリットです。自宅で医療支援を行うことで、地域の医療機関としての社会貢献度が高まります。
また、自宅でも安心して診てもらえるという点から、地域住民からの信頼や評判が向上しやすいでしょう。
たとえば、自治体の高齢者向け在宅医療イベントを開催し、健康相談や予防指導を行うことで、地域内での認知度と信頼性が上がります。
患者との信頼関係を構築しやすい
医療機関が在宅医療を提供すると、患者との信頼関係を構築しやすいです。
定期的に自宅に訪問することで、患者や家族とじっくりとコミュニケーションを取れます。
また、患者は自宅で医師や看護師と話すため、病院にいるときと比べて精神的にも負担が少なく、関係を築きやすいでしょう。
さらに、病院とは異なり生活環境を把握できるので、より個別に合わせた医療を提供できるようになります。
情報共有や連絡を効率化できる
在宅医療は、情報共有や連絡を効率化できる点がメリットです。在宅医療では、電子カルテや訪問スケジュールシステムを活用することで、通院時の情報共有や連絡を効率化できます。
また、医師・看護師・リハビリなどの複数のスタッフで情報を共有できるため、重複診療や抜け漏れを防止できます。
たとえば、訪問前に電子カルテで最新の検査結果や処方内容を確認し、訪問時にすぐ対応することが可能です。
患者管理の手間を減らせるだけでなく、情報共有や連絡を効率化できるためおすすめです。
【患者側】在宅医療のメリット

患者側が在宅医療を受けるメリットは、主に4つあります。
- 通院負担の軽減が図れる
- 生活環境に即した診療を受けられる
- 定期的な健康管理・チェックを受けることが可能
- 家族の負担が軽減できる
それぞれのメリットについて解説します。
通院負担の軽減が図れる
在宅医療を受けると、通院の負担が軽減される点がメリットです。
高齢者や体の不自由な方、慢性疾患の患者は、病院までの移動が負担になりやすいです。
一方で、在宅医療では、医師や看護師が自宅まで来て診療してくれるため、通院にかかる時間や体力・費用を削減できます。
たとえば、歩行が困難な糖尿病患者が、自宅で血糖値管理や診察を受けられるので、タクシーなどで病院に通う必要がなくなります。
生活環境に即した診療を受けられる
在宅医療は、生活環境に即した診療を受けられる点もメリットとして挙げられます。
医療従事者が、自宅での生活状況や環境を直接確認できるので、より現実的で安全な治療や生活指導を受けることが可能です。
たとえば、足の調子が悪い患者に対して、家庭での転倒リスクを確認し、手すりの設置など必要に応じて環境改善を提案してもらえます。
定期的な健康管理・チェックを受けることが可能
定期的な健康管理・チェックを受けられる点は、在宅医療のメリットです。
在宅医療で医師や看護師が自宅に訪れた際に、症状やバイタルサインを定期的に確認してもらえます。
また、症状の悪化を早期に察知できるため、緊急入院や重症化のリスクを減らせます。最悪の状態を予防しやすいので、大きなメリットがあるといえるでしょう。
家族の負担が軽減できる
患者が在宅医療を受けるメリットとして、家族の負担が軽減します。在宅医療を受けることで、通院のための付き添いや、病院への送迎などがなくなるため、家族の介護負担が軽減されます。
また在宅医療では、医療スタッフが自宅で診療やケアをしてくれるので、健康管理などの負担も軽減されるでしょう。
たとえば、認知症の高齢者の家族は、通院のための付き添いや薬の管理の心配が少なくなるため、仕事や日常生活との両立が図りやすくなります。
【医療機関側】在宅医療のデメリット・注意点

医療機関が在宅医療を行うときのデメリット・注意点は、主に3つあります。
- 準備や運営負担が増加する
- 急変時対応への負担がある
- 事務や請求業務が複雑化する
それぞれのデメリット・注意点について解説します。
準備や運営負担が増加する
在宅医療を提供するデメリットは、準備や運営負担が増加する点が挙げられます。
在宅医療を始めるには、スタッフの体制の確保や、訪問用の車両・医療機器の準備などが必要です。
また、通常の外来診療とは異なり、移動時間や訪問スケジュール管理などの業務も追加されます。
そのため、訪問スケジュール管理システムや電子カルテ、チャットツールなどを導入して効率化を行うのがおすすめです。
急変時対応への負担がある
急変時対応への負担がある点は、在宅医療を提供するデメリットです。在宅医療は、24時間対応が基本とされるため、夜間や休日に患者が急変した場合でも対応が必要です。
医師の負担増に繋がるだけでなく、体制が整っていない場合は、患者と家族の安心感を損なうリスクがあります。
たとえば、夜中に在宅患者が呼吸困難を訴えたときは、往診対応や緊急搬送の手配をしなければなりません。
夜間や休日のオンコール対応で医師の負担を少なくするために、複数の医師でシフトを組み、負担が1人に集中しないようにするのがおすすめです。また、救急病院や訪問看護ステーションと連携し、夜間や休日の対応を分担するという対策も挙げられます。
事務や請求業務が複雑化する
在宅医療を提供するときは、事務や請求業務が複雑化する点も考慮しておきましょう。在宅医療は外来診療と比べ、算定できる診療報酬項目が多く、条件や要件も複雑です。
また、患者ごとの訪問回数や疾患、緊急往診の有無などにより請求内容が変わるので、事務担当者の知識と労力が欠かせません。
事務や請求業務の複雑化に対応するために、レセプト請求に詳しい事務員を育成したり、在宅医療請求に強い事務代行サービスを利用したりするのも一つの手段です。
ほかにも、院内ルールをマニュアル化しておくと、スタッフ間でも共有して全員が知識を深めやすいです。
【患者側】在宅医療のデメリット・注意点

在宅医療を受けるデメリット・注意点は、主に3つあります。
- 診療内容や検査の制限がある
- 自己負担額がやや高くなる場合がある
- 緊急対応や設備制約がある
それぞれのデメリット・注意点について解説します。
診療内容や検査の制限がある
在宅医療を受けるデメリットとして、診療内容や検査の制限がある点が挙げられます。在宅医療は、CTIやMRI・内視鏡などの大がかりな検査や高度な処理は行えません。
また、治療選択肢が、病院外来と比べて制限されることがあります。
具体例をあげると、自宅で血液検査や簡易心電図は可能ですが、CTでのがん検査や緊急手術はできません。
基本は在宅医療を受けつつ、定期的に病院で精密検査を受けられるようにする必要もあります。
自己負担額がやや高くなる場合がある
自己負担額がやや高くなる場合がある点は、在宅医療を受けるデメリットとして挙げられます。
在宅医療は、訪問料や交通費相当の費用が加わるため、外来通院よりも自己負担が増える場合があります。
また、公的医療保険でカバーされるものの、訪問の頻度によって月額負担が増えるケースも多いです。
対処法として、訪問回数や負担額の目安を、医療機関に確認してから利用を開始すると良いでしょう。ほかにも、高額療養費制度や、公費医療、介護保険サービスを組み合わせるのがおすすめです。
緊急対応や設備制約がある
在宅医療は、緊急対応や設備制約がある点に気をつけましょう。病状が急に悪化した場合、病院のようにすぐに高度な医療が受けられません。
また、自宅では医療機器や人員が限られるため、対応に時間がかかってしまう場合があります。
たとえば、夜間に呼吸困難が出た場合、医師が駆けつけるまでに時間がかかり、その間は家族が対応しなければなりません。
ほかにも、在宅酸素療法や点滴はできるものの、人工呼吸器や輸血などは病院搬送が必要です。
まとめ:在宅医療はメリットやデメリットを把握して選択しよう!

在宅医療は、医療機関側も患者側もさまざまなメリット・デメリットがあります。それぞれのメリット・デメリットを把握していると、在宅医療が合っているか判断しやすいでしょう。
在宅医療を検討している方は、本記事でご紹介したメリットやデメリットを考慮したうえで判断してみてください。



