開業医に限らず、一定の収入を得ている人は確定申告はしなければなりません。勤務医の場合は、雇用主が手続きをしてくれるため、自身で行うことはないです。
しかし、開業医となれば事業所得となるため、自ら確定申告をしなければなりません。
確定申告とは、1月1日〜12月31日までの1年間の所得と、その金額に対する所得税を計算して、税金の過不足を精算する手続きのことで、手続きの方法が複雑でわからないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、開業医向けの確定申告の流れや確定申告の注意点、勤務医との違いについて詳しくご紹介します。
この記事の内容
勤務医と開業医における確定申告の違い
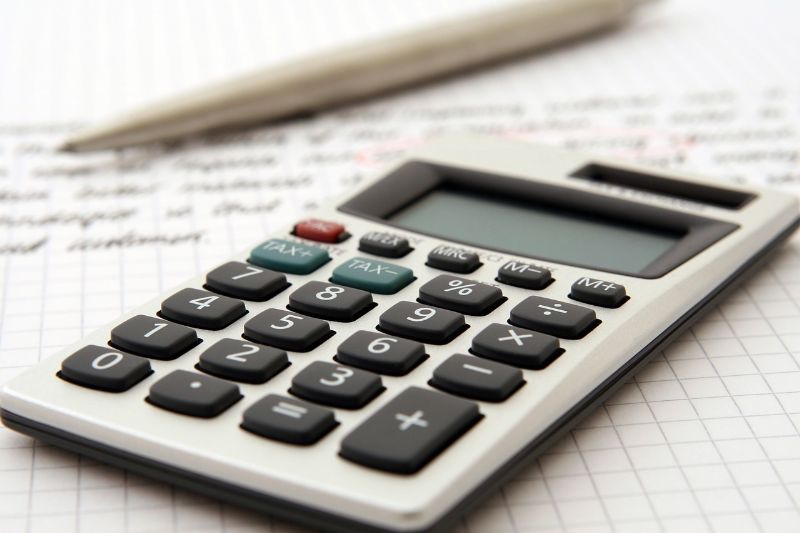
まずは、勤務医と開業医における確定申告の違いについて解説します。
具体的には、以下の2つが挙げられます。
- 勤務医は給与所得で開業医は事業所得になる
- 開業医は確定申告が必須になる
勤務医は給与所得で開業医は事業所得になる
大前提として、勤務医の給料は「給与所得」となり、開業医の給料は「事業所得」となります。
勤務医は病院やクリニックなどで雇用された医師であり、雇用主から給与所得として給料が支払われるため基本的には確定申告を行う必要はありません。
給与所得者は、基本的に勤務先が「源泉徴収」や「特別徴収」を行うため、所得税や住民税の納税も勤務先によって行われます。
納税額に過不足があった場合は、毎年12月に行われる年末調整によって差額を還付または徴収するため、勤務医は基本的に確定申告は不要です。
しかし、以下に当てはまる場合は勤務医でも確定申告を行う必要があります。
- 給与の収入金額が2,000万円以上の場合
- 副業などで給与所得以外の収入が20万円以上ある場合
- 複数の病院に勤務している場合
医師の場合は、上記のいずれかに当てはまる可能性が比較的ありますので、確認しておきましょう。
開業医は確定申告が必須になる
開業医は「源泉徴収」や「特別徴収」といった納税代行はないため、自身で確定申告を行い、納税しなければなりません。
確定申告の際は「白色申告」「青色申告」が選べますが、「青色申告」の場合は最大65万円の特別控除が受けられるため大きな節税対策になります。
家賃や光熱費、消耗品費などを経費計上でき、その控除額が大きく引き上げられる反面、経理の手間が増えたり簿記の知識が必要となるためメリットだけではないことは注意しましょう。
青色申告にする場合は、事前に納税地の税務署に青色申告承認申請書を提出しなければいけませんので、そこも忘れずに対応しましょう。
白色申告の場合は、特に事前の届け出等は必要なく、簡単な取引記録と必要書類を提出するだけで済みます。
手間が少ない分、優遇措置を受けられないデメリットもあるため、よりしっかりと節税対策を行いたいなら青色申告を選択しましょう。
開業医の主な事業収入
開業医の収入は、事業収入にあたると紹介しましたが、消費税計算等に関わるため、収入区分を正しく処理しておきましょう。
開業医の主な事業収入は、以下の3つです。
- 保険診療収入
- 自由診療収入
- 雑収入
保険診療収入
保険診療収入は、「社会保険診療報酬」「国民健康保険診療報酬」による収入のことを指します。
基本診療料や特掲診療料などの外来・入院に関するものが該当します。
基本的に会計処理としては、レセプト(診療報酬明細書)を計算して、支払機関に請求した時点で、請求額を前月の診療収益として計上する方法がとられます。
自由診療収入
自由診療収入は、保険適用外の診療の収入です。
自費診療とも言われる診療を指します。
医療行為におけるすべての収入金額から、社会保険診療収入を引いた金額が該当します。
健康診断や予防接種、その他一部の治療においては自由診療になりますが、診療内容によってはほとんど自由診療収入がないこともあります。
自由診療収入の例
- 自費診療
- 予防接種
- 人間ドック
- 労災、交通事故、公害医療
- 保険証を持参しない場合の診療
- 人工妊娠中絶
雑収入
雑収入は、医療行為以外の医療収入に付随して得た収入です。
保険診療収入・自由診療収入以外の事業収入が雑収入に分類されます。
雑収入の例
- 診断書の作成
- 治療器具や材料など、医療関連商品の販売などで得た収入
- 患者紹介料
- 従業員の食事代
- 医薬品の仕入リベート
- 地方自治体から支給される休日診療手当
- 電話、自動販売機等の手数料
- 緊急医療機関謝礼金
雑収入の計上漏れはよくあるミスなので、注意してください。
開業医の確定申告(所得税計算)の流れ

ここからは、開業医の確定申告(所得税計算)の流れをご紹介します。
1.事業の総収入を算出する
まず、事業の総収入を算出します。
事業の総収入は、先ほど解説した「保険診療収入」「自由診療収入」「雑収入」の合計です。
2.必要経費を算出する
次に、必要経費を算出します。
医院・クリニックの必要経費は、以下2つの方法で計算できます。
- 「社会保険診療報酬の概算経費の特例」を適用する
- 収支実額計算
社会保険診療報酬の概算経費の特例とは、「社会保険診療報酬が5,000万円以下」「自由診療収入および雑収入の報酬総額が7,000万円以下」の2つの条件を満たした場合に適用される特例です。
この特例を適用するかは毎年自身で選べますが、適用する場合は、家族が一緒に働いている際の特例である「青色事業専従者給与」の適用が出来なくなるため注意が必要です。
社会保険診療報酬の概算経費の特例を適用する場合は、「青色申告決算書付表(医師・歯科医師用)」が必要になります。
青色申告決算書、確定申告書に添付して提出しましょう。
社会保険診療報酬の概算経費は、以下のように計算されます。
| 社会保険診療報酬 | 概算経費計算式 |
|---|---|
| 2,500万円以下 | 診療報酬収入×72%(所得率28%) |
| 2,500万円超~3,000万円 | 診療報酬収入×70%(所得率30%)+控除額50万円 |
| 3,000万円超~4,000万円 | 診療報酬収入×62%(所得率38%)+控除額290万円 |
| 4,000万円超~5,000万円 | 診療報酬収入×57%(所得率43%)+控除額490万円 |
例えば、社会保険診療報酬が3,000万円だった場合、概算経費は2,150万円のため、実額経費がこれよりも少ない場合、差額分を経費で落とせることとなり、課税所得も減って節税につながります。
実額経費は「固有の経費」「共通の経費」に分けて考える必要があります。
自由診療収入から固有経費、按分共通経費、青色申告控除額を差し引いた金額が自由診療収入にかかる所得金額となるため経費の計算は必須ですが、共通経費は按分して計算する必要があります。
按分割合は、以下の計算式で求められます。
自由診療の収入金額÷総収入金額×調整率=自由診療割合
なお、調整率は診療科目により異なり、以下のように定められています。(所得税青色申告決算書(一般用)付表《医師及び歯科医師用》記載要領より)
| 診療科目 | 調整率 |
|---|---|
| 内科、耳鼻咽喉科、皮膚科、呼吸器科など | 85% |
| 眼科、外科、整形外科 | 80% |
| 産婦人科、歯科 | 75% |
例えば、診療科目が整形外科で、自由診療収入が2,000万円、社会保険診療報酬が3,000万円だった場合、自由診療割合は32%です。
32%を経費金額にかけて実額経費を求める形となります。
開業医の必要経費は、具体的には以下が当てはまります。
- 人件費(スタッフへの給与など)
- 青色事業専従者給与(生計を一にする配偶者への賃金など)
- 家賃・設備費(家賃・地代、水道光熱費、医療機器など)
- 旅費交通費(交通費やホテル代)
- 租税公課(固定資産税など)
- 広告宣伝費(看板掲載料など)
- 通信費(電話料金やインターネット)
- 消耗品費(医療器具、文房具など)
これらはあくまで一例なので、必要経費として認められるものとそうでないものを事前に把握しておきましょう。
3.損益通算をする
損益通算とは、事業所得や不動産所得など所得の合計額の中で、黒字と赤字を相殺することです。
不動産所得を得ようとして不動産を購入したけど、思うように入居者が増えず経営が赤字になっている場合などに、所得金額の合計の中から赤字分を控除するという方法になります。
ただし、株や不動産の譲渡による損失は、事業所得からの差し引きができないため注意してください。
4.純損失または雑損失の繰越控除をする
純損失とは、損益通算をしても控除しきれなかった損失のことです。
青色申告者の場合は、翌年以降3年間にわたって繰り越せるため、翌年以降に黒字所得から控除ができます。
雑損失とは、雑損控除を行っても控除しきれなかった金額で、こちらも純損失と同様に翌年以降3年間にわたって繰り越せます。
雑損控除とは、災害や盗難等で生じた損失を所得から控除することです。
雑損失の繰越控除は青色申告者、白色申告者のどちらでも適用されます。
5.青色申告特別控除をする
青色申告特別控除とは、青色申告者が受けられる控除です。
青色申告特別控除が適用されれば、税金がかかる所得を控除分減らせます。
控除額は記帳方法や申告方法により、65万円、55万円、10万円と適用できる金額が異なります。
また、それぞれの金額ごとに控除を受けるための条件が設定されています。
| 65万円控除 | (1)事業所得、不動産所得がある (2)複式簿記で記帳している (3)複式簿記に基づき作成した青色申告決算書を添付して確定申告書をする (4)期限内に確定申告をする (5)現金主義による所得計算の特例を受けていない (6)e-Taxを用いて確定申告をしている、もしくは電子帳簿保存を行う |
|---|---|
| 55万円控除 | 上記(1)~(5)を満たしているが、(6)を満たしていない場合 |
| 10万円控除 | 65万円控除・55万円控除の条件を満たしていない場合 |
6.所得控除をする
所得控除とは、所得金額から一定金額を差し引く制度のことです。
所得控除が適用されれば、所得税や住民税の金額を減らせるため、節税につながります。
所得控除の一覧は、以下の通りです。
| 種類 | 控除の概要・所得税計算での控除額 |
|---|---|
| 基礎控除 | ・2,400万円以下:48万円 ・2,400万円超2,450万円以下:32万円 ・2,450万円超2,500万円以下:16万円 ・2,500万円超:0円 |
| 社会保険料控除 | 健康保険料、国民健康保険料などの支払いがある場合 |
| 医療費控除 | 年間支払った医療費が高額であった場合 |
| 雑損控除 | 災害や盗難などで損害を受けた場合 ・(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10% ・(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円 上記いずれか多いほうの金額 |
| 扶養控除 | 控除対象となる扶養親族がいる場合に、38~58万円の控除が受けられる |
| 配偶者特別控除 | 控除対象の配偶者の給与収入が103万円以上の場合に、1~48万円の控除が受けられる(配偶者控除の適用がない場合) 1,000万円超で適用されない |
| 配偶者控除 | 控除対象の配偶者の給与収入が103万円以下の場合に、13~48万円の控除が受けられる 1,000万円超で適用されない |
| 障害者控除 | 本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合、1人につき27万円 特別障害者は40万円、同居特別障害者は75万円 |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の場合、27万円の控除 |
| 寡婦・寡夫控除 | 寡婦又は寡夫の場合、27万円の控除 |
| 寄附金控除 | 国に対する寄附金やふるさと納税に対し、合計金額から2,000円を引いた金額など |
| 地震保険料控除 | 保険会社に支払った地震保険料がある場合、最高額5万円まで |
| 生命保険料控除 | 保険会社に支払った生命保険料や年金保険料などがある場合、最高額12万円まで |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 共済掛金や個人型年金など、確定拠出年金法に係る掛金の支払いがある場合 |
7.税額を算出する
税額は、「課税所得×税率-控除額」で計算できます。
課税所得は、総収入金額から必要経費、損益通算、純損失または雑損失の繰越控除、青色申告特別控除、所得控除を差し引いた数字です。
以下の表に当てはまる課税金額の計算方法で、1年間の所得税の金額を計算します。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円~1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円~3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円~6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円~8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円~17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円~39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
この所得税と、復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)、10%の住民税をあわせて申告することとなります。
8.税額控除があれば差し引く
最後に、税額控除があれば差し引きます。
税額控除は、所得税額から一定の金額を控除することです。
代表的な税額控除は、配当控除、住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除などがあります。
開業医が確定申告までに行いたい節税対策

ここまで確定申告の流れをご説明しましたが、確定申告までに節税対策を行うことも重要です。
開業医が確定申告までに行いたい節税対策は、以下の4つです。
- 利用可能な所得控除を活用する
- 共済に加入する
- 経費を漏れなく計上する
- ふるさと納税を適用する
利用可能な所得控除を活用する
先にもご説明した所得控除を活用することで、節税対策が可能になります。
配偶者がいる場合は配偶者控除の活用は検討すべきですし、それ以外にも保険料を支払っている場合は地震保険、生命保険などの保険料を控除できます。
共済に加入する
共済への加入も、節税対策として広く知られている方法です。
「小規模企業共済」は業種に関わらず、個人事業主が退職金代わりとして利用しているケースもあります。
また、取引先が倒産した場合に貸付を受けられる「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)」の加入も一つの手段です。
掛金を最大800万円まで積み立てられて、そのすべてを事業の経費として処理できます。
ただし、医療法人化を検討している場合は、共済への加入はできないため注意しましょう。
経費を漏れなく計上する
経費の計上漏れはよくあるミスですので、漏れなく計上することが大切です。
経費計上は、節税において最も基本的な対策なので、定期的に漏れがないかを確認してください。
しかし、経費計上できるからと言って、節税目的のためだけの余分な出費は資金繰りに影響を与える恐れがあるため、無暗に出費を繰り返すのはやめましょう。
ふるさと納税を適用する
ふるさと納税は、寄附金控除として扱われるため、節税対策として有効です。
寄付額のうち、2,000円を超える部分については所得税・個人住民税から控除が受けられます。
ただし、寄付金控除には上限額があり、所得が高いほど上限額も大きくなります。
上限を超えた寄付は節税効果がなく、ただの寄付となるため注意が必要です。
開業医の確定申告における注意点
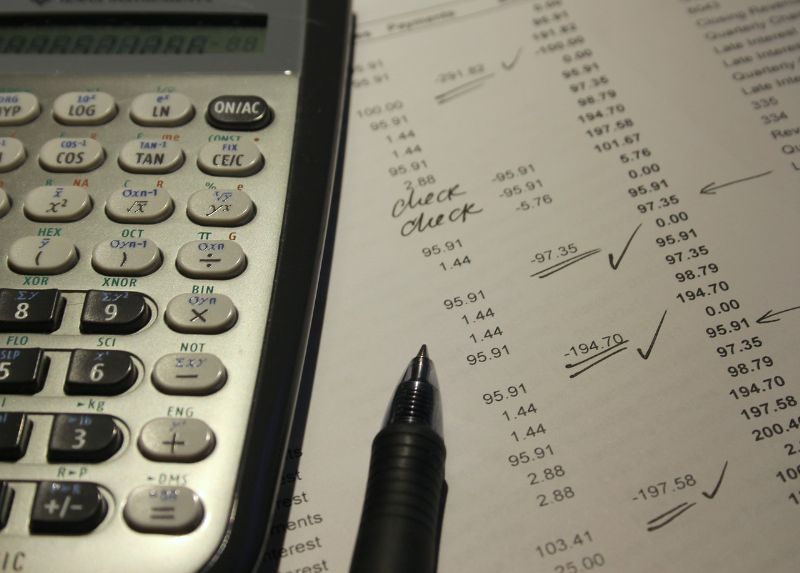
開業医の確定申告において注意すべき点をご紹介します。
給与所得や雑所得の計上漏れがないか確認する
開業医として得た事業所得だけでなく、給与所得や雑所得を得ることもあり、それらの計上漏れがないかを確認しましょう。
「医療関係のメディア監修を雇われてしている」「不動産投資をしている」と言ったように、事業以外の収入は給与所得や雑所得として計上しなければなりません。
配偶者に対して青色事業専従者給与を支払うときは条件を確認する
配偶者に対して青色事業専従者給与を支払うときは、よく条件を確認して間違いのないようにしましょう。
家族に支払う給与賃金は、以下の条件を満たしている場合に、必要経費として認められます。
- 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
- その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
- その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分
- の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
出典:国税庁ホームページ|青色事業専従者給与と事業専従者控除
社会保険診療報酬の概算経費の特例との同時適用はできないため、注意しましょう。
開業医は売上が大きくなったら医療法人化も検討がおすすめ

開業医は、経営が軌道に乗り、売上が大きくなったら医療法人化を検討することもおすすめです。
所得金額が多くなればなるほど、税率が高くなっていくため、医療法人化したほうが節税効果も高くなるケースが多いです。
経費計上や控除を利用するだけでは節税対策としては心もとなく、いずれ大きな課税は避けられなくなってしまいます。
法人化した場合は、基本的に税率は一定で、年800万円までは15%、年800万円超は23.2%となります。
仮に事業所得が800万円だった場合、開業医は23%、医療法人なら15%で64万円も納税額が変わるためこの差はかなり大きいでしょう。
そのほかにも、報酬を給与として受け取ることで大きな節税効果が見込めたり、メリットがいくつか存在するため、売上が大きくなった際は医療法人化を検討しましょう。
まとめ:開業医の確定申告を漏れなく行って安定した経営を目指そう
開業医は勤務医と異なり、確定申告が必須です。
あらかじめ収入の種類などを学んでおき、確定申告を漏れなく行って安定した経営を目指しましょう。
確定申告は毎年3月15日が期限となっていますが、ギリギリに始めると思った以上に捗らず期限に間に合わなくなる恐れもあるため、早めに動き出しましょう。
開業医の確定申告はややこしい部分も多く、大変な作業かとは思いますが、会計ソフトなどを利用すれば手間も大きく削減できるため、この記事を参考に必ず申告してください。


