「医師と患者の関係で大切なことは、具体的にどのようなことだろう……」
このような悩みを抱えていませんか?
医師と患者の関係は重要で、正確な治療に直結します。
たとえば、医師と患者の関係が十分に構築されておらず、コミュニケーションがうまく取れない場合は、本来の症状とは異なる治療を行ってしまう可能性があります。
本記事では、医師と患者の関係で大切なことについて解説します。
信頼できる医師の特徴や信頼される医師になるためのポイントも紹介しているので、参考にしてみてください。
この記事の内容
【医師側】患者との関係で大切なこと4つのこと
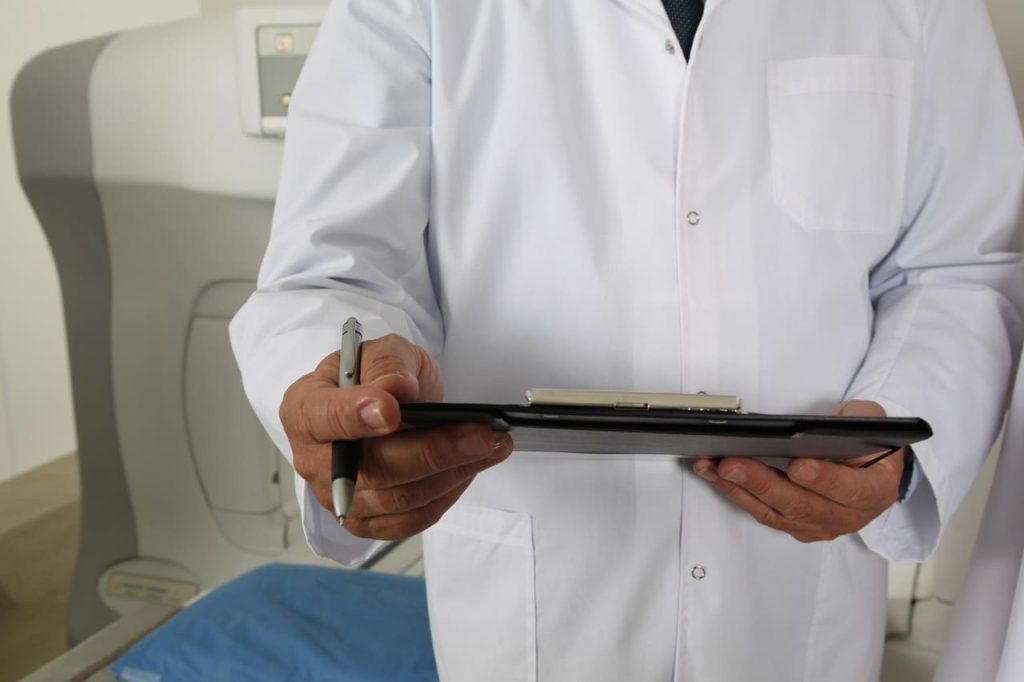
患者との関係で大切なことは、主に4つあります。
- 治療方針の論理的説明で理解・納得を促す
- 治療だけでなく傾聴と共感も重視する
- アラートサインの見極めを慎重に行う
- 治療パートナーとしての配慮を行う
それぞれの内容について解説します。
治療方針の論理的説明で理解・納得を促す
患者との関係で大切なこととして、治療方針の論理的説明で理解・納得を促すことが挙げられます。病気の状態や治療の選択肢を順番に説明するのがおすすめです。
また、治療方針の説明をする際に、治療ごとのメリットとデメリットを丁寧に説明し、患者が自分で納得して選べるような説明を意識しましょう。
「とりあえず病気に有効な薬を出しておきます。毎日飲むようにしてください」という、効果や副作用を説明せず、一方的に押し付ける内容だと患者に不信感を与えてしまいます。
たとえば、高血圧で悩む患者に対して、「この薬を使うことで血圧は下がりやすいですが、めまいの副作用が出ることがあります。薬を使わない場合は、食事と運動だけで調整する方法になります」などと細かく説明しましょう。
患者は自身が納得した治療方針を選択することで、治療への納得感と安心感が高まります。
ただし、治療について説明するときは、専門用語を避け、数値を含めながら丁寧に伝えることを意識してみてください。
治療だけでなく傾聴と共感も重視する
治療だけでなく傾聴と共感を重視することは、患者との関係づくりで大切なことです。
患者の話をしっかりと聞くことで、不安を取り除きながら背景を理解できます。病気や治療の解決だけに急いで、患者の気持ちを無視してしまう状態は避けましょう。
たとえば、患者が「薬を飲んでいるけど、まだ夜眠れない」と相談してくるとき、医師が「そのうち効きますので、飲み続けましょう」と伝える状態では、患者は「聞いてもらえなかった」と感じやすいです。
そのため、「それは辛いですね。眠れないと日中も大変ですね。詳しく状況を教えていただけますか?」というような感情を受け止めたうえで、追加の情報を引き出すのがおすすめです。
共感を持つことで信頼関係を築きやすく、治療継続や満足度を高められます。身体のことだけでなく、精神的な不安や困りごとに対して丁寧に傾聴すると、安心感を与えやすいです。
アラートサインの見極めを慎重に行う
医師と患者の関係づくりで大切なこととして、アラートサインの見極めを慎重に行う点も挙げられます。
体の異変や病気の悪化のサインを早めに見つけることで、病状の悪化や最悪の事態を防ぎやすいです。小さな変化でも「念のため」を大事にし、早めに対応することが重要です。
たとえば、患者が息苦しさと胸が少し痛いという症状で訪れた際に「風邪でしょう。薬を出しておきます。」などのように胸痛を軽視して放置すると、心筋梗塞などの重大な病気を見逃す可能性があります。
「胸痛があるのは心配なので、心電図や血液検査を行いましょう。場合によっては入院が必要です」と伝えることで、患者を安心させながら重大な症状を見逃さず対応できます。
また、アラートサインの見極めとして、患者や家族に、「いつ」「どんな症状があれば連絡・受診すべきなのか」を明確に伝えましょう。
さらに、疑わしいときは入院・専門院の紹介、再診を早めに設定し、記録を具体的に残しておくのがおすすめです。
患者自身が大丈夫と判断しても、病気の前兆が現れている可能性もあるため、家族の方からも話を聞いて判断すると良いでしょう。
治療パートナーとしての配慮を行う
患者との関係で大切なこととして、治療パートナーとしての配慮を行いましょう。
医師と患者や家族が協働して現実的かつ持続可能な治療計画を作り、患者の生活に根ざした医療を実行するのが好ましいです。
悪い例として、服薬を促す際に「この薬が一番効きますので、必ず飲んでください」と患者の生活や希望を無視してしまうと、患者は不安になって服薬を止めてしまう可能性があります。
そのため、患者の生活または仕事を考慮して、一緒に治療方針を決めるのが良いでしょう。
患者を受け身にせず、一緒に治療を考える仲間として関わるのがおすすめです。医師だけの判断ではなく、患者と一緒に取り組む姿勢を意識してみてください。
【患者側】医師との関係で大切なこと4つのこと

患者が医師との関係づくりで大切なことは、主に4つあります。
- 正確に情報を伝える
- 積極的なコミュニケーションを取る
- 診療時間などのマナーを守る
- 医師に対して無理な要望を言わない
それぞれの内容について解説します。
正確に情報を伝える
医師との関係づくりで大切なことは、正確に情報を伝えることです。医師は体の症状や生活習慣などを聞き取りしてくれますが、正確な状態は本人しかわかりません。
あいまいな情報や隠しごとがあると、正しい診断や治療が難しくなります。
たとえば、薬を毎日飲んでいない場合は、ごまかすのではなく「2日に1回のみ忘れることがある」など正確に伝えるのが好ましいです。
また、「胸が痛い」と伝えるのではなく、「階段を上がるときに左胸がズキズキ痛み5分ぐらい続く」というように詳しく伝えることで、正しい状態がわかりやすいです。
そのため、医師に説明を伝える際には、詳細かつ正しい情報を意識しましょう。
積極的なコミュニケーションを取る
積極的なコミュニケーションを取ることは、医師との関係づくりで大切です。わからないことや不安なことを遠慮せずに質問し、治療方針について意見を伝えるようにしましょう。
積極的なコミュニケーションを取ることで、治療方針も柔軟に対応してもらえる可能性があります。
具体例を挙げると、「副作用が心配なので、別の治療法がありますか?」と伝えると、別の方法を提案してもらえる可能性があります。
そのため、わからない点や不安なことがある場合は、積極的なコミュニケーションを取って、納得した状態で治療を受けましょう。
診療時間などのマナーを守る
医師との関係を作るときは、診療時間に遅れないなどのマナーを守りましょう。
たとえば、診療時間を守らないと診療が滞ってしまい、他の患者の診察にも影響する可能性があります。
ほかにも、スマホは待合室でマナーモードにしたり、薬の飲み忘れや中断をしたときは素直に伝えたりするのが好ましいです。
マナーが悪いと医師から悪い印象を抱かれやすく、親身になって対応してもらえない可能性があります。
医師に対して無理な要望を言わない
医師に対して無理な要望を言わない点は、医師との関係を作るときに大切なことの一つです。
具体例を挙げると、医学的に不適切な薬や検査をわがままで求めてしまうと、医師を困らせてしまいます。
医師には安全で適切な医療を提供する責任があり、無理な希望を通すと逆に患者にとって危険になることがあります。
そのため、医師に対して無理な要望は言わないようにしましょう。
信頼できる医師の特徴

信頼できる医師の特徴は、主に5つあります。
- 説明がわかりやすい
- 患者の悩みを真剣に聞いてくれる
- 誠実で素直な対応を取ってくれる
- プロとしての姿勢を見せてくれる
- 顔を見て診察をしてくれる
それぞれの特徴について解説します。
説明がわかりやすい
信頼できる医師の特徴として、説明がわかりやすい点が挙げられます。
医学用語を使いすぎず、患者が理解できる言葉で治療や検査の説明をしてくれる医師は、患者に寄り添った医療サービスを意識しています。
また、図やパンフレットを使いながら具体的に説明してくれると、視覚的にも伝わりやすいです。
信頼できる医師に相談したいときは、説明がわかりやすい医師を見つけましょう。
患者の悩みを真剣に聞いてくれる
患者の悩みを真剣に聞いてくれる医師は、信頼できるといえるでしょう。
たとえば、症状だけでなく、不安や生活上の困りごとに対しても耳を傾けてくれる医師がおすすめです。
また、診察時にパソコンばかり見ず、患者の表情や様子を観察しながらコミュニケーションを取ってくれる医師は信頼できます。
さらに、途中で口を挟まずに最後まで話を聞いてくれると、患者はより希望に寄り添った治療提案を受けやすいです。
誠実で素直な対応を取ってくれる
信頼できる医師の特徴として、誠実で素直な対応を取ってくれる方が挙げられます。治療の副作用や手術のリスクなど、患者にとって不利な情報も隠さずに伝えてくれる医師が信頼できます。
また、できることとできないことを正直に伝えてくれる医師が良いでしょう。
ほかにも、自分の専門外の病気であれば、「専門医を紹介します」と素直に伝えてくれる医師は、安心して任せられるでしょう。
加えて、診療過程での説明不足や小さな判断の誤りがあった場合に、隠すのではなく説明が不十分だったと素直に誤りを認めてくれる医師は信頼できます。
プロとしての姿勢を見せてくれる
プロとしての姿勢を見せてくれる医師は、信頼できるといえるでしょう。
たとえば、新しい治療やガイドラインを常に勉強し、最新情報をもとに説明をしてくれる医師は信頼できます。
ほかにも、検査の案内をするときは、根拠をもとに丁寧に説明してくれる医師は信頼できます。
顔を見て診察をしてくれる
信頼できる医師の特徴として、顔を見て診察をしてくれるという点が挙げられます。
カルテやパソコン画面ばかりで見ず、患者の目を見て対話してくれる方が良いでしょう。
具体例を挙げると、子どもの診察をする際に、子供の目線に合わせてしゃがみながら話してくれる医師がおすすめです。
ほかにも、「不安なことがありませんか?」と表情を診ながら声がけしてくれる方が信頼できる医師として挙げられます。
信頼される医師になるための3つのポイント

信頼される医師になるためのポイントは、主に3つあります。
- 患者の生活習慣や症状の背景にまで目を向ける
- 患者の負担を減らすツールやシステムを導入する
- 医療に関する知識や技術を継続して磨く
それぞれのポイントについて解説します。
患者の生活習慣や症状の背景にまで目を向ける
患者の生活習慣や症状の背景にまで目を向けることは、信頼される患者になるための大切なポイントです。症状だけでなく、その人の生活全体を把握して診療に活かすと良いでしょう。
具体例を挙げると、糖尿病の患者に対して、ただ薬を出すのではなく、普段の食事について聞いたり、仕事の長さなどの生活習慣を確認したりするのがおすすめです。
表面的な治療にとどまらず、根本的な改善策を一緒に考えると、患者から信頼されやすいです。
患者の負担を減らすツールやシステムを導入する
信頼される医師を目指したいときは、患者の負担を減らすツールやシステムを導入しましょう。
たとえば、オンライン診療を導入すると、通院が困難な方や薬だけ受け取りたいという方の負担を減らせます。
ほかにも、オンライン予約システムを導入すると、患者の待ち時間を短縮できます。
患者の満足度を高めるシステム・ツールを導入することで、患者思いの医師というイメージが付きやすいです。
医療に関する知識や技術を継続して磨く
医療に関する知識や技術を継続して磨くと、信頼される医師になりやすいです。
医療は常に進歩しており、最新の知識や技術を学び続けることは重要です。
具体例を挙げると、「最近はこの治療が有効だと報告されています」というように、エビデンスをもとに説明ができるようになると、患者から信頼されやすくなります。
学会や研修会に参加して、新しい治療法や薬について学ぶのはおすすめです。
まとめ:医師と患者の関係で大切なことを把握してお互い納得した関係を構築しよう!

医師と患者の関係で大切なことを把握していると、お互いが納得した関係を構築できます。
とくに、コミュニケーションを大切にすることで、正確な治療を受けやすいです。
医師と患者の関係づくりを大切にしたい方は、本記事で紹介した内容を参考にしてみてください。


