「返戻レセプトが多いけど、原因は何かな……」
「返戻レセプトの再請求の具体的な流れを知りたい……」
このような疑問を抱えていませんか?
レセプトは入力間違いや算定ルールに誤りがあると、提出したレセプトが返戻レセプトとして返ってきます。
返戻レセプトは、支払基金や国保連が審査を通さなかったレセプトになるため、放置していると請求できずに未収になってしまいます。
そこで本記事では、返戻レセプトとはどのようなレセプトか、返戻を受けやすいポイントや再請求の方法について解説します。
返戻レセプトが起きる代表的な原因や理由が気になる方は、参考にしてみてください。
この記事の内容
返戻レセプトとは?
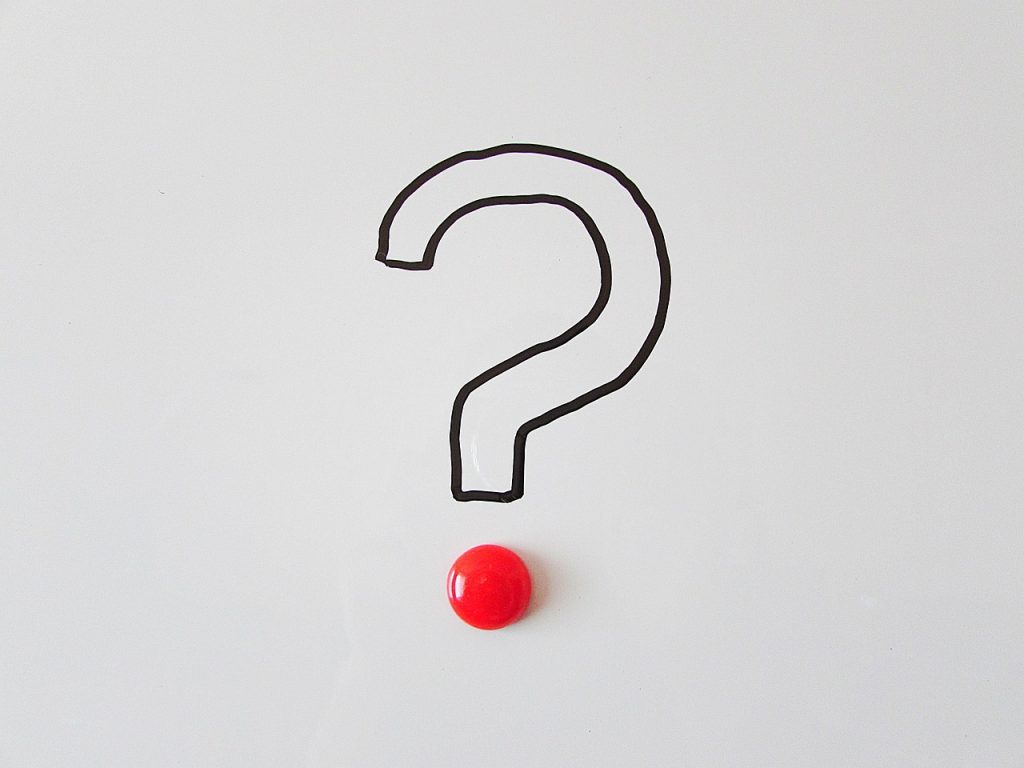
返戻レセプトとは、医療機関や薬局が提出した診療報酬明細書(レセプト)を、支払基金または国保連などの審査支払機関がそのままでは審査できないと差し戻したものです。
不備や記入漏れがあると返戻を受けやすく、一度返戻されたレセプトは修正して再提出しなければ支払いが行われません。
点数算定ルールの誤りや、診療行為・薬剤の記入漏れなどが返戻になる理由としてあげられます。返戻レセプトは放置してしまうと、請求そのものが成立しないため、報酬が入りません。
そのため、早急に修正対応する必要があります。
レセプト査定との違い
提出したレセプトは、返戻される場合もあれば、査定される場合もあります。
レセプト査定とは、医療機関や薬局が提出した請求内容の一部が、診療報酬の算定ルールや診療報酬点数表に照らした際に認められず、請求額の一部が減額され支払われることです。
査定は、主に医学的な妥当性がない場合や点数表のルール違反、診療録との整合性不備が原因としてあげられます。
査定は請求が成立するものの一部が減額されて支払われますが、返戻は請求が成立していないので支払いが行われません。
返戻を受けた場合は修正や再請求しないと入金されないため、返戻レセプトがある場合は速やかに修正して再提出する必要があります。
返戻レセプトが起きる代表的な原因・理由

返戻レセプトが起きる代表的な原因・理由は、主に4つあります。
- 記載漏れ・記載間違い
- 医療行為の不適切・算定ミス
- 書類不備
- 保険資格の問題
それぞれの原因・理由について解説します。
記載漏れ・記載間違い
返戻レセプトの起きる原因・理由でとくに多いのが、記入漏れや記載間違いです。レセプトに必要な情報が抜けていたり、誤っていたりする場合は返戻を受けます。
具体例を挙げると、患者の生年月日が本来であれば1989年であるのにもかかわらず、1998年と記載されている場合は、記載間違いとして返戻を受けます。
ほかにも、投薬の日数や用量の記載漏れ、負担割合の間違いなどが該当するため、注意が必要です。
単純な入力ミスや確認不足によって記載漏れや記載間違いを招きやすいので、ダブルチェックなどの厳重なチェック体制を整えるのが好ましいです。
医療行為の不適切・算定ミス
医療行為の不適切や算定ミスは、返戻レセプトの原因の一つです。同一日に同じ検査を重複して算定していたり、算定できない組み合わせを同時に算定していたりすると、返戻を受けます。
たとえば、初診料と特定の管理料を同時に算定していたり、月1回までの指導料を2回算定していたりすると、算定ミスとして返戻を受けやすいです。
医師のオーダーミスやレセコン設定の誤りが背景にある場合も多いため、一度医師に確認してみると良いでしょう。
書類不備
返戻レセプトを受ける原因・理由として、書類不備も挙げられます。特定の診療行為や、薬剤使用に必要な書類が不足しているケースが返戻を受けます。
具体例を挙げると、特定疾患療養管理料の算定時に、指導計画書や指導記録の添付がないと、書類不備として返戻を受けやすいです。
ほかにも、在宅医療で必要な訪問診療計画書や、同意書が添付されていない場合、公費医療に必要な受給者証の写しが不足している場合などが該当します。
書類管理体制が不十分だと、書類不備による返戻レセプトを受けやすいため、管理体制の見直しを行うようにしましょう。
保険資格の問題
返戻レセプトの原因として、保険資格の問題も挙げられます。患者の保険証や資格情報が正しく反映されていない場合は、返戻を受けます。
たとえば、保険証の更新で、記号番号が変わっているのにもかかわらず、古い情報で請求していると、返戻を受けやすいです。
その他にも、国保から社保に切り替わったのを確認できていなかったり、マイナ保険証の資格情報を更新できていなかったりすると、返戻を受けます。
窓口確認やオンライン資格確認等を活用すると、保険資格の問題による返戻を防止できます。
返戻で送られてくる書類の種類

返戻で送られてくる書類の種類は、主に3種類あります。
- 増減点連絡書
- 返戻内訳書
- 増減点返戻通知書
それぞれの書類について解説します。
増減点連絡書
増減点連絡書は、請求点数の修正や訂正に関する連絡書類です。審査側が「この診療行為の点数が増点されます・減点されます」と伝えるものです。
たとえば、算定条件を満たしていない加算を請求していた場合、点数がマイナスされた状態の通知が届きます。
ほかにも、検査加算がレセプトから漏れていたときは、追加でプラスされた点数が通知されます。
レセプトの差し戻しではなく、支払基金や国保連が訂正して清算してくれる場合に利用されるケースが多いです。
返戻内訳書
返戻内訳書は、返戻されたレセプト内容を整理した書類です。どの患者のどの診療部分が返戻対象となっているかについて、一覧形式で記載されています。
具体例を挙げると、「患者名・診療年月・理由」や「患者名・診療年月・レセプト種別・理由」などが記載されています。
返戻された内容の一覧表をイメージするとわかりやすいでしょう。
返戻内訳書をもとに、どの点が誤っているかを確認し、修正を行ったうえで再提出が必要です。
増減点返戻通知書
増減点返戻通知書は、増減点と返戻が一緒にある場合にまとめて通知される書類です。
増減点の内容や返戻の内容を一体的に記載しており、点数修正と返戻が同時に発生しているときに送られる書類です。
たとえば、「患者名:検査加算不足→+100点」「患者名:保険者番号誤り→レセプト返戻」などのように記載されています。
点数修正と返戻が同時に発生しているので、内容を確認したうえで修正を行い、再提出する必要があります。
返戻レセプトの再請求の具体的な流れ

返戻レセプトの再請求は、主に5つの流れで進めます。
- 返戻通知と指摘の確認
- 訂正や添付資料の準備
- 修正後に再請求
- 再審査
- 診療報酬の支払い
それぞれの流れについて解説します。
STEP.1:返戻通知と指摘の確認
返戻レセプトがある場合は、支払基金や国保連から返戻通知書や返戻内訳書が届きます。
返戻内訳書には、「保険者番号の記載誤り」や「公費負担者番号が未記載」などが記載されています。
返戻内訳書から、どの患者・どの診療分・何が原因で返戻されたのかを把握することが可能です。
STEP.2:訂正や添付資料の準備
返戻通知書や返戻内訳書が届いたあとは、指摘内容に応じてレセプトを訂正する必要があります。
具体例を挙げると、保険者番号が誤っている場合、正しい番号を入力し直す必要があります。
ほかにも添付資料に不備があるときは、必要書類を準備することが必要です。
たとえば、公費の資格証明書のコピーや、診療内容を証明する紹介状・検査結果などを用意しましょう。
書類不備か、算定根拠不足かにより、準備する内容が異なります。
STEP.3:修正後に再請求
レセプトの修正や添付資料の準備が終わったあとは、再請求を行います。
紙レセプトであれば、訂正後に国保連合会(国保中央会)、または健康保険組合・協会けんぽの支払機関に送付しましょう。
返戻通知書や請求書に、再提出先が記載されていることが多いため、確認してみてください。
電子レセプトの場合は、レセコンで修正後、再請求用のデータを作成して送信します。
STEP.4:再審査
電子レセプトや紙レセプトを再請求したあとは、審査支払機関が再度チェックを行います。
不備が直っている場合は、問題なく診療報酬が支払われます。
一方で、再度不備がある場合は、再度返戻される場合もあるため、注意が必要です。
STEP.5:診療報酬の支払い
審査支払機関による審査が通過した分に関しては、支払報酬が支払われます。
たとえば、8月診療分で返戻になったレセプトを修正し、10月請求分に再請求を行った場合は、12月に支払いが確定します。
再請求分は、本来の診療月から遅れて支払われる点を考慮しておきましょう。
返戻レセプトを受けやすい項目のチェックリスト

返戻レセプトを受けやすい項目は、主に5つあります。
- 患者情報
- 診療日・診療内容
- 医療行為・算定
- 書類・添付資料
- その他
それぞれの項目について解説します。
患者情報
返戻レセプトで誤りになりやすいポイントでは、患者情報が挙げられます。患者に関する基本情報の誤りや未記入があると、返戻を受けやすいです。
たとえば、保険者番号が間違っていたり、被保険者証の有効期限が切れていたりすると、返戻の対象になります。
ほかにも、氏名の誤字や漢字間違い、生年月日または性別の記載ミスなどがあると返戻を受けます。
診療日・診療内容
返戻を受けやすい項目では、診療日や診療内容も挙げられます。診療のいつ・何をしたかに関する情報が不足・不備がある場合は、レセプトが返戻されます。
具体例を挙げると、診療日が誤って記載されていたり、同日に複数回算定できない処置を、重複で請求していたりすると、返戻対象になりやすいです。
同日に複数回算定できない処置は、点滴やワクチン接種、心電図・胸部レントゲンなどが該当します。
診療日や内容の不一致は、審査を行う際に引っかかりやすいため、注意が必要です。
医療行為・算定
診療内容や加算の算定に関する不備がある場合は、返戻を受けやすいです。
たとえば、検査加算の算定条件を満たしていない状態で加算を行っていたり、処方箋料の算定が漏れていたりすると、返戻を受けます。
ほかにも、点数表と異なる算定コードを使用していたり、同じ日に同じ処置を二重請求していたりすると、返戻対象になります。
医療行為ごとの算定ルールは複雑なので、確認不足が返戻を招きやすいです。
書類・添付資料
返戻レセプトを受けやすい項目では、書類・添付資料が挙げられます。必要な書類が未添付または不備がある場合は、返戻を受けやすいです。
具体例を挙げると、公費負担者の資格証明書のコピーがなかったり、診療情報提供書や紹介所が未添付だったりする場合は、返戻になります。
また、添付書類を準備できている場合でも、コピーが不鮮明で書類の内容が読めないという場合は、返戻になりやすいです。
書類の添付漏れは返戻の中でもよくあるため、気をつけるようにしてみてください。
その他
返戻レセプトは、他にもさまざまな理由から返戻される場合があります。
たとえば、レセプト提出期限が過ぎていたり、押印忘れなどの書式上の記載ルール違反があったりする場合は、返戻の対象になります。
人為的なミスやルールの見落としによって返戻を受ける場合も多いため、レセプトを提出する際には入念に確認したうえで行いましょう。
返戻レセプトを受けないために意識したい4つのポイント

返戻レセプトを受けないために意識したいポイントは、主に4つあります。
- 診療報酬請求ルールを遵守する
- 書類・添付資料のダブルチェックを行う
- レセプト作成システムや電子請求システムを活用する
- 厚生労働省の通知や審査支払基金からの最新情報を確認する
それぞれのポイントについて解説します。
診療報酬請求ルールを遵守する
返戻を受けないために意識したいポイントでは、診療報酬請求ルールを遵守する点も挙げられます。ルール違反があると、返戻対象になってしまいます。
たとえば、検査加算を算定する場合、診療行為や検査結果などの前提条件が満たされているか確認しましょう。
算定条件や加算のルールを確認し、ルールに沿って請求するようにしてみてください。
書類・添付資料のダブルチェックを行う
書類・添付資料のダブルチェックを行うと、返戻レセプトを受けにくい環境を構築できます。
添付漏れがないか、書類に不備がないかを二重で確認することで、返戻を防止しやすいです。
また、コピーが不鮮明の場合は、書類不備の対象になる場合もあるため、必要書類や添付資料をコピーする際には、読み取りやすさにも気をつけましょう。
レセプト作成システムや電子請求システムを活用する
返戻レセプトを受けないためには、レセプト作成システムや、電子請求システムを活用するのがおすすめです。
レセコンや電子請求システムの自動チェック機能を活用すると、手作業でのミスを減らせるほか、効率的に返戻を防止できます。
たとえば、添付書類の確認漏れをアラートで通知する機能が備わっていると、ミスを予防できます。
厚生労働省の通知や審査支払基金からの最新情報を確認する
厚生労働省の通知や、審査支払基金からの最新情報は、返戻を受けないために確認しましょう。
レセプトは、法改正や診療報酬改定、審査通知に基づき請求ルールを最新化する必要があります。
知らなかったでは済まされないため、情報更新は欠かせません。
審査支払基金からの返戻傾向をチェックしたり、新しい検査・薬剤の算定条件を把握し、最新情報に基づいてレセプトを作成したりするようにしましょう。
まとめ:返戻レセプトを受けないために対策を練ろう!

返戻レセプトを受けた場合は、修正や添付書類の準備を行う必要があります。
レセプトの返戻が多いほど負担がかかってしまい、他の業務に影響が出てしまう可能性があります。
返戻レセプトを予防するためにも、ダブルチェック体制や情報入力の正確性を意識し、最新情報と照らし合わせながらレセプトを作成するようにしましょう。


