「レセプト業務は具体的にどのようなことをするの?」
「レセプト業務を正確かつ効率良く行うコツを知りたい……」
このような疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
レセプト業務は、主に医療機関や介護施設で行われる、診療報酬請求に関する事務作業です。専門的な知識が必要なだけでなく、正確な算定スキルが欠かせません。
本記事では、レセプト業務の具体的な内容や、正確かつ効率良く行うコツを解説します。
レセプト業務のスキルを上げる方法や業務を行う際の注意点を含めて紹介しているので、参考にしてみてください。
この記事の内容
レセプト業務とは?

レセプト業務とは、診療報酬請求に関する事務作業を指し、患者が受けた医療サービスに対して健康保険組合や国民健康保険などの保険者に報酬を請求する手続きです。
医療機関の経営を支える重要な業務の一つで、1点でも間違えると収益に影響が出ます。多くの医療機関では月ごとに診療報酬をまとめて請求するため、月末や翌月初にレセプト作成・点検が集中しやすいです。
また、作成したレセプトに不備・ミスがある場合は、返戻・査定があり、修正を行って再び請求する必要があります。
医療サービスに対するお金を正確に請求するための事務作業になるため、レセプト業務は経営を行う上で重要な業務といえるでしょう。
診療報酬が支払われる仕組み
診療報酬は、保険制度を通して間接的に支払われます。
診療報酬が支払われる基本的な流れは、以下のとおりです。
- 患者が医療機関で診療を受ける
- 医療機関は診療内容をカルテから確認して診療報酬請求書(レセプト)を作成する
- 患者が窓口で自己負担分を支払う
- 医療機関が保険者に残りの費用を請求する(レセプト提出)
- 保険者は提出されたレセプトに問題ないか審査を行う
- 審査を通過した診療報酬(レセプト)の支払いが行われる
- 医療機関は診療報酬の振込を確認する
診療報酬は、レセプトの内容をもとに審査が行われ、問題なければ保険者から支払われる流れです。
レセプトの内容に不備やミスがある場合は、医療機関に通知を行い、返戻や査定を行います。
返戻はミスや不備によって請求が認められないと判断されたレセプトで、修正を行って再請求を行う必要があります。
査定の場合は、減額された状態で支払われてしまい、収益に影響が出やすいため、レセプトの内容は正確に行うようにしましょう。
レセプト業務の内容

レセプト業務の内容は、主に5つあります。
- 診療内容の確認
- レセプトの作成
- レセプトの提出・請求管理
- 診療報酬の適正化
- 医療スタッフとの連携・研修
それぞれの業務内容について解説します。
診療内容の確認
レセプト業務の中には、診療内容の確認作業が挙げられます。医師のカルテや看護記録、検査データなどを確認し、どの診療行為が行われたかを把握する作業になります。
点数算定に必要な情報整理を行う作業でもあり、適当に対応してしまうと返戻の原因になりやすいです。
たとえば、内科で患者が診察を受け、血液検査と処方箋が出された場合は、診察料や検査料、薬剤料を確認します。
ほかにも、カルテに血液検査の結果や実施内容が正確に記載されているかを確認するようにしましょう。
レセプトは少しのミスや不備でも返戻の対象となるため、診療内容の確認作業は慎重に行う必要があります。
レセプトの作成
レセプトの作成は、レセプト業務の中でもとくに重要な業務です。診療内容を保険点数に基づいてレセプト(請求書)にまとめる作業で、専門的な知識が欠かせません。
レセプトを作成するときは、診療行為と算定ルールを一致させるようにしましょう。実際に行った診療行為を、診療報酬点数表に沿って正確に算定します。
また、保険証の有効期限や負担の割合、公費の併用を正しく処理する必要があります。
加えて、診療行為に関連する病名がないと査定対象になるため、行為ごとに対応する病名を正しく紐付けるようにしてみてください。
レセプトの提出・請求管理
レセプトの作成が終わったあとに、健康保険組合や国民健康保険にレセプトの提出を行うこともレセプト業務の一つです。また、提出後の請求状況を管理し、支払いまでを追跡します。
提出したレセプトに返戻や査定がある場合は、保険者から通知が届きます。
返戻の場合はどの部分にミス・不備があるのか通知が届くため、内容に沿って修正を行い、再提出することが必要です。
支払い状況を管理表で記録していると、未収になってしまう状態を避けられます。
診療報酬の適正化
医療行為が保険適用のルールに沿っているかチェックする診療報酬の適正化は、レセプト業務の一つです。
不適正請求を防ぎ、医療機関の収入を最大化するための分析も行います。
具体例を挙げると、同じ日に複数回の血液検査を算定していないかチェックしたり、過去のレセプトを照合して、請求漏れがないか確認したりします。
ほかにも、保険点数が改定された場合は、レセプト作成ルールを更新し、次回以降の作成時に役立てる状態を構築することもレセプト業務です。
医療スタッフとの連携・研修
レセプト業務は、医療スタッフとの連携や研修も挙げられます。
医師や看護師、薬剤師などと情報共有を行い、ただし診療記録や算定方法を確認することが大切です。
たとえば、保険点数の算定条件が変わった場合、医師に記録方法の統一や案内をすると、ミスが起きにくいです。
また、新しい制度やルール変更に合わせて、スタッフ向け研修を行うと良いでしょう。
月次ミーティングで、返戻理由や請求ミスを共有すると、改善策を検討しやすいです。
レセプト業務の具体的な流れ
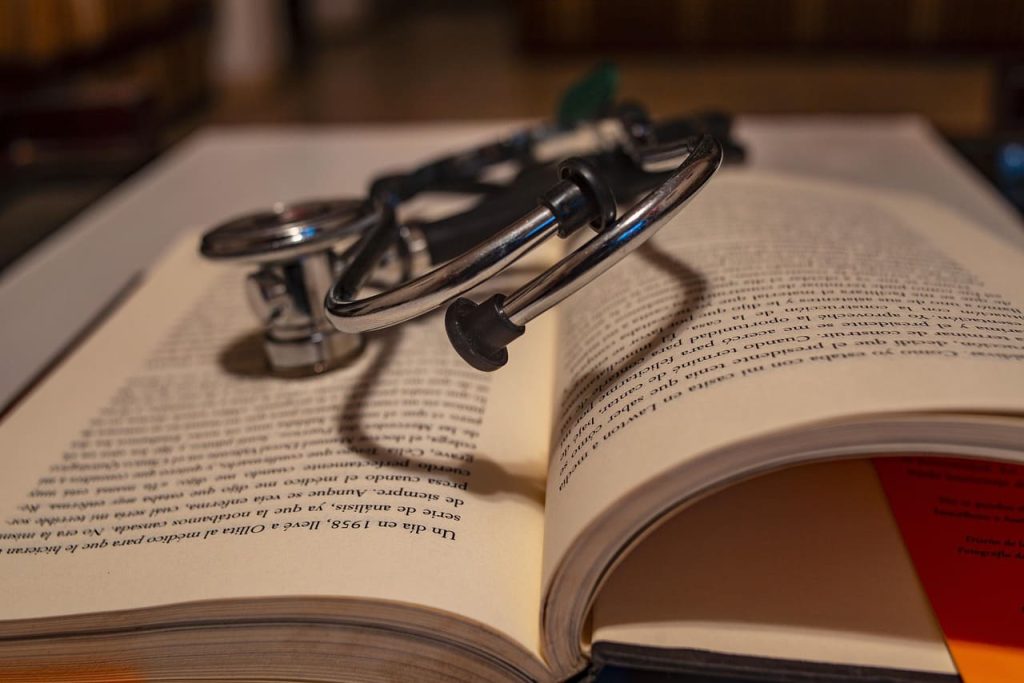
レセプト業務は、6つの流れで進めます。
- レセコンに診療情報を入力する
- レセプトを作成する
- レセプトの点検・確認を行う
- 医師に確認を求める
- 審査支払機関に提出する
- 返戻・再提出対応
それぞれの流れについて解説します。
STEP.1:レセコンに診療情報を入力する
レセプト業務を行う際には、まずレセプトコンピュータ(レセコン)や電子カルテに、診療行為や検査、処方などを入力しましょう。
点数算定の基礎データとなるため、診療情報を入力する段階でミスがあると、後の工程に直結します。
具体的には、氏名や生年月日、保険者番号・資格確認結果など、患者の基本情報を入力しましょう。
ほかにも、初診料や再診料、注射・処置・手術など診療行為の入力も行います。
とくに、カルテやレセコンに入力する際には、診療行為と対応する病名を必ず紐づけるようにしましょう。
STEP.2:レセプトを作成する
電子カルテやレセコンに入力が終わったあとは、登録した情報をもとに、患者ごとの診療報酬明細書(レセプト)を作成します。
レセコンを利用している場合は、自動的に患者ごとのレセプトが生成されますが、自動生成後に補足修正や調整が必要になる場合があります。
たとえば、作成したレセプトを確認し、内容がカルテと一致しているかチェックしましょう。
ほかにも、自費診療と保険診療の区分が正しく処理されているかなども確認するのがおすすめです。
また、入院レセプトの場合は、診療年月日ごとの算定内容が過不足なく反映されているかチェックしてみてください。
STEP.3:レセプトの点検・確認を行う
レセプトを作成したあとは、レセプトの点検や確認を行います。レセプト業務の中でもとくに重要な業務で、返戻や査定を減らすためには欠かせません。
記載漏れや点数の誤算定、ルール違反がないか重点的にチェックしましょう。
具体例を挙げると、同日に同一の検査が2回算定されていないかや、特定の加算廃止の指示記録のもとで行われているか、算定ルールの確認をするのがおすすめです。
ほかにも、保険証の有効期限や資格喪失日の確認などを行うと、返戻を受ける可能性を下げられます。
STEP.4:医師に確認を求める
レセプト点検の段階で不明な点がある場合、医師や医療スタッフに確認するのが好ましいです。医師の記載不足や診療録の整合性不足は、返戻や減点の原因につながります。
たとえば、検査は実施しているものの、カルテに検査名が未記入の場合は、医師に追記を依頼しましょう。
ほかにも、処方薬が適応疾患と合致していないときは、医師に診断名の追加を依頼する必要があります。
返戻や減点は収益に影響が出るだけでなく、修正をして再提出の手間が発生するため、不明な点は医師に確認を求めて最小限に抑えましょう。
STEP.5:審査支払機関に提出する
点検や修正を終えたあとは、レセプトを支払基金や国保連合会に提出しましょう。レセプトの提出は、紙レセプトまたはオンライン請求で行うことが可能です。
具体的には、月末に締めを行い、翌月10日までに提出するようにしましょう。オンライン請求では、レセプトデータを一括送信を行い、受付番号を確認します。
提出控えを保存したあと、提出件数や請求額を台帳に記録しましょう。
STEP.6:返戻・再提出対応
審査支払機関に提出をした際に、不備がない場合はそのまま指定した銀行口座に診療報酬が振り込まれます。
しかし、提出したレセプトに不備があると判断された場合は、通知とあわせてレセプトが返戻されます。
返戻を受けた状態は審査に通過しなかったレセプトになるため、放置していると診療報酬が支払われません。
そのため、返戻されたレセプトは修正を行い、再提出を行う必要があります。
返戻を受けやすい理由としては、算定ルール違反や診療記録記載不足、適応疾患不一致などが挙げられます。
返戻があると、修正や再提出の手間が発生するため、負担を減らすためにも診療情報の入力や点検の段階で慎重に行いましょう。
レセプト業務を正確かつ効率良く行うコツ

レセプト業務を正確かつ効率良く行うコツは、主に7つあります。
- 診療内容や処方情報は早めに整理する
- レセプトソフトの機能を活用する
- 定期的にルールを確認する
- ダブルチェック体制を整える
- 提出スケジュールを管理する
- 過去のレセプトを参考にする
- 情報共有を怠らずに徹底する
それぞれのコツについて解説します。
診療内容や処方情報は早めに整理する
レセプト業務を効率良く行いたい場合は、診療内容や処方情報を早めに整理しましょう。
正確性を高めたいときは、診療後の時間が経っていない間に、診療記録や処方情報を登録するのがおすすめです。
また、すぐに対応が難しい場合は、その日のうちに整理をすることで、後で漏れや誤りが出てしまう状態を防げます。
たとえば、午前外来が終わった段階で、実施した検査や処方内容をレセコンに入力しておくと良いでしょう。
レセプトソフトの機能を活用する
効率良くレセプト業務を進めたい場合は、レセプトソフトの機能を活用しましょう。
近年のレセコンや電子カルテには、エラーチェック機能や自動計算、過去データ参照などの便利な機能が備わっています。
具体例を挙げると、ソフトのチェック機能を活用することで、二重算定や適応疾患の不足があった際に、自動で警告してくれます。
ほかにも、処方入力時に薬剤コードを自動で補完させるようにすると、入力ミスを減らすことが可能です。
返戻や査定を受ける可能性を減らせるため、レセコンや電子カルテを活用する際には、搭載されている機能にも注目してみてください。
定期的にルールを確認する
レセプト業務を効率良く行いたい場合は、定期的にルールを確認しましょう。
診療報酬は2年ごとに大きな改定があり、最新ルールを押さえていないと正しく算定できません。
具体例を挙げると、特定疾患療養管理料の算定条件が改定された場合、定期的な勉強会でスタッフ全員に周知すると良いでしょう。
ほかにも、新しい加算が導入された場合、患者説明が必要・同意書が必要などの算定条件を確認するのがおすすめです。
ダブルチェック体制を整える
ダブルチェック体制を整えると、レセプト業務を効率良く行えるでしょう。1人で入力から点検まで行うと、ミスに気づきにくいです。
一方、複数人で確認するダブルチェック体制を導入すると、1人では気づけなかったミス・誤りを発見できます。
不備を減らすことで、返戻や査定を受ける可能性も下げられます。返戻の量が減ることによって、修正にかかっていた時間がなくなるため、医師や医療事務スタッフの負担を軽減できるでしょう。
提出スケジュールを管理する
レセプト業務を効率良く行いたいときは、提出スケジュールを管理しましょう。毎月10日が提出期限となっており、直前に慌ててレセプト入力・点検を行ってしまうと、ミスが多くなりやすいです。
余裕を持って計画的に進めることで、焦って対応する必要がないため、不備が出る可能性を抑えられます。
提出締め切りギリギリに行うと、エラーが出た際に再提出の時間がなくなるため、計画的に進めるようにしましょう。
過去のレセプトを参考にする
過去のレセプトを参考にすると、レセプト業務を効率良く行えます。同じ病名や同じ処置の患者の過去レセプトを確認すると、算定漏れや入力ミスを防げます。
具体例を挙げると、同じ薬剤を長期処方している患者の過去のデータを確認し、日数や数量にズレがないか確認すると良いでしょう。
ほかにも、過去の処方内容と比較しながら進めることで、ミスがあった際に気づきやすいです。
情報共有を怠らずに徹底する
レセプト業務を効率良く進めたいときは、情報共有を怠らずに徹底しましょう。医師や看護師、事務の間で記録やルールの共通理解を持つことが重要です。
情報が分断されていると、請求ミスに繋がってしまいます。
たとえば、月次ミーティングで、今月返戻されたケースを共有しておくと、次回からの改善につながります。
レセプト業務を行う際の注意点

レセプト業務を行う際の注意点は、主に5つあります。
- カルテや処方箋に基づき診療情報を正確に入力する
- 保険点数や併算定制限などのルールを確認する
- 返戻・指摘対応を徹底する
- 数字やコードの打ち間違い・入力ミスを避ける
- 提出期限を遵守する
それぞれの注意点について解説します。
カルテや処方箋に基づき診療情報を正確に入力する
レセプト業務を行う際には、カルテや処方箋に基づいて診療情報を正確に入力しましょう。カルテと処方箋に記載された内容とレセプトが一致していないと、返戻対象となってしまいます。
具体例を挙げると、カルテに高血圧症で内服管理と記載しているのにもかかわらず、レセプトに糖尿病管理料が算定されていると、不一致で返戻を受けます。
返戻を受けないために、診療情報を正確に入力を行い、カルテとレセプトが合致しているか確認しましょう。
保険点数や併算定制限などのルールを確認する
診療報酬には、同日に算定できない組み合わせや、算定回数の制限があるため、ルールを入念に確認しましょう。たとえば、初診料と特定疾患療養管理料は、同日に算定できないため、両方入れてしまうと返戻を受けます。
ほかにも、心電図などの検査は月1回しか算定できないのに、同月に2回算定してしまうと、返戻を受けてしまいます。
そのため、診療報酬点数表をチェックし、算定ルールに沿ったレセプト作成ができているかチェックしましょう。
返戻・指摘対応を徹底する
レセプト業務の注意点として、返戻・指摘対応を徹底しましょう。返戻や保険者からの指摘を放置していると、その診療分の診療報酬が支払われません。
具体例を挙げると、保険証の資格切れで返戻があった場合は、患者に確認を取って新しい保険証で再請求を行いましょう。
ほかにも、疾病名不足で算定不可になっているときは、医師に確認して傷病名を補記し、再提出を行うようにしてください。
数字やコードの打ち間違い・入力ミスを避ける
数字やコードの打ち間違い、入力ミスはなるべく避けるようにしましょう。わずかな数字・英字の誤りでも、不備や査定の対象になります。
ほかにも、数字の0(ゼロ)と、アルファベットのO(オー)を誤って入力してしまうと、不備として返戻を受けます。
また、医薬品のコード入力で、後発品を選択すべきところを、先発品にしてしまうと、返戻を受けるため注意しましょう。
提出期限を遵守する
レセプト業務の注意点として、提出期限を遵守しましょう。レセプトは毎月10日までに提出する必要があり、遅れてしまうと翌月請求扱いになります。
翌月請求扱いになってしまうと、資金繰りに影響が出てしまう可能性があるため、注意が必要です。
たとえば、提出前に点検に時間をかけすぎてしまうと、締切に間に合わないという状態になってしまいます。
レセプトはミスが許されないため、計画的に進めて余裕を持った状態で提出しましょう。
レセプト業務のスキルを上げる方法

レセプト業務のスキルを上げる方法は、主に5つあります。
- 診療報酬制度の理解や医療用語・疾患・薬剤などの基礎知識を強化する
- レセプト作成・チェックを何度も行う
- 学会・セミナーなどに参加して情報収集をする
- 作業手順のマニュアル化を行う
- 上司や先輩にレビューしてもらう
それぞれの方法について解説します。
診療報酬制度の理解や医療用語・疾患・薬剤などの基礎知識を強化する
レセプト業務のスキルを上げたい場合は、診療報酬制度の理解や医療用語・疾患・薬剤などの基礎知識を強化しましょう。点数表や算定ルール・医学的な背景を理解することにより、入力やチェックの精度を上げることが可能です。
たとえば、診療報酬改定のたびに、厚生労働省の通知や疑義解釈資料を確認すると良いでしょう。
ほかにも、医薬品コード表や併算定禁止ルールを定期的に見直すのもおすすめです。
レセプト作成・チェックを何度も行う
レセプト作成やチェックを何度も行う方法も、レセプト業務スキルを上げる方法として活躍してくれます。実際にレセプトの作成・点検を繰り返し行うことで、パターン認識を鍛えられます。
また、チェックリストを活用し、薬の日数や病名、検査回数などを重点的に確認すると、ミスが起きやすい点の不備を防ぎやすいです。
過去の返戻になったレセプトを教材にし、自分であればどのように修正するか考えるのもおすすめです。
学会・セミナーなどに参加して情報収集をする
学会・セミナーなどに参加して情報収集すると、レセプト業務スキルが向上しやすいです。制度改定や最新の実務対応は、現場だけでは追いつかないこともあります。
外部研修を利用して情報を収集することで、知識をアップデートできます。
具体例を挙げると、診療報酬改定セミナーや、医療事務技能研修に参加すると良いでしょう。
また、医療事務協会や、レセプト関連団体の勉強会に参加し、他院の事例や工夫を学ぶのもおすすめです。
作業手順のマニュアル化を行う
レセプト業務スキルを上げたいときは、作業手順のマニュアル化を図りましょう。業務の流れを可視化することで、作業ミスを減らし、再現性のあるスキルを身につけられます。
たとえば、レセコン入力チェックリストや、返戻対応フロー図を作成してチームで共有すると、院内スタッフ全体のスキルアップが期待できます。
ほかにも、病名不足や点数重複などのよくあるミスをマニュアルに追記しておくと、同じミスを防ぎやすいです。
上司や先輩にレビューしてもらう
上司や先輩にレビューしてもらうのも、レセプト業務のスキルを上げる方法としておすすめです。
上司や先輩に確認してもらうことで、自分では気づきにくい誤りや改善点を、経験者の視点からフィードバックしてもらえます。
また、ミスを減らすために、新人のうちは必ず先輩にレセプトをダブルチェックしてもらうと良いでしょう。
返戻があった際には、先輩や上司と一緒に、どこが間違っているのか、どのように修正するべきだったのか確認すると、スキルアップが図れます。
レセプト業務に関するよくある質問
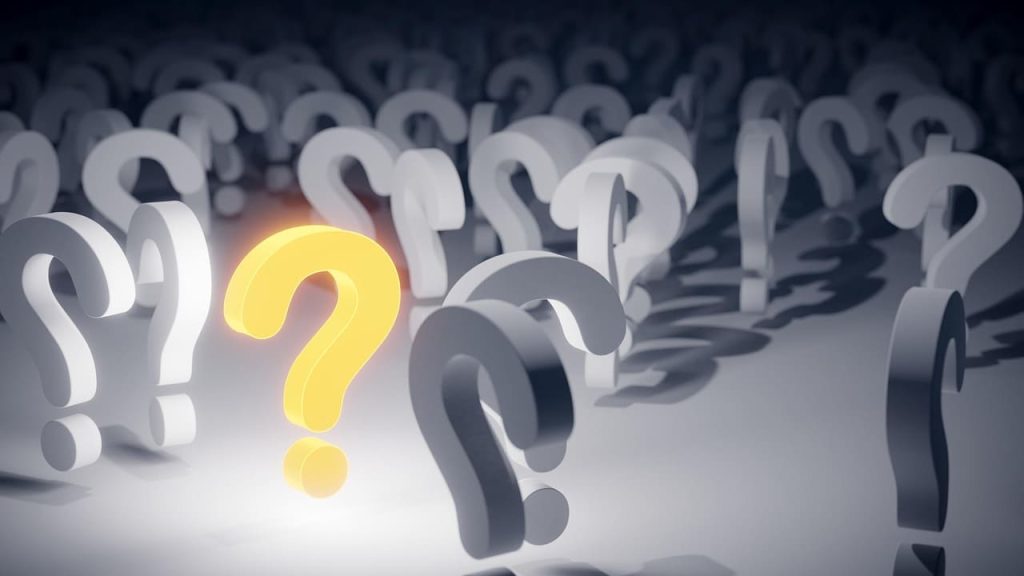
レセプト業務に関するよくある質問は、主に3つあります。
- レセプト業務は未経験でもできますか?
- レセプト業務でよくあるミスはなんですか?
- レセプト業務はどのような勉強方法がありますか?
それぞれの質問に対して解説していきます。
レセプト業務は未経験でもできますか?
レセプト業務は、未経験でも作成することは可能です。ただし、レセプトの作成は、医療用語や診療報酬制度などの専門知識が必要であるほか、レセコン操作の習熟が必須です。
そのため、未経験の場合は、先輩や上司と一緒に確認しながらレセプト作成を行うのが良いでしょう。
また、過去のレセプト事例を参考にしながら、自身でレセプトの作成をしてみると経験を積めます。
レセプト業務でよくあるミスはなんですか?
レセプト業務でよくあるミスは、診療報酬の算定ミスや入力ミスが挙げられます。算定ミスや入力ミスがあると、返戻の原因となるため、注意が必要です。
たとえば、入力ミスでは薬の数量や日数、医療行為コードの間違いが多いです。
なかには、カルテに検査名や病名が未記載で返戻を受けるというケースもあるため、慎重に対応するようにしましょう。
レセプト業務はどのような勉強方法がありますか?
レセプト業務の勉強方法では、実務経験とあわせて、学習・研修・復習の組み合わせがおすすめです。
たとえば、診療報酬の基礎や医療用語の勉強は、市販のテキストなどを活用すると良いでしょう。
実践的な学習では、過去のレセプトと診療報酬点数表を使い、処置や検査の点数を調べたり、自身でレセプトを作成してみたりするのがおすすめです。
ほかにも、通信講座や専門学校を活用し、専門知識を持つプロの指導を受けながら学ぶ方法もあります。
あわせて、最新の制度改定や疑義解釈を習得したい場合は、セミナーや学会に参加すると良いでしょう。
まとめ:レセプト業務は正確な計算と医療機関内の連携が重要
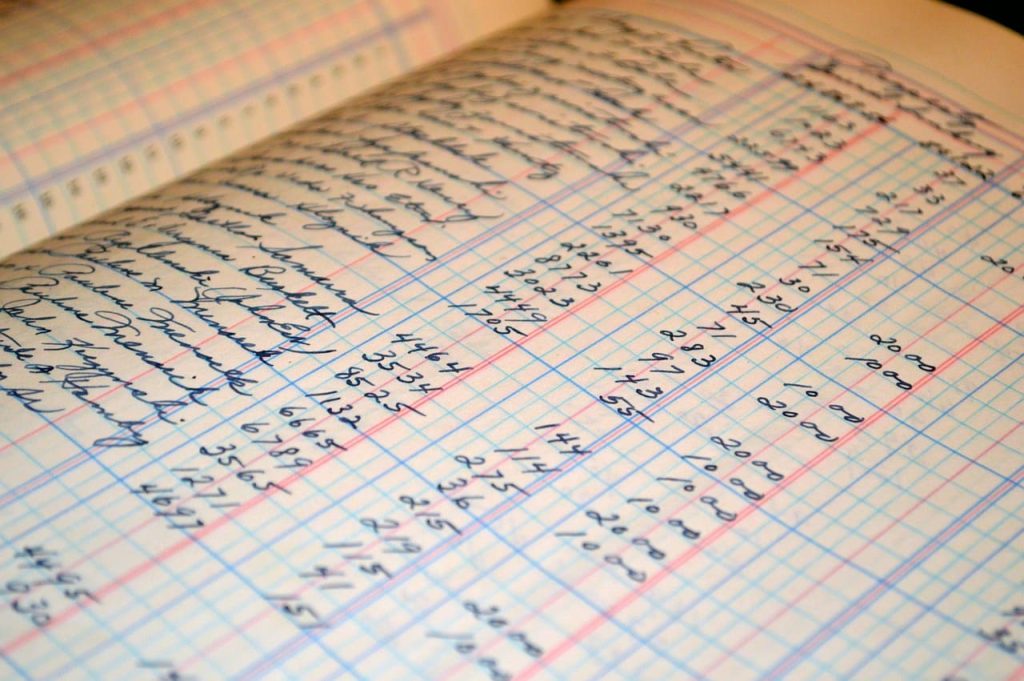
レセプト業務は、正確な計算と医療機関内の連携が重要です。スケジュールギリギリまで先延ばしにしてしまうと、提出直前で焦ってしまい、ミスを誘発してしまう可能性があります。
計画的にスケジュール管理を行い、診療情報をすぐに入力していくことで、不備や記入漏れをなくしやすいです。
収益に影響するため、レセプト業務は余裕を持った状態で慎重に行うようにしましょう。


