「病院の物品管理表を用意しないといけないけど、必要な項目は知りたい……」
「物品管理表を作るうえで、起きやすい課題と対策を知っておきたい……」
このような疑問を抱えていませんか?
病院の物品管理表は、部署によって形式が異なり、在庫切れを防止して必要なときに必要な物品が使える状態を維持しやすい点が魅力です。
しかし、物品管理表を適当に作ってしまうと、使いにくいだけでなくさまざまなトラブルが起きる可能性があります。
そこで、本記事では病院の物品管理表について解説します。
病院の物品管理表の必要項目や、作る際の注意点も紹介しているので、参考にしてみてください。
この記事の内容
病院で使う物品管理表とは?

病院の物品管理表は、病院内で使用する医療材料・備品の在庫や使用状況を記録・管理するための一覧表です。
医療現場では、注射器やガーゼ、薬剤など取り扱っている物が多いため、物品管理表を使って管理するのが好ましいです。
物品管理表はExcelなどを使用して紙で管理する方法や、電子管理システムを導入して利用する方法が挙げられます。
医療の安全性とコスト管理の両方の面で欠かせない管理表です。
病院の物品管理の重要性
病院では、診療や看護に必要な物品が常に適切に管理されてないと、患者の安全性や業務効率に大きな影響を及ぼします。
たとえば、滅菌期限が過ぎた注射針は、カテーテルを使用すると、感染リスクが高まりやすいです。
また、手術室で必要な機材が揃っていないと、手術の進行が遅れる可能性があります。
さらに、物品管理表を利用することで、必要なものを必要なときに、必要な量だけを準備できるため、医療材料費を削減できます。
物品管理における法的要件と基準
物品管理表は、病院の物品管理の効率化を図るだけでなく、法令やガイドラインに基づいた運営・作成が必要です。
とくに、物品管理を行う上で意識したい法的要件と基準は、以下の4つが挙げられます。
- 医薬品医療機器等法
- 医療法・医療安全管理指針
- 診療報酬・監査との関連
- トレーサビリティ
たとえば、輸液ポンプや滅菌機材などの医療機器は、承認を受けたものを使用する必要があります。
また、注射器やディスポ手袋などの、ディスポーサブル製品は、感染対策上の基準として、再利用できません。
さらに、診療報酬の算定要件に、安全な器材・薬剤の使用が含まれており、在庫や使用記録をきちんと残していないと監査で不備を指摘される可能性があります。
そのため、物品管理はさまざまな法令やガイドラインに基づいて行う必要があります。
病院で使う物品管理表の内容

病院で使う物品管理表の内容は、4つ挙げられます。
- 発注する物品の管理
- 消耗品の管理
- 固定資産の管理
- 請求などの出費の管理
それぞれの内容について解説します。
発注する物品の管理
病院で使う物品管理表の内容では、発注する物品の管理を入れましょう。病院では、薬剤や医療材料を定期的に仕入れる必要があります。
発注量やタイミングを管理しないと、在庫不足や過剰在庫が起こりやすいです。
たとえば、手術をする際に、手術用ガウンやマスクが不足していると、緊急手術に支障が出る可能性があります。
ほかにも、点滴ルートチューブを大量発注しすぎてしまった場合、有効期限切れによる廃棄ロスが発生し、不要な出費が生まれます。
消耗品の管理
病院では、消耗品の使用頻度が高いため、こまめにチェックするためにも消耗品の管理を行いましょう。
手袋や注射器、消毒アルコールなどは、日常的に大量に消費します。
そのため、部署ごとに使用料や残量を記録し、翌月の必要数を見積もると良いでしょう。
また、滅菌ガーゼなどの消耗品は、滅菌期限があるので、物品管理表で期限切れチェック欄を設けるのがおすすめです。
固定資産の管理
固定資産の管理は、物品管理表の内容に入れるようにしましょう。
医療機器や設備は、高額かつ長期的に使用するため、耐用年数や点検記録を含めて管理する必要があります。
たとえば、輸液ポンプや心電図モニターは、購入日や使用部署、点検日、故障履歴を管理するのがおすすめです。
ほかにも、ポータブルレントゲンは、数十万円から数百万円以上するため、資産台帳に登録し、減価償却の対象として処理しましょう。
耐用年数や点検記録を含めて管理し、固定資産の状況を把握するようにしてください。
請求などの出費の管理
病院で物品管理表を作るときは、請求などの出費の管理を入れましょう。
物品購入に伴う費用を管理することで、病院経営に直結する支出を可視化できます。
たとえば、毎月の医療材料費を管理表で集計したり、診療報酬でカバーできない未収金や廃棄ロスなどのコストを管理表で別枠として可視化したりしましょう。
部署ごとに経費を分けて管理することで、どの部署でコストがかかっているかがわかりやすく、改善につながります。
病院の物品管理表を作る際の注意点

病院の物品管理表を作る際の注意点は、5つあります。
- 必要な項目を網羅して記録する
- 在庫管理にかかるコストを可能な限り減らす
- 在庫管理を行う際には必ず記入する
- データを登録・入力する際には上書きしない
- ルールを制定・統一させる
それぞれの注意点について解説します。
必要な項目を網羅して記録する
物品管理表は、必要な項目を網羅して記録する必要があります。
作成する際には、物品ごとに「いつ」「どれだけ」「どこにあるか」がわかるように記録しましょう。
ほかにも、以下の項目を記録するのがおすすめです。
- 物品名
- 数量
- 型番
- 使用期限
- 保管場所
- 発注日
- 使用者
このように記録することで、誰でも在庫状況を正確に把握できます。
在庫管理にかかるコストを可能な限り減らす
病院の物品管理表を扱うときの注意点として、在庫管理にかかるコストを可能な限り減らしましょう。
物品管理表を作ることで、各物品ごとの在庫数が確認できます。
また、使用期限や使用頻度を確認することで、無駄な在庫を抱えず、必要なときに必要な量だけ管理できます。
月ごとの消費量を把握し、発注量を調整しましょう。
在庫管理を行う際には必ず記入する
在庫管理を行ううえで、棚卸しや在庫確認をした際には、必ず記入するようにしましょう。
たとえば、毎週月曜日に各部門で在庫を確認し、表に在庫数や確認者、確認日を記入するのがおすすめです。
在庫数や確認者・確認日を記入することで、誰がいつ確認したかが明確になり、紛失や誤差を早期に発見できます。
データを登録・入力する際には上書きしない
病院の物品管理表を作成・取り扱う際には、データを登録・入力する際には上書きしないようにしましょう。
過去の記録を消してしまうと、誰がどれだけ使用したかが追跡できず、トラブルが生まれる可能性があります。
Excelや在庫管理システムで数量を変更する際には、前回在庫→今回在庫(使用数)のように、変更履歴を残しましょう。
ルールを制定・統一させる
病院の物品管理表を作成する際は、ルールの制定や統一に注意しましょう。
記録方法や確認方法をスタッフ全員で統一させることで、誤記入や混乱を防ぎます。
たとえば、毎週月曜日に在庫確認を行う、使用した物品は使用日・数量・使用者を必ず記入するといったルールの制定がおすすめです。
また、ルールをマニュアル化しておくと、新人でも間違いなく運用できます。
病院の物品管理表で起きやすい課題と対策

病院の物品管理表で起きやすい課題は、4つあります。
- 部門ごとに内容が統一されていない
- 正確な利用状況がわかりにくい
- 棚卸業務の現物検査に膨大な時間がかかる
- 不備を外部機関に指摘される
それぞれの課題と対策について解説します。
部門ごとに内容が統一されていない
病院の物品管理表では、部門ごとに内容が統一されていないという点が課題として発生しやすいです。
たとえば、内科では注射器5mlと記載されているものの、外科では5mlシリンジなど表記がバラバラな状態になるケースも少なくありません。
ほかにも、Excelや紙、管理システムなど、記録方法が異なると、全体の在庫を把握できません。課題に対する対策として、物品名称や入力ルールを統一するマニュアルを作成しましょう。
JANコードや院内独自コードを使うと、名称が多少違ってもコードで一元管理できるようになります。
正確な利用状況がわかりにくい
物品管理表の利用で起きやすい課題では、正確な利用状況がわかりにくいという点が挙げられます。
正確に記入・登録されていない場合、実際の消費量と在庫数が合わず、紛失や使いすぎが判別できません。
対策として、使用時に記録を残す仕組みを徹底しましょう。
また、システムの導入が難しい場合は、簡易な出庫表やバーコードスキャンなどを活用するのがおすすめです。
棚卸業務の現物検査に膨大な時間がかかる
物品管理表の取り扱いで起きやすい課題では、棚卸業務の現物検査に膨大な時間がかかる点が挙げられます。年に数回行う棚卸しで、数千点の物品を一つ一つ数えるのに数日かかります。
また、通常業務と並行する必要があるため、スタッフに大きな負担がかかりやすいです。対策として、定期的な小規模在庫確認を行い、大規模棚卸の負担を軽減しましょう。
ほかにも、バーコードやハンディ端末を活用し、一括読み取りをするのもおすすめです。
不備を外部機関に指摘される
不備を外部機関に指摘される点は、病院の物品管理表で起きやすい課題です。医療監査や外部審査で、記録が不十分・使用期限切れが放置されているなどの指摘を受ける可能性があります。
医療監査や外部審査などの外部機関に不備を指摘されると、信頼性が損なわれるだけでなく、改善指導やペナルティの対象になる場合もあります。
対策として、記録の残し方を標準化し、チェック体制を設けましょう。また、期限管理はシール貼付やアラート機能でわかりやすくするのがおすすめです。
さらに、在庫表に使用期限欄を必須項目として追加し、毎月1回期限が近い物品リストを出して確認すると良いでしょう。
物品管理の業務を効率化させる方法

物品管理の業務を効率化させる方法は、3つ挙げられます。
- 物品の管理方法のマニュアルを構築
- 定数管理
- 物品管理システムを活用する
それぞれの方法について解説します。
物品の管理方法のマニュアルを構築
物品管理の業務を効率化するために、物品の管理方法のマニュアルを構築しましょう。誰が物品管理を行っても、同じ手順で管理できるようにルール化するのが好ましいです。
たとえば「使用したら必ず在庫表に数量・日付・使用者を記入する」「物品名称は統一する」というルールをマニュアル化することで、新人でも迷わず対応できます。
マニュアルをしっかりと構築することにより、管理のばらつきがなくなります。
定数管理
物品管理を行う際には、定数管理がおすすめです。部門ごとに「常に一定数を置く」という方式で、細かい出入りを逐一記録しなくても良い状態を作ります。
たとえば、手術室にはガーゼは常に100枚・注射器は50本置くと決め、使用して減った際には翌日や週末に補充して必ず元の数に戻すという方法が定数管理です。
在庫表には、使用分を記録するのではなく、補充した数を記録すれば問題ありません。
記録作業がシンプルになり、現場スタッフの負担が減るためおすすめです。
物品管理システムを活用する
物品管理の業務を効率化したいときは、物品管理システムを活用しましょう。Excelや紙ではなく、専用のシステムやアプリを利用することで、在庫を自動的に見える化できます。
たとえば、バーコードを読み取って入庫・出庫を記録すると、自動で在庫数が更新されます。
また、使用期限が近い物品は、自動でアラートで知らせてくれる機能が備わっているシステムもあります。
現物確認や棚卸の負担が大幅に減り、外部監査にも対応しやすいです。
病院・クリニックにおすすめの物品管理システム6選

病院・クリニックにおすすめの物品管理システムを6つご紹介します。
ODSS

| 運営会社 | 鍋林株式会社 |
|---|---|
| 価格 | 要問い合わせ |
| 特徴 | ・薬品請求業務をオンラインで行える ・専用のサーバー設置は不要 ・有効期限付きの納品データを用いて入庫 |
| 公式サイト | https://www.nabelin.co.jp/business/medical-system/odss/ |
ODSSは、クラウド型薬品在庫管理システムです。発注点や納品場所指定、納品指定など、さまざまな発注方法で発注業務を効率化できます。
薬品請求業務をオンラインで行うことが可能です。また、ハンディターミナルを利用した棚卸機能を搭載しています。
「箱」や「バラ」の棚卸単位も簡単に単位を切り替えられるため、棚卸しを行いやすいでしょう。
また、有効期限付きの納品データで入庫ができ、出庫時に有効期限付きバーコードを読み取ることで期限管理が可能です。
Medyus2
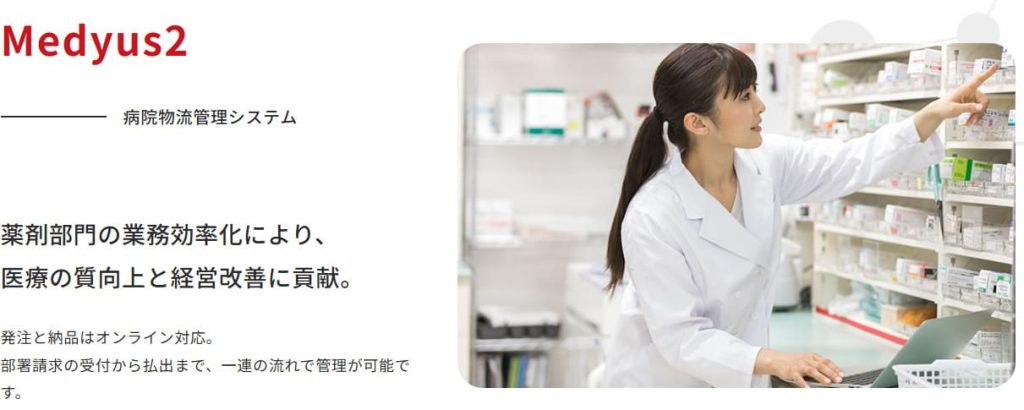
| 運営会社 | 株式会社メディアス |
|---|---|
| 価格 | 要問い合わせ |
| 特徴 | ・期限切れ管理・購買管理・在庫適正化に長けている ・発注業務の負担を軽減できる ・ABC分析機能が備わっている |
| 公式サイト | https://www.medyus.co.jp/medicine/ |
Medyus2は、期限切れ管理や購買管理、在庫適正化に長けている物品管理システムです。医薬品マスタが備わっており、薬効分類や薬価収載コード、薬価なども自動的に取得できます。
薬価改定の更新管理も容易で、医薬品の薬価状況などを把握しやすいでしょう。
また、病棟常備などの部署配置薬を、部署端末から請求可能です。
あらかじめ設定した定数一覧に請求数を登録するだけで、簡単に薬剤部に依頼できます。薬剤部は受け付けた内容を発注・納品するだけで良く、常備の補充業務を効率化できます。
ENIFwin Nex-Sus

| 運営会社 | 東邦薬品株式会社 |
|---|---|
| 価格 | 要問い合わせ |
| 特徴 | ・全国の医療機関500件以上で導入されている ・ハンディターミナルで時間の短縮化が図れる ・バーコードシールを印字してスキャン可能 |
| 公式サイト | https://www.tohoyk.co.jp/support-system/enifwin-nex-sus/ |
ENIFwin Nex-Susは、全国の医療機関500件以上で導入されている物品管理システムです。
病院薬剤部内の医薬品の購入・出庫などの移動管理や、棚卸管理などの業務運用を効率化できます。
専用のハンディターミナルがあり、発注や出庫・棚卸が倉庫内で行え、業務負担の省略化と時間の短縮が図れます。
また、プリンターでバーコードシールを印字して薬品棚や病棟棚に貼り付け、スキャニングすることも可能です。
Mediboard
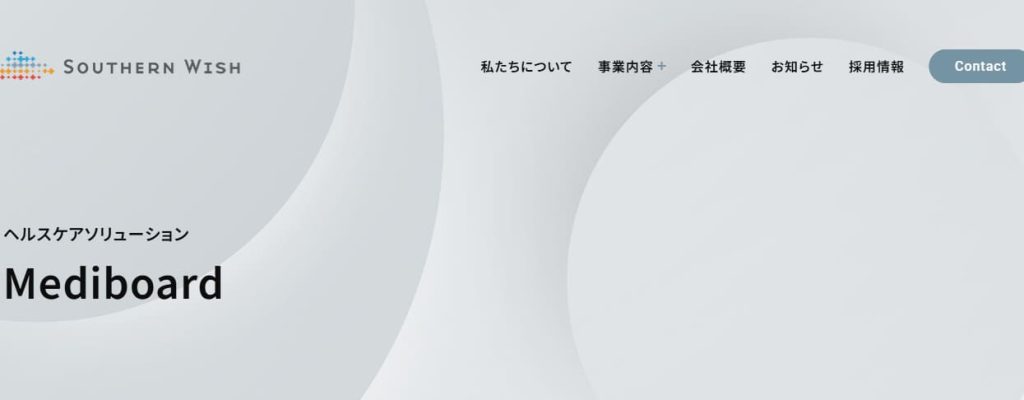
| 運営会社 | 株式会社サザンウィッシュ |
|---|---|
| 価格 | 要問い合わせ |
| 特徴 | ・申請や決済、発注から納品までデジタル化 ・抱えている課題に対して支援 ・専任の担当者がサポート |
| 公式サイト | https://www.southernwish.com/mediboard/ |
Mediboardは、申請から決済、発注から納品までをデジタル化できる物品管理システムです。GS1バーコード対応の在庫管理システムで、バーコードを読み取ってシステム内の商品の探索や納品登録が行えます。
また、現場からも納品状況を確認でき、納品問い合わせによる負荷を軽減できます。
院内の各部署や各施設の物品状況が一目でわかるため、経営分析を行いやすいです。
さらに、システムを導入する際には、専任の担当者がサポートしてくれるので、導入後に使い方がわからないという状況を避けられます。
スマートマットクラウド

| 運営会社 | 株式会社エスマット |
|---|---|
| 価格 | 要問い合わせ |
| 特徴 | ・導入件数1,800件以上 ・手入力ゼロで見える化を図る ・不動在庫を発見しやすい |
| 公式サイト | https://www.smartmat.io/ |
スマートマットクラウドは、重さで在庫管理が可能な物品管理システムです。スマートマットに管理したい物を置くだけで、重さで在庫数を算出してくれます。
常に自動計測されており、医薬品や消耗品を使用した際に通知が届き、自動発注を行います。
手入力ゼロで在庫状況の管理が可能で、管理業務負担を大幅に削減可能です。
また、不動在庫を発見しやすい分析機能も備わっているため、無駄な出費も抑えられます。
システムK-1 CUBE
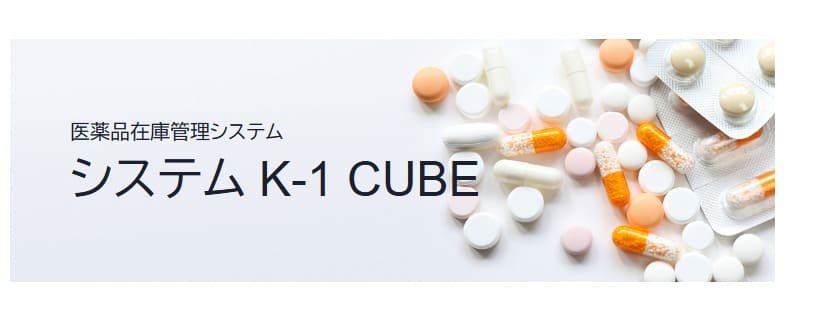
| 運営会社 | 中央システムサービス株式会社 |
|---|---|
| 価格 | 要問い合わせ |
| 特徴 | ・複数の発注データ登録が可能 ・ハンディターミナルを活用できる ・実績データを各種統計帳票として出力可能 |
| 公式サイト | https://chuoss.co.jp/business/k1cube/ |
システムK-1 CUBEは、物品管理システムの中でも、価格管理や在庫管理が可能なシステムです。発注点発注や定量発注、定期発注など、さまざまな発注に対応しています。
また、専用のハンディターミナルを活用すると在庫管理だけでなく、薬などの棚卸業務も負担軽減できます。
実績データを各種統計帳票として出力できるため、経営分析したいときにも活躍しやすいです。
まとめ:病院で使う物品管理表は運用・記入ルールの統一が重要!

病院で使う物品管理表は、運用や記入ルールの統一が重要です。
物品管理表でしっかりと物品を管理することで、医療の安全性の確保とコスト管理ができます。
少しでも物品管理表の負担を軽減したい場合は、物品管理システムを活用するのがおすすめです。
病院・クリニックを運営するうえでは重要になるため、物品管理表の作成や取り扱いで悩んでいる方は、本記事でご紹介した内容を参考にしてみてください。


