「医療用語のBIとは、どのような言葉なのだろう……」
「BIの採点方法と評価基準を知りたい……」
このような疑問・悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
医療用語のBIは「バーセル・インデックス(Barthel Index)」の略称で、入退院時の見極めや介護・リハビリ支援などに活用されます。
本記事では、医療用語のBIがどのような検査なのか、評価項目や判定基準を解説します。
信頼性やBI評価の精度を保つためのポイントも含めて紹介しているので、参考にしてみてください。
この記事の内容
医療用語のBI(バーセルインデックス)とは?

医療用語のBI(バーセルインデックス)は、日常生活動作(ADL)の自立度を評価する指標です。患者がどの程度自分で日常生活を送れるかを数値で表す評価法で、入退院時の見極めやリハビリ・介護などの支援時に利用されます。
たとえば、リハビリ前とリハビリ中にBI評価を実施し、リハビリ効果のモニタリングに活用するケースがあります。
ほかにも、退院支援として、BIスコアをもとに退院後の生活環境を判断することも可能です。
また、BI評価と同様に日常生活動作や生活機能の自立を評価する方法が2種類あります。
- FIM評価
- 生活機能チェックシート
FIM評価と生活機能チェックシートは、BI評価とどのように違うのか把握していると、状況に合わせた使い分けができます。
FIM評価との違い
BI評価とFIM評価の違いは、表の通りです。
| 項目 | BI評価 | FIM評価 |
|---|---|---|
| 評価目的 | ADLの自立度を簡易的に把握 | 自立度と介助量をより正確に把握 |
| 評価対象 | 身体的ADL | 身体的+認知的ADL |
| 評価項目数 | 10項目 | 18項目 |
| 評価方法 | 2~4段階 | 7段階 |
| 点数範囲 | 0~100点 | 18~126点 |
| 評価時間の目安 | 約5~10分 | 約20~30分 |
FIM評価は、機能的自立度評価法を指し、BI評価よりも日常生活動作の自立度をより正確に評価します。
また、BI評価は移動や排便、更衣などの身体的ADLを主に評価しますが、FIM評価は身体的評価と合わせて理解や記憶などの認知的ADLも評価します。
そのため、BI評価は身体的ADLを中心とした評価法で、FIM評価は身体的ADL評価に認知的ADLを含めたより詳細な評価法と考えるとわかりやすいです。
生活機能チェックシートとの違い
BI評価と生活機能チェックシートの違いは、表の通りです。
| 項目 | BI評価 | 生活機能チェックシート |
|---|---|---|
| 評価目的 | 日常生活動作の自立度を数値化 | 心身・社会面を含めた生活全体の把握 |
| 評価方法 | 専門職が観察・評価 | 本人記入または聞き取り |
| 評価内容 | 食事・排泄・移動などの10項目 | 運動・認知・栄養・社会関係などの他分野 |
| 利用目的 | リハビリ・介護度の評価 | 介護予防・早期支援の判断 |
BI評価と生活機能チェックシートは、どちらも生活の質を高める支援を考えるツールとして活用します。
生活機能チェックシートは、生活だけでなく、心身や社会面を含めた生活全体を把握する点が特徴です。
主に介護予防や早期支援の判断に利用され、本人記入や聞き取りによってチェックシートを活用します。
BI評価はADLの自立度を数値で表すツールで、生活機能チェックシートは生活全体の課題を見つけるチェック表と考えるとわかりやすいです。
BI(バーセルインデックス)の評価項目と採点方法

BIは、10個の項目で評価します。
- 食事
- 車椅子からベッドへの移動
- 整容
- トイレ動作
- 入浴
- 歩行
- 階段昇降
- 着替え
- 排便コントロール
- 排尿コントロール
それぞれの項目ごとに採点方法を解説します。
1.食事
食事は、0点・5点・10点の3段階で評価します。
| 点数 | 具体例 |
|---|---|
| 0点 | 食事をするために介助が必要 |
| 5点 | スプーンを口に運ぶが介助が必要 |
| 10点 | 自分で食べられる |
食事は、どの程度自力でできるかを評価します。
たとえば、手の届くところに食べ物を置くと、トレイやテーブルを使って一人で摂取できる場合は、10点です。
一方、野菜・肉類・魚などを切ったり、スプーンを補助したりと、一部介助が必要なときは5点と評価します。
2.車椅子からベッドへの移動
車椅子からベッドへの移動は、0点・5点・10点・15点の4段階で評価します。
| 点数 | 具体例 |
|---|---|
| 0点 | 介助なしでは移動できない |
| 5点 | 介助者の力を少し借りて移動できる |
| 10点 | 見守りや声がけだけで移動できる |
| 15点 | 手すりを使わずに安全に移動できる |
車椅子からベッドへの移動は、体のバランスや足の筋力について確認します。
具体例を挙げると、車椅子のブレーキをかけ、フットレストを上げてベッドに移れる場合は、15点です。
声がけや見守りだけで移動できる場合は10点、持ち上げ介助などの介助者の力が必要なときは5点と評価します。
車椅子からベッドに移動する際に、介助者がどのくらい関わる必要があるかが採点時のポイントです。
3.整容
整容は、0点と5点の2段階で評価します。
| 点数 | 具体例 |
|---|---|
| 0点 | 介助が必要 |
| 5点 | 自分で歯磨きや洗顔ができる |
たとえば、歯磨きや洗顔、整髪・ひげ剃りなどが一人でできる場合は5点です。
一方、歯磨きや洗顔などの整容を一人で対応できないときは、0点と評価します。
手の動きや細かい動作を行えるかを確認します。
4.トイレ動作
トイレ動作は、0点・5点・10点の3段階で評価します。
| 点数 | 具体例 |
|---|---|
| 0点 | おむつを使用 |
| 5点 | 介助で便座に移動する必要がある |
| 10点 | トイレ動作が全て自分でできる |
トイレ動作は、衣類の着脱や後始末などができるかをチェックします。
具体例を挙げると、手すりや福祉用具は使用するものの、自分で全てできる場合は10点です。ポータブル便器を使用した場合は、洗浄ができるかも確認します。
一方、トイレをするためにズボンを下げたり、トイレットペーパーを取ってあげたりなど、介助が一部介助が必要な場合は、5点と評価します。
5.入浴
入浴は、0点と5点の2段階で評価します。
| 点数 | 具体例 |
|---|---|
| 0点 | 介助が必要 |
| 5点 | 自分一人でできる |
たとえば、浴槽につかったり、シャワーを使ったりなど、一人で入浴できる場合は5点です。
一方、部分介助が要るときや、入浴に関する動作で全て介助が必要なときは、0点と評価します。
浴槽への出入りや身体を洗うなどの細かな動作が自力で行えるかを判断します。
6.歩行
歩行は、0点・5点・10点・15点の4段階で評価します。
| 点数 | 具体例 |
|---|---|
| 0点 | 車椅子でも自走できない |
| 5点 | 歩行に介助が必要 |
| 10点 | 見守りで歩行できる |
| 15点 | 杖や補装具を使って安全に歩ける |
歩行は「45m以上歩行できるか」や「自力で歩行できるか」がポイントです。杖や補装具を活用して、45m以上自力で歩行できる場合は、15点と評価します。
介助や監視が必要なときは10点です。
歩行が難しく、車椅子を活用すると45m移動できるときは、5点と採点します。
45mをどのような状態で歩行・移動できるかが重要なポイントです。
7.階段昇降
階段昇降は、0点・5点・10点の3段階で評価します。
| 点数 | 具体例 |
|---|---|
| 0点 | 介助が必要 |
| 5点 | 見守りや一部介助で昇り降りができる |
| 10点 | 昇り降りが自力でできる |
階段昇降は、階段の段数は関係なく「自力でできるか」「介助や見守りが必要か」で判断します。
手すりや杖などを使い安全に階段を昇り降りできるときは10点です。
階段を昇り降りする際に、一部介助や見守りが必要なときは、5点と評価します。
階段の昇り降りが介助なしでは行えない場合は、0点です。
8.着替え
着替えは、0点・5点・10点の3段階で評価します。
| 点数 | 具体例 |
|---|---|
| 0点 | 介助が必要 |
| 5点 | 半分以上は自分でできる |
| 10点 | 靴やファスナーなどの着脱が可能 |
上下の衣服を自分で着脱できる場合は、10点と評価します。
着替えをする際に、部分介助が必要であるものの、半分以上は自分でできるときは5点です。
ボタンやファスナーなどの細かい操作や、バランス感覚などを確認します。
9.排便コントロール
排便コントロールは、0点・5点・10点の3段階で評価します。
| 点数 | 具体例 |
|---|---|
| 0点 | 介助が必要 |
| 5点 | 失禁がときどきあるまたは浣腸や座薬に介助が必要 |
| 10点 | 失禁がなく浣腸や座薬の取り扱いができる |
排便コントロールは「失禁の有無」や「浣腸・座薬が自力でできるか」が重要な採点ポイントです。
失禁がなかったとしても、浣腸や座薬を利用する際に介助が必要なときは、5点と評価します。
浣腸や座薬まで一人でできる場合は10点になります。
10.排尿コントロール
排尿コントロールは、0点・5点・10点の3段階で評価します。
| 点数 | 具体例 |
|---|---|
| 0点 | 介助が必要 |
| 5点 | 失禁がときどきあるまたは収尿器の取り扱いに介助が必要 |
| 10点 | 失禁がない |
排尿コントロールは「失禁の有無」や「収尿器の取り扱いに介助が必要か」で判断します。
失禁がない場合は10点と採点します。
一方、失禁がなくても、収尿器の着脱や管理に介助が必要なときは5点です。
BIの一般的な評価・判定基準

BIは、10項目の合計点数をもとに評価します。
| 点数 | 評価基準 |
|---|---|
| 40点未満 | 全介助 |
| 40~60点未満 | 部分介助 |
| 60~85点未満 | 部分自立 |
| 85点以上 | 自立 |
細かな評価基準は病院や施設によって異なりますが、一般的には85点以上で自立、60~85点未満で部分自立、40~60点未満で部分介助、40点未満で全介助と判断します。
また、BIにおける自立と介助は60点が分岐点といわれており、介護の内容を判断するうえで重要な境目です。
在宅や介護施設での日常動作を簡単に評価したいときや、入退院時のADLを素早く把握したいときは、BI評価を活用してみてください。
医療業界で利用されるBIの主なメリット

医療業界で利用されるBIのメリットは、主に3つあります。
- 評価方法が簡単で短時間で行える
- 客観的なスコアでADLの自立度を数値化できる
- 機能回復やリハビリ効果のモニタリングに役立つ
それぞれのメリットについて解説します。
評価方法が簡単で短時間で行える
BIは、簡単かつ短時間で評価を実施できる点がメリットです。BIは10項目の評価基準をもとにして観察・採点するだけで評価でき、特別な機器は必要ありません。
慣れると5~10分程度の短い時間で実施可能で、医師やリハビリスタッフが忙しい中でも素早く評価できます。
短時間で評価が可能で、評価者の負担が少ない点から、多くの病院や介護施設で利用されています。
客観的なスコアでADLの自立度を数値化できる
BIは客観的なスコアで、ADLの自立度を数値化できます。自立度を数値化することにより、スタッフ間での情報共有が容易になり、主観に偏らない客観的な評価が可能です。
具体例を挙げると、同じ患者の状態をリハビリ担当医や看護師、看護スタッフで共有可能で、共通認識のもとで経過観察ができます。
病棟内や多職種チームでの情報共有・退院判断・介護計画の作成などに役立つ点がBIの魅力です。
機能回復やリハビリ効果のモニタリングに役立つ
BIは、機能回復やリハビリ効果のモニタリングにも役立ちます。BIを繰り返し行うことで、ADLの改善やリハビリ効果を数値で追跡することが可能です。
たとえば、脳梗塞の患者に対して、入院時と2週間後にBI測定を行うと、ADLの状況を把握できます。
また、リハビリ効果のモニタリング目的でBIを実施する場合、改善が見られない項目は別のリハビリ方針を検討するなど、判断材料として活用できます。
リハビリの成果や機能回復を客観的に示せるため、患者や家族への説明に便利です。
医療業界で利用されるBIのデメリット
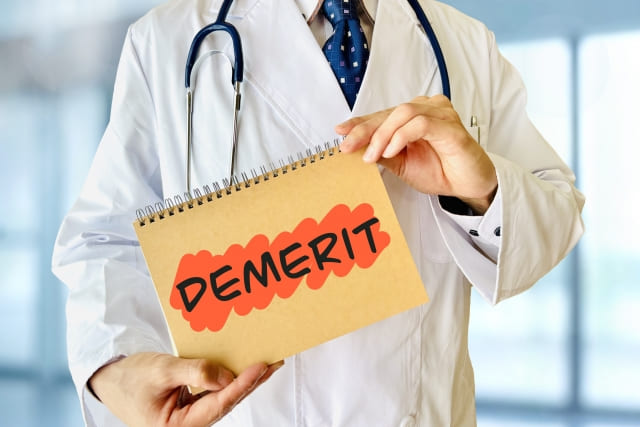
医療業界で利用するBIのデメリットは、主に3つあります。
- 細かい変化を捉えにくい
- 評価者の主観に左右される
- 潜在能力を反映しにくい
それぞれのデメリットについて解説します。
細かい変化を捉えにくい
BI評価を活用するときは、細かい変化を捉えにくい点に気をつけましょう。BIは「できる・できない」や「一部介助・全介助」といった大まかな段階評価で構成されています。
たとえば、脳卒中の患者が、食事をスプーンで1/3しか食べられなかった状態から、半分くらいまで自分で食べられるようになっても、BIでは「一部介助」のままで点数が変わりません。
そのため、細かく経過を追いたいという場面では不向きです。小さな変化を評価したい場合は、FIMを活用するのがおすすめです。
評価者の主観に左右される
BIは、客観的な点数を付ける仕組みではあるものの、評価者の主観に左右される点に注意しましょう。
具体例を挙げると、一人の患者に対して、看護師Aは「見守りが必要」と判断して10点中5点を付け、看護師Bが「ほぼ自立」と見て10点中10点を付ける場合があります。
とくに、看護師や理学療法士、作業療法士など多職種が関わるチームでは、統一基準を持たないと比較が難しくなりやすいです。
チームで評価する際には、どの動作をどこまでできたら「自立」と判断するか、事前に共通認識を定めておくと良いでしょう。
潜在能力を反映しにくい
BIは、潜在能力を反映しにくい点がデメリットです。BIは、実際にどのくらい自立して生活しているかの「実行能力」を評価します。
そのため、能力はあるのに、環境や習慣による影響でできない人の潜在能力は反映できません。
たとえば、軽い認知症の方が、入浴をする際に入浴動作や手順を忘れてしまった場合でも、介助が必要と判断される場合があります。
実際は声がけや環境を調整するだけで自分でできる可能性があるのに、介助が必要という低い点数になり、本来の身体能力よりも低く評価されるケースがあります。
そのため、実際のパフォーマンスだけでなく、IADL評価や認知機能テストを併用するのがおすすめです。
BI評価の精度と信頼性を保つための5つのポイント

BI評価の精度と信頼性を保つためのポイントは、主に5つあります。
- 評価基準を統一させる
- 能力評価ではなく遂行評価を重視する
- 多職種で情報を共有する
- 定期的な再評価と比較を行う
- BI評価者の教育と訓練を実施する
それぞれのポイントについて解説します。
1.評価基準を統一させる
BIを多職種間やチームで運用するために、評価基準を明確に統一させることが大切です。
同じ行為でも、どこまでできたら「自立」とみなすかを、共通認識を持っておくことが重要になります。
評価者によって判定にブレがあると、BI評価も曖昧になり、正確に判断しにくくなります。
そのため、共通のマニュアルを作成してBIを実施するのがおすすめです。
2.能力評価ではなく遂行評価を重視する
BI評価を実施するときは、能力評価ではなく遂行評価を重視しましょう。BIは「できるか」ではなく「実際に行っている」を評価することが大切です。
たとえば、理学療法では「歩ける能力がある」と判断しても、実際の生活では転倒が怖くて歩けず、車椅子を使用しているときは、BIでは「歩行:介助あり」と評価する必要があります。
普段している行動を記録することが大切なので、日常生活での自立度を正しく反映させましょう。
3.多職種で情報を共有する
BI評価の精度向上を図りたいときは、多職種で情報を共有を行いましょう。BI評価は、看護師・理学療法士・作業療法士・介護士など、複数の職種で関わることが多いです。
そのため、視点を共有して総合的に判断することが重要です。
カンファレンスで各職種の観察内容を共有し、評価の一貫性を保つことによって信頼性の向上が図れます。
4.定期的な再評価と比較を行う
BI評価の信頼性と精度を向上させたいときは、定期的な再評価と比較を行いましょう。BIは一度だけでなく、経時的に繰り返し評価をすることで、回復や悪化の傾向を客観的に捉えられます。
たとえば、リハビリ前とリハビリ中の評価を確認し、数値の向上が見られない場合は、リハビリ計画の見直しを行うことが可能です。
ほかにも、機能回復が数値ではっきりと分かる場合は、退院時期の判断材料としても活用できます。
再評価のタイミングを、週1や退院時などルール化しておくことで、データの一貫性を保てます。
5.BI評価者の教育と訓練を実施する
BI評価の精度を高めたいときは、評価者の教育と訓練を定期的に実施しましょう。BI評価は、評価者によるばらつきが生まれるケースがあり、正しく評価しないと精度を保てません。
正しい評価基準を理解し、実際の観察スキルを養うことで、評価の再現性を高められます。
たとえば、新人スタッフが初めてBIを行う場合は、経験豊富なスタッフと一緒に実際の患者を評価すると、評価の違いを比較・調整できます。
定期的に、模擬ケースでのBI判定練習やケースカンファレンスを実施して、組織全体の評価制度を維持するのがおすすめです。
医療業界でBIの活用がおすすめなシーン

医療業界でBIの活用がおすすめなシーンは、主に4つあります。
- 急性期・回復期のリハビリの初期評価
- リハビリ効果の経過観察
- 介護保険関連の評価・ケアプラン立案時
- 多職種間でADL情報を共有したいとき
それぞれのシーンについて解説します。
急性期・回復期のリハビリの初期評価
急性期や回復期などのリハビリの初期評価としてBIが活用されるシーンが多いです。BIは、評価がシンプルかつ短時間で済むため、体力が低下している患者にも負担が少ないです。
とくに、急性期では患者の生活能力の全体像を早くつかみ、リハビリ計画を立てるうえで役立てられます。
リハビリ計画の立案や改善に役立てられるため、入院時などに実施するのがおすすめです。
リハビリ効果の経過観察
リハビリ効果の経過観察にBIが活用されることも多いです。BIは患者のADL能力の変化を数値で追えるため、リハビリの効果を客観的に評価できます。
また、同じ方法で定期的に評価することで、回復度合いを比較しやすいです。
チーム全体でリハビリの効果を共有・可視化できるほか、点数変化をグラフ化して記録すると、家族や患者への説明にも役立ちます。
介護保険関連の評価・ケアプラン立案時
BI評価は、介護保険関連の評価やケアプラン立案時にも活用されます。BIの数値は、介護度の目安や、介護サービスの必要性を判断するときに便利です。
具体例を挙げると、BI評価の内容をもとに、自立生活は可能だが一部介助が必要なため、ケアプランに訪問介護やデイサービスの利用を反映させることもできます。
BIスコアは、ケアマネや介護職との共通言語になり、医療から介護への連携をスムーズにします。
多職種間でADL情報を共有したいとき
BIは多職種間でADL情報を共有したいときに便利です。BIスコアは数値がシンプルでわかりやすく、医師や看護師、介護職など多職種間で共有理解が持てる評価指標となります。
ADL情報を共有することで、チームで一貫した支援方針を立てることが可能です。
たとえば、退院支援カンファレンスで、BI点数を提示することで、介護側のスタッフにもADLレベルが一目で伝わります。
BIは医学的専門用語が少なく、チーム全体で理解できる共通言語として使えるため、チームワークを活かした支援を行いたいときにおすすめです。
まとめ:BIの活用で質の高い医療・介護サービスを提供しよう!

BIの活用は、質の高い医療や介護サービスを提供したいときに活躍してくれます。
とくに、短時間かつシンプルな評価になるため、患者への負担も少ない点が魅力です。
リハビリ効果のモニタリングにも役立ち、医療や介護のチームワークを活かした支援ができるため、多くの医療機関におすすめです。
医療や介護の質を高めたいときは、本記事で紹介しているBI評価を試してみてください。


