胃がん(イガン)の原因
癌の広がりにより、早期胃がんと進行胃がんとに大別される。また、悪性度の高い胃がんとにスキルス胃がんがある。胃がんの原因の3割は食べ物にあるといわれ、暴飲暴食も危険因子になるとされている。また、ヘリコバクター・ピロリ菌の感染が胃がんの発生率を高めることが明らかになっているが、ピロリ菌が100%胃がんの発症に関連しているかどうかはまだわかっていない。胃がん(イガン)の症状
上腹部の鈍痛、胸やけ、吐き気、食欲不振などがおこる。早期には症状がみられないことが多いが、進行すると、胃部不快感や嘔吐、吐血、下血などがおこる。胃がん(イガン)の治療
癌の種類により、内視鏡手術や腹腔鏡手術、開腹手術等の手段がとられ、広がりに応じて抗がん剤等を用いる。胃がんの死亡率は年々減少傾向にあり、早期に治療を始めればほぼ治るものになっている。- 受診科目
- 消化器内科
- 内視鏡内科
- 外科
この病気について7人の医師の見解があります。
医師から聞いた
胃がんの対処(治療)方法
7件中1~7件を表示
| 1 | < | PAGE 1/1 | > | 1 |


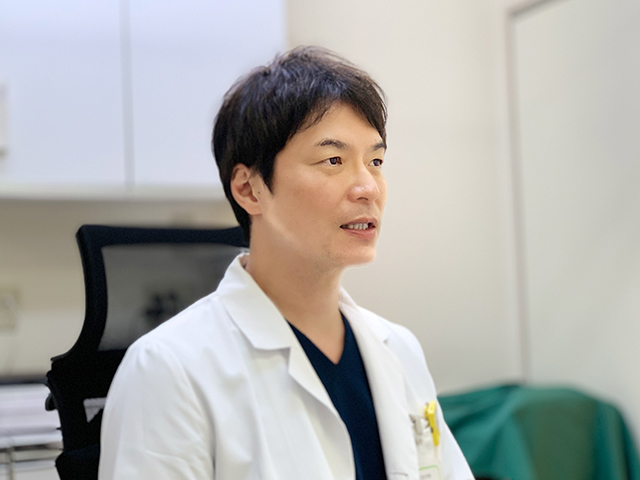
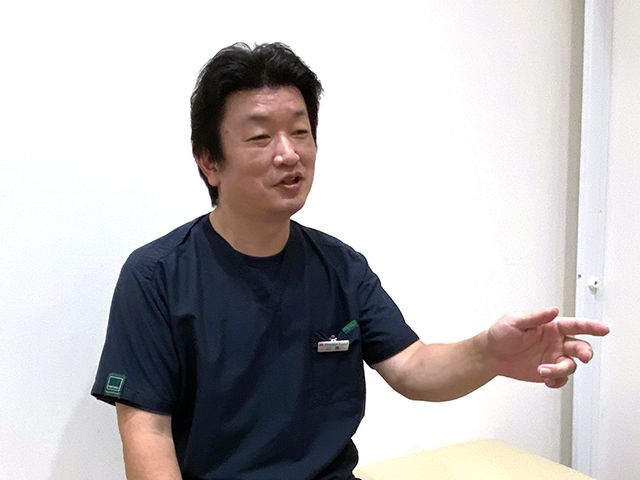




なぜ『胃がん』は早期発見が重要なのか?
胃がんの原因の99%は、ピロリ菌の発生が関与しています。ピロリ菌は3歳くらいの子ども時代に感染しています。昔は井戸水からきているといわれていましたが、現在は親からの経口で感染しているのではないかといわれているんです。
尿素を分解する酵素をつくり、アンモニアが胃酸を中和して、ピロリ菌は自分が住みやすい環境をつくります。ピロリ菌と胃壁の炎症がずっと戦っているうちに、粘膜が徐々に萎縮して炎症を起こし、胃潰瘍や胃がんの発生になります。
2013年に厚生省は、「慢性胃炎があってピロリ菌があれば、保険診療で除菌治療をしていい」と認めました。検診をするとピロリ菌がいるのがわかります。40代50代になると慢性胃炎があり、ピロリ菌がいるマークがいくつかあるんです。一度の除菌治療では、一回あたり抗生剤2種類と胃薬、朝夕1週間飲んで、93%以上成功するんですよ。しかしこれらの病状を自覚するのは不可能なので、定期的に胃カメラで検診することが大切になります。
保険診療で除菌するには、『胃カメラを行った上で慢性胃炎という診断』が必要です。もし、ピロリ菌がいないことがわかっているのであれば、毎年検診する必要はありません。一回も検診を受けたことがない場合は、ピロリ菌がいるかいないかで大違いなので、検診を受けて欲しいですね。