大野 基晴 院長
OONO MOTOHARU
ブライダルチェックから顕微授精まで何なりと。患者さんファーストの不妊治療法をご提案します。
東京都出身。東海大学医学部を卒業後、順天堂大学医学部付属順天堂医院などで研鑽を積み、2017年からセントマザー産婦人科医院にて不妊治療を学ぶ。婦人科系疾患をはじめ体外受精・顕微授精などの高度な医療技術を得意とする。2023年6月に『北千住ARTクリニック』を開業。
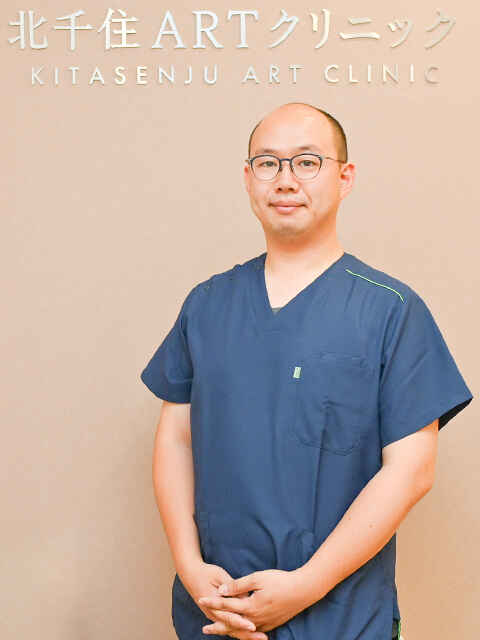
大野 基晴 院長
北千住ARTクリニック
足立区/千住/北千住駅
- ●婦人科
不妊治療のエキスパートとして私を育んでくれた故郷に恩返しがしたい。

実は私は帰国子女で、幼少期から台湾をはじめ何度も引っ越しを経験しているためいろいろな風景や価値観に触れる機会が多く、変化の多い人生でした。しかし、どの国・地域に行っても変わらないものが一つだけありました。それは、歯科医師である父の「患者さんや私たち家族を大切に思う姿勢」です。どのような環境下でも歯科医師としてブレない父を見るうちに「いつか僕も患者さんを第一に考えるお医者さんになりたい!」と感じるようになり、気づいたら医学部を目指していたというわけです。父と同じ歯科医ではなく産婦人科医になろうと思ったのは、学生時代の産婦人科医の恩師が積極的にお産の現場や婦人科系疾患の治療などを見せてくれ、たくさんのインプレッションを与えてくれたからですね。「じゃあ、どうして産科でも婦人科でもなく不妊治療の道に進んだの?」とお思いでしょう。実はこの頃から不妊の分野に惹かれる気持ちはあったのですが…患者さんのケアに携わる日々が充実しすぎていて気づかなくて(笑)。「私たちがこうして命を紡いでいるのは命の神秘あってこそ…休んでいる場合じゃないぞ!」という使命感のようなイメージでしょうか。そんな日々が続いた2017年のある日。ご縁があり不妊治療で定評のあるセントマザー産婦人科で勤務をすることになりまして…初めて自分の気持ちに気づいたんですね。「あ、私は不妊で悩む人たちの助けになりたいんだ」と。それからの展開は早かったですね。患者さんやご家族にとって憩いの場となるような最高の環境作りをスタートし、2023年6月に『北千住ARTクリニック』が完成しました。私を育んでくれた大好きな故郷で、命を紡ぐお手伝いをする準備が整ったのです。
届けたいのは安心。時間とお金がかかる長期戦だからこそ信頼関係を大切にしたい。

開業して間もないですが、私はこの十数年間でさまざまな病院での勤務経験と多数の治療実績がありますので、ブライダルチェックから子宮筋腫・内膜症といった婦人科系疾患の治療までどのような悩みにも対応できます。とくに2022年4月に保険適用となった不妊治療(一般不妊・生殖補助医療)にあたる、人工授精・体外受精・顕微授精などの知識と技術力には自信がありますので、些細なことでもぜひご相談ください。ただ不妊治療はとてもデリケートな問題…。時間やお金もかかる長期戦が予想されるため、信頼関係がとても重要になります。お互いの信頼関係を構築するためにも、まずは患者さんのご事情とご希望をしっかりとヒアリングさせてください。というのも、これまで多くの不妊に悩む患者さんをケアしてきたからこそ思うのは、不妊治療はメンタルケアが非常に重要だということ。「不妊は私のせいなんだ」と自分を責める方、「妊娠できるんでしょうか?」と不安でいっぱいな方、「ゴールが見えなくて辛いです」と感情をあらわにされる方…さまざまですが、このような言いにくいことをまずは打ち明けていただき、私たちを信頼していただくことが治療の第一歩だと思っています。どの患者さんもここにご来院いただくまで十分すぎるほど頑張ってきた方ばかり…せめて『北千住ARTクリニック』では肩の力を抜いて何でも話してくださいね。いつでも私たちは患者さんの味方です。
医学的・年齢的・世間的にどうかではなく、患者さんとご家族のハッピーを第一に考えます。

多くの場合、不妊治療のゴールは妊娠でしょう。しかし、私はただ淡々と患者さんにゴールに向かう治療をするのではなく、患者さんが今後の人生をハッピーに歩んでいけるお手伝いをさせていただいているスタンスです。例えば、私のもとには20~40代の妊娠を望まれる多くの患者さんがいらっしゃいますが、全く同じ治療をされる方は一人もいません。20代の患者さんが「すぐにステップアップしたい」とおっしゃれば私はその意見を尊重しますし、40代前後の患者さんが「自然妊娠で頑張りたい」とおっしゃれば精一杯フォローさせていただきます。また、治療をお望みでなければ無理強いはしませんし、心が追い付いていない状態でステップアップをするようなこともしません。経済的制約・時間的制約の中でも後悔のない治療法を一緒に考えていきましょう。なぜなら、医学的・年齢的・世間的にどうかではなく患者さんとご家族のハッピーが第一だと信じているからです。もちろん、医学的な面ではしっかりと丁寧にサポートさせていただき「北千住ARTクリニックに任せてよかった」と思っていただけるよう精一杯対応させていただきますのでご安心くださいね。
魅力的な立地・動線・最新医療機器・予約システムはすべて患者さんの笑顔のために。
いくら豊富な知識と技術を持っていても、当クリニックを選んでもらわなければ始まりません。そこで女性の患者さんが多いのもあり「チープな言葉のアピールをするのではなく態度で示そう!」と思い立ち、患者さんに選んでもらえるよう立地・内装・スタッフの働きやすさに徹底的にこだわりました。まず都心からのアクセスが抜群に良く、歩いているだけでも心がホッとする街並みが特徴の人気エリア・北千住を選び、少しでも晴れやかな気持ちでご来院いただけるようにしました。内装は解放感を感じさせつつも温かみのある色味にし、患者さんがアットホームな気持ちでいられるような環境を整えています。また、「患者さんの笑顔=スタッフの笑顔」と考えているので、培養士・看護師・事務員さんにとってスムーズな動線と最新医療機器を確保し、患者さんとスタッフにとってストレスフリーになるように心がけています。また、ご予約につきましてもスムーズにお取りできるようにWeb予約システムを完備しています。初診は悩みやこれまでの経緯を丁寧にお聞きしたいので多少お時間をいただきますが、2回目以降はスムーズにご予約ができるため、ぜひ不妊治療と仕事・ご家庭との両立にお役立てください。
これから来院される方へ
『北千住ARTクリニック』は「つくばエクスプレス北千住駅」から徒歩6分の距離にあり、当院は4階にあります。金曜日は終日休診ですが、土曜日は20時まで、第1・3・5日曜・祝日は午前まで営業しています。当クリニックは、これまでの十数年間で得た専門知識と技術を活かし、患者さんの経済的制約や時間的制約を十分に配慮しながら最適な治療法をご提案いたします。そのためには、不妊治療に対する悩みや疑問は一つ残らず打ち明けてくださいね。近年、SNSやブログなどで個人が発信する機会が増え、不妊治療や婦人科系の病気に対して情報が独り歩きしていると感じることもあります。私は男性ですが、これまでの治療実績から患者さんが抱える悩みや疑問、そしてパートナーやご家族が抱える不安も熟知していると自負しています。「こんなこと言ったらダメかな」と思うようなことも想定の範囲内ですので、不妊でお悩みの際はぜひ私にご相談ください。
大野 基晴 院長 MEMO
産婦人科専門医 /生殖医療専門医
- 出身地:東京都
- 趣味:映画鑑賞・読書・ゲーム
- 好きな本:『ハリー・ポッター』『ロード・オブ・ザ・リング』
- 好きな音楽:ロック・パンク
- 好きな映画:『スパイダーマン』『アイアンマン』
- 好きな場所:屋上・犬の散歩コース
- 好きな言葉:『大いなる力には、大いなる責任が伴う』
大野 基晴 院長 から聞いた
『多嚢胞性卵巣症候群』
多嚢胞性卵巣症候群:卵の質が悪いと誤解しないで!適切な予防と治療が大切です。
グラフで見る『大野 基晴 院長 』のタイプ
 |
穏やかでやさしく話しやすい先生 |  |
||||
![]()
| 穏やかでやさしく 話しやすい |
エネルギッシュで 明るく話しやすい |
![]()
先生を取材したスタッフまたはライターの回答より
 |
穏やかでやさしく話しやすい先生 |  |
||
| 穏やかでやさしく 話しやすい |
エネルギッシュで 明るく話しやすい |
|||
先生を取材したスタッフまたはライターの回答より
CLINIC INFORMATION
| 電話 | 03-6426-5933 |
|---|---|
| 所在地 | |
| 最寄駅 | |
| 駐車場 | |
| WEB | |
| 休診日 |



