摂食障害[食行動障害](キョショクショウ)の原因
検査をしても異常がみられないのに、長期にわたって食行動が乱れることを総称して摂食障害とよぶ。摂食障害には、食事をとらずに極度にやせていく神経性やせ症、食欲がとまらない神経性過食症などがある。摂食障害[食行動障害](キョショクショウ)の症状
ダイエットなどをきっかけにして極度に食事を制限する状態が続き、やがて食べようとしても食べれなくなったり、あるいは食べてもすぐに吐いてしまう結果に。ほとんど食べていないにもかかわらず、胸やけや胃もたれがおこる。摂食障害[食行動障害](キョショクショウ)の治療
二次的にからだに異常が出ている場合は、その治療をおこなう。身体療法と精神療法、家族療法などを組み合わせて治療はおこなわれる。- 受診科目
- 精神科
- 心療内科
この病気について3人の医師の見解があります。
医師から聞いた
摂食障害[食行動障害]の対処(治療)方法
3件中1~3件を表示
| 1 | < | PAGE 1/1 | > | 1 |

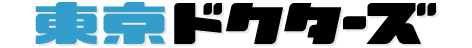


『摂食嚥下障害』の原因や予防法とは?
摂食嚥下障害は加齢や脳梗塞などの疾患により、飲み込みの機能が落ちることが主な原因です。むせてしまう、食事が満足に食べられない、場合によっては誤嚥性肺炎になってしまうことも。食べられないことで体重や筋力が落ちて、からだの衰えや死にもつながります。機能が落ちていくことを食い止めるため、まずは検査をします。実際に食事をしている様子、姿勢、食事の形状(とろみ、大きさ、刻んでいるかどうか)、常食を一緒に食べているのかどうかをチェックします。次に内視鏡検査で何が原因で飲めていないのかを確認します。たとえば、脳梗塞の後遺症で左側に麻痺があって左側の喉の動きが悪い、舌の動きが悪いため食べ物を送りこめていない、嚥下の反射が出ていないなど。原因がわかったら対策をします。たとえば、発生トレーニングを通して舌の筋肉を鍛える、喉の可動域を広げるマッサージをする、窒息しそうな場合であれば肺活量をあげる訓練など、原因によってリハビリのメニューを決めます。リハビリに関しては歯科医やSTさん(言語聴覚士)にみてもらいます。予防法は体力を低下させないために、プールで歩く、犬の散歩をするなど歩く習慣をつけることです。脳梗塞、脳出血、心筋梗塞によって麻痺が起き、動きが悪くなって飲めなくなることもあるため、それらの病気予防にも食生活が重要です。バランスの良い食事、血がサラサラになるような食生活、水分をとる、栄養状態の見直しなど、特別に何かをしなければならないというよりは、健康な生活を送ることがいちばん大切です。