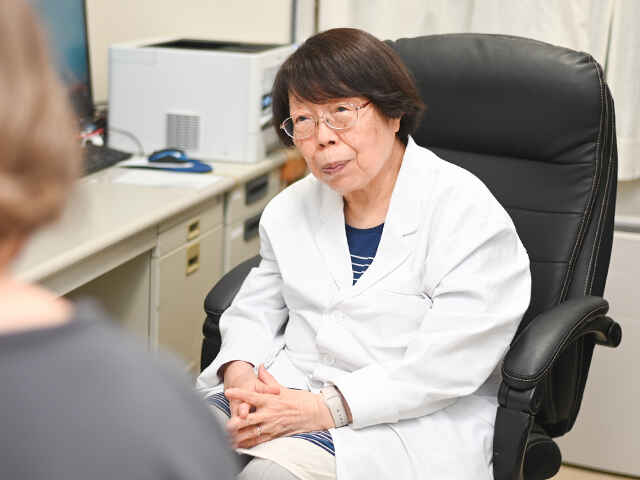西嶋 公子 院長
KIMIKO NISHIJIMA
その人が、その人らしく生きられるように――。医療・介護の垣根を越えて包括的なケアの実現を目指す
東京医科歯科大学(現・東京科学大学)卒業後、小児科医として研鑽を積む。国立小児病院(現・国立成育医療センター)、国立療養所神奈川病院(現・国立病院機構神奈川病院)勤務を経て、1979年に『西嶋医院』を開設。

西嶋 公子 院長
西嶋医院
町田市/成瀬台/こどもの国駅
- ●内科
- ●小児科
- ●訪問診療
子どもの命を救うため小児科医として研鑽を積む

私が医師を志したのは中学2年生のとき、新しいもの好きの父が買ってきた白黒テレビがきっかけです。目が見えない子どもたちにスポットを当てたドキュメンタリー番組に感銘を受け、「眼科医になろう」と思ったことが全てのスタートでした。地元の公立中学校から筑波大学の附属校に進み、まだまだ女性の医学生が少ない時代に当時の東京医科歯科大学から合格をいただきました。私の医学部時代はちょうど大学紛争が起こった時期に重なり、私自身も常に「医学とは、医療とはどうあるべきか」を考えながら過ごしていたことを覚えています。社会の仕組みのどこかに矛盾があるならば、それをどうやって変えていくのか、という視点を持つようになったのもこの頃からでした。
大学卒業後は、小児科の医師として経験を積みました。医学部に入った当初は眼科に進むことを考えていたのですが、臨床実習のときに白血病のお子さんを担当したことで「小児がんを診たい」という気持ちが強くなり、この領域を学ぶために当時の国立小児病院の血液科で勉強させていただきました。在籍した5年間に受け持った患者さんは100人を数えますが、そのうち命を救うことができたのはわずかに2人だけでした。「医療だけでは解決できないことがある」……そのことに気付かされたつらい経験ではありましたが、当時8か月だった子が今も私の患者さんでいてくれることが、診療を続けるモチベーションになっていることは確かです。
開発が進む成瀬台に開業して約半世紀

小児科医として独り立ちしてからは、国立小児病院と国立療養所神奈川病院を掛け持ちするような形で診療し、母校の難治疾患研究所では白血病のDNA研究にも従事しました。臨床に、研究に、と多忙な日々を送るなかで医師9年目の1979年に『西嶋医院』を開設し、それから5年後の1984年に研究論文をまとめて博士号を取得しました。この地域の医療に携わって半世紀近くになりましたが、患者さんにとって身近な場所で、地域全体をまるごと診るような気持ちで診療を続けていることは、今も昔も変わることはありません。
クリニックを開いた1979年は成瀬駅が開業を迎えた年でもあり、この地域の開発が進められていた時期でした。新しい街が形づくられていくのに合わせてファミリー世帯が多く流入し、小児科と内科を掲げる当院には、1日に100人を超えるお子さんが通院されていたと記憶しています。しかし時間の経過とともに地域にお住まいの方も年齢を重ね、いろいろなところに不具合が出てきました。以前の建物は2階まで階段でお越しいただく必要があったため、「2階まで上れない」という声をいただくようになったのです。そのため成瀬台の中で候補地を探し、1999年に現在の場所へ移転してきました。
「その人らしく生きる」をサポート

新しくなった『西嶋医院』の建物は1階がクリニック、2階が通所リハビリテーション(デイケアだんけ)になっています。クリニックでは今も変わらず内科と小児科とを柱に診療するほか、訪問診療に力を入れていることも特徴です。月曜日から土曜日の午前中は外来診療、月曜日から金曜日の午後は訪問診療の時間にあてることで、地域の方々の健康と暮らしを支えていきたいと考えています。
訪問診療をスタートしたのは、私の父が認知症になったことがきっかけでした。一時的に入院することになった父の元を訪れた際に、高齢者の医療・介護の問題に直面したことで、「その人がその人らしく生きられるようにするには、どうしたらいいか」を考えるようになったのです。患者さんの高齢化を背景にクリニックを新築移転したように、来るべき高齢化社会に向けて何をすべきかを考え、一人の医師として、この地域に暮らす住民として取り組みを続けてきました。
地域包括ケアのパイオニアとして
『西嶋医院』を開設した1979年当時、この地域の新たな住民となられたのは40~50代が中心でした。それから時は流れて今、成瀬台の高齢化率は40%近くになり、町田市の中でも特に高齢化が進んだ地域になっています。私はクリニックを開業した当初から成瀬台の現在の姿を予想し、今後は「地域の中での支え合い」や「医療と介護の連携」が必要になるだろうと考えていました。介護保険制度がスタートするずっと前から、「地域包括ケア」という言葉がまだない時代から、住民参加型の街づくりを目指してきたのです。
私が最初に立ち上げたボランティアグループ「暖家(だんけ)の会」は、クリニックの患者さんやご家族に声をかけて1989年に結成しました。翌1990年にはホスピスツアーでアメリカ東海岸を訪れ、真のボランティア精神とは何かを学びました。自ら動くことの大切さに気付いた私は1992年、4,500人分の署名を集めて町田市にケアセンター建設を提言しました。これが、1996年に開設されたケアセンター成瀬です。施設には特別養護老人ホームやデイサービスが併設され、地域福祉推進の中核的な役割を担うと同時に、地域の方々の支え合いの場にもなっています。
これから受診される患者さんへ
私は現在『西嶋医院』の院長を務めるほかに、医療・介護サービスを展開する法人グループの理事長なども兼務しています。これまでの取り組みが評価され「地域に密着して人々の健康を支えている医師」として日本医師会から表彰(赤ひげ大賞)を受けたこともあるのですが、医師としてはやはり、患者さんから感謝の言葉をいただいたりしたときに喜びや、やりがいを感じます。医療・介護サービスが整備された「この地域に住んでいてよかった」……そう言っていただけることが私にとっては一番うれしいことです。
私たちのことを頼りにしてくださる方々のためにも、今後も人をみて・地域全体をみる医療や介護を展開してまいります。医療分野ではがんの早期発見や予防医療に積極的に取り組み、介護分野ではグループホームやデイサービスなどさまざまな形で「その人らしい暮らし」を支えていきたいと考えています。何かお困りのことやご心配なことがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
※上記記事は2025年6月に取材したものです。時間の経過による変化があることをご了承ください。
西嶋 公子 院長 MEMO
- 出身地:東京都
- 出身大学:東京医科歯科大学
- 趣味・特技:絵画鑑賞、博物館めぐり
- 好きなドラマ:「『暴れん坊将軍』など、時代劇」
- 好きな観光地:フランス
- 好きな言葉・座右の銘:「人の痛みに寄り添う心」
西嶋 公子 院長から聞いた
『認知症』
「他者との交流」こそが認知機能維持に役立つ
認知症についてはお薬による治療よりも、非薬物療法によるアプローチが有効です。非薬物療法とは文字どおりお薬を使わず、他者との交流によって認知機能の維持を目指す方法です。たとえばデイケアなどの通所サービスを利用して、家族ではない第三者と会って話をすると脳が刺激され、認知機能にもよい影響をもたらします。
高齢者を1人ぼっちで家に閉じ込めるようなことは避け、社会性を保てる環境を整えてあげることが、認知機能の維持に有効であることをぜひ知っていただきたいです。
グラフで見る『西嶋 公子 院長』のタイプ
 |
エネルギッシュで明るく話しやすい先生 |  |
||||
![]()
| 穏やかでやさしく 話しやすい |
エネルギッシュで 明るく話しやすい |
![]()
先生を取材したスタッフまたはライターの回答より
 |
エネルギッシュで明るく話しやすい先生 |  |
||
| 穏やかでやさしく 話しやすい |
エネルギッシュで 明るく話しやすい |
|||
先生を取材したスタッフまたはライターの回答より
CLINIC INFORMATION
| 電話 | 03-6426-5933 |
|---|---|
| 所在地 | |
| 最寄駅 | |
| 駐車場 | |
| WEB | |
| 休診日 |